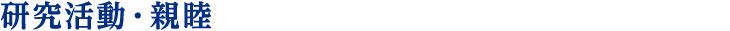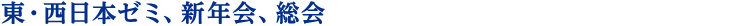高塚謙太郎氏 講演
高塚謙太郎氏 講演詩についてのメモ
1 詩を起動させるプログラムというものがあるという立場、もしくは詩そのものがそもそもプログラミング言語である立場がある。いずれにせよ誰かがそのプログラムを起動させることで詩は現れる。その時に、その詩から読み手に何かが伝わったといってよいのか。書き手はプログラムもしくはその走り方を仕組んだだけに過ぎず、走り出したプログラムを読み手自身が処理しているに過ぎない。読み手は、読み手の感動を、感動しているだけだ。
2 私の感情と私の書いた詩とは無関係だ。ただ、何らかの関係を誰に対しても明白な形で浮かび上がらせることができず、にもかかわらず関係というものはあるのだという性質だけをそこに残す、いわば関係-性のようなものがあるに過ぎない。人間の感情(心)を詩の根源性に据えた言説の多くは単に詩というものに実装させるガジェットとして「心」を使用しているに過ぎない。
3 目の前に並べられた詩の行と、書き手の実存みたいなものは無関係だ。ところが実存を詩についての言説に絡めると、人間性や人間の深淵といった「人間」というものの重みがのしかかってくる。これは「人間」を特異点におく全体主義だ。人間性という非人間的制度によって、詩が価値づけられているという事態が起こっている。詩は、あらゆるイデオロギーを支えているのとまったく同じ言葉(プラットフォーム)によって結構されているのにも関わらず、あらゆるイデオロギーからもっとも遠く離れて存在しているはずだ。もちろん、詩はどうしても常に何らかのイデオロギーに連絡され回収され続けるが、それと同じ速度で詩篇はイデオロギーから逃れるように飛散していっているはずだ。
4 「詩を書くことが許されない時にこそ詩が生まれる」という、いわば詩そのものに超越論的位置を与える言説は、詩を書くという行為の神秘化および絶対化を強く促してしまう。あるいはそのような行為に至る過程そのものに気持ちの悪い甘えの構造を導入してしまう。このように特権的に生み落とされた詩は、端的にそして必ず戦意昂揚詩に他ならない。無意味に詩の神秘化を促すことで詩はいつでも簡単に戦意昂揚のための装置になれる。そのフレームの中で詩を書くということは、相当に野蛮な行為である。
5 詩はそもそも制作と同時にイデオロギーとともに存在してしまうが、詩の生成は手作業だけに拠る。ところが、詩において、書き手のイデオロギーのみが価値として語られてしまう。詩は技術の研鑽の歴史だったはずだ。私はその気風だけを負いたい。人間性という威嚇の前に詩を置いておくつもりはない。詩を生成するものは技術でしかない。人間性の威嚇からは距離を取る必要がある。詩を詩たらしめるものは、意味内容やメッセージ、作り手の心ではなく(もちろん意味やメッセージ、心があってもいっこうにかまわないが、それは絶対条件では決してなく)、言葉の技術もしくはその結果だけだ。詩とは、単に技術である。詩については、この位置から語り始めるしかない。