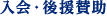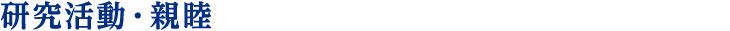講演「大江満雄の対話の詩学」 講師 木村哲也氏
講演「大江満雄の対話の詩学」
講師 木村哲也氏

講演する木村哲也氏
私は東村山市にある国立ハンセン病資料館に勤務。今年三月に「大江満雄セレクション」を発行したことから、お招きいただいたと思っています。
高知県宿毛市出身の私は、中学三年の時、八〇歳の大江満雄に会ったことがあります。『東京宿毛会』という集まりで、中学生の私を子ども扱いせず、情熱的に詩の話をしてくれたので、とても印象に残っています。
その後、私が大学二年のとき、大江満雄(八五歳)の訃報を新聞で見て、お別れ会に行きました。そこではお別れの言葉を鶴見俊輔氏が述べられていたので、鶴見氏と面識ができました。しばらくして大江満雄を読みたくなると、著書がどこにもない現実があり、若気の至りで鶴見氏に大江満雄全集みたいなものができないか、相談しました。すると鶴見氏は「思想の科学社で良ければ協力しましょう。」と真摯に返事をくれました。
編集には、森田進氏、渋谷直人氏、私、鶴見俊輔氏の四人が入り、大江満雄が亡くなった五年後の一九九六年に思想の科学社から「大江満雄集―詩と評論」を発行。この編集の過程で大江満雄とハンセン病の人との関わりが判り、大学院生だった私は、今なら大江満雄を知るハンセン病の方から話が聞けると、行動しました。
一九五三年、大江満雄は全国八つのハンセン病療養所の入所者七三名の合同詩集「いのちの芽」を編んでいます。その参加者は高齢となり、今ならまだ、かろうじてお話が聞ける状態でした。
戦後のハンセン病文学が軽んじられ、紹介が遅れていると痛感していたなか、今の資料館の学芸員に採用され、ちょうど「いのちの芽」が出て七〇年目の節目に、資料館で企画展として復活させることができました。
大江満雄は、今こそ読み直されるべき詩人ではないでしょうか。本日はエッセンスを三つ、話します。
一つ目は 「一貫する他者志向」。 大江満雄は、台風の水害で一家離散し、父親と東京へ上京するも、父も他界。一四歳で親戚に預けられ、余儀なく自立を強いられます。
二二歳の時に、第 一詩集「血の花が開くとき」を出します。上京した一九二〇年代に見た長屋暮らしの人々を捉えた東京が、スケッチとしてよく書けている良い詩集です。片隅で生きる人たちへの思い、他者とともにあろうとする思考が垣間見られます。
二つ目は、転向と戦争詩の評価。プロレタリア詩人として活動した大江満雄は、治安維持法で三ヶ月拘留されて転向を余儀なくされます。しかし、戦争詩を書かざるをえなくなった大江満雄の戦争詩は、選び抜かれた緊張感のなか、 勢いで書く安易な戦争詩とは違っています。一九四三年発行の「日本海流」には、転向直後の大江満雄のどこにも行けない、死んだと同じ心境を戦場の死者に重ね合わせ、「心渇ける」と言っています。
大江満雄はクリスチャンで、磔にされたイエスの最後の言葉にある「渇く」に、自分を磔にされたイエスに投影しているとも読めます。
又、一九四二年発行の「国家と詩」のエッセイは、日米開戦後で国への批判が一切できない状況下で書かれたものですが、再評価されるべき内容で、歴程に掲載されたものです。
一九五五年には鮎川信夫による批判がありました。戦争協力詩の合同詩集『辻詩集』(1943年)と、戦後、アメリカの水爆実験に抗議した合同詩集『死の灰詩集』(1954年)の共通点を指摘し、空疎なプロパガンダに堕していることを鋭く批判したもので、その中で大江満雄は名指しで槍玉にあげられ、大江満雄の低評価は、これが原因なのでしょうか。思潮社の現代詩文庫と土曜美術社出版販売の日本現代詩文庫に大江満雄は入っていません。日本現代詩人会の発起人五人のうち、大江満雄だけが文庫にないのです。
三つ目は対話思想の展開です。
戦後、大江満雄は、二度の挫折を経験します。言論の弾圧による転向と戦争詩を書いたら、その社会がひっくり返り、価値観が崩壊したという二つの挫折。そこから、どう詩作を始めるか。
人と人は、互いに距離を持って存在し、その距離を埋めるのが対話。その対話のためにあるのが詩だというのが、大江満雄のたどり着いた戦後の詩です。
大江満雄の対話詩は、単に人間だけでなく、植物や自然も対話の相手としていました。「花」という詩がとても良いので、これを紹介して終わります。
あそこに/いま 真っしろい 浜木綿の花が咲いている。
あの花の そばに/波が たえまなく 打ちよせている。 アキ有り
あの花を/わたしが いちばん よく識っている といいたくなる。
あの花は/わたしを知らないのに。
これはとても美しい対話詩。花と対話をしている。この詩人の発足させた会が、日本現代詩人会ということで、本日はありがとうございました。
(文責・沢村)