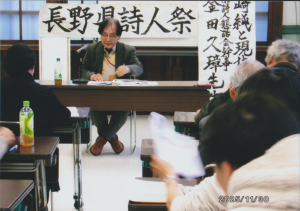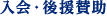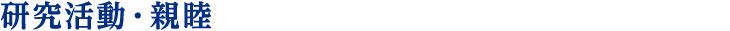講演会報告 第36回長野県詩人祭
講演会報告 第36回長野県詩人祭
期日 令和七年十一月三十日(日)
午後一時四十分
会場 松本市あがたの森文化会館
講師 日本現代詩人会会員 金田久璋氏
演題「詩人岡崎純と現代詩の先端」
一岡崎純の詩を読む―第4回蝸牛忌の朗読作品から
今年七月五日に岡崎純を偲び、開催された「第四回蝸牛忌」に参加の十六名が各自選び朗読した岡崎詩を紹介し、詩人の詩、生き方に触れた。二〇一七年八七歳で物故した岡崎が蝸牛好きだったことから「蝸牛忌」としたこと等を含め、氏の朗読と語りは、岡崎作品の魅力を充分に伝え、感銘を深めた。
二岡崎純の詩歴とその詩論
―金田久璋著『瞬間の王と現実の王』参照
①『土星』の詩人・杉本直と『時間』のネオリアリズム
②寓喩と「小さな抒情的叙事詩」
③「対比を超える」ということ
岡崎純が学生の頃に師事した『時間』の同人杉本直(詩集『土星』を出版)のネオリアリズムによる感化と影響について話を進め、「特異なリアリティーの表出」がみられること、最後の詩集『寂光』(第30回日本詩人クラブ賞受賞)に収めた詩「逆水」に関し、金田氏が『詩と思想』に書いた解説文を紹介。岡崎純が終生、大切にした「言葉の単純化」や、禅の教えに基づく「対比を越える」のオンリーワンの精神を重視。中野重治のエッセー「素朴であること」に準拠した岡崎の詩は、珠玉の詩だったと思う。安易なオノマトペに寄りかからず、比喩に立脚し、形而上的な視点にたち、哲学的世界を表現。岡崎純の詩は「多声的」であり、庶民、常民の声を詩にしていて、村の習俗について寓喩を援用し「小さな抒情的叙事詩」として表現した云々。説得力のある言葉が強く印象に残っている。
三現代詩の先端としての青年、高校生の作品と傾向
詩のコンクール受賞作品から高校生の詩を二編紹介。しめくくりとして金田氏の近作六篇を朗読し、本講演会を終えた。
講師の金田久璋氏は周知の通り、民俗学者の谷川健一を師として学び、現在、「日本地名研究所」(川崎市)所長を務める。福井県が生んだ著名な詩人岡崎純と日常的に深く関わった中で、交流の実績(資料)に基づく具体的で分かりやすい講演内容だったことを申し添えたい。
(長野県詩人協会会長 酒井力記)