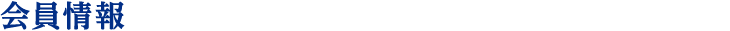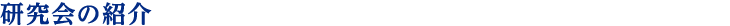各地のイベントから(会報154号から)
各地のイベントから(会報154号から)
第58会中日詩祭」開催
掘りつづけよ、自分を超えて。

講演する平林敏彦氏
第58会中日詩祭が、昨年七月一日(日)午後一時より、名古屋電気文化会館で開催された。
冒頭の挨拶で、会長の若山紀子氏は、沖縄全戦没者追悼式で朗読された中学三年生の詩に触れた。「私は、今生きている。未来は、この瞬間の延長戦上にある。つまり、未来は、今なんだ」という一節をあげ、これが本当の詩の力である、たった一人でも感動してもらえるような詩を創ろうと呼びかけた。
詩祭の第一部として、第58回中日詩賞、新人賞の贈呈式があった。中日詩賞は、中村薺氏の『かりがね点のある風景』に贈られた。新人賞には、中谷泰士氏の『旅を 人の視界へ』が選ばれた。期せずして、お二人とも石川県在住である。受賞の挨拶と詩の朗読があった。
第二部では、「昭和の戦中戦後の詩を語る――金子光晴、近藤東、そして『荒地』まで」と題する平林敏彦氏の講演があった。長い詩歴の中で(平林氏は一九二四年生まれ)出会った詩人たちについて、エピソードを織り交ぜ、熱く深く語られた。
「当時の詩人同士の付き合いは濃密で、私生活がお互いにわかってしまうような近さがありました。『荒地』の詩人たちもそうでした。今は自分の周りの詩しか読んでいないし、交流も狭いので、寒い気がします」
「昭和一七年から一九年頃、詩の投稿をしていました。選者は近藤東でした。近藤さんがいなかったら今の自分はいません。近藤さんは昭和一九年に『百万の祖国の兵』という詩集を出しています。これは、戦争応援の詩集ではなく、ウイットを効かせたサタイヤを徹底的にやったモダニズムです。今読むと、パラドキシカルなのがわかります」
第三部は、「詩のこころを読む~わたしの好きな詩と詩人たち」と題する劇車銀河鐵道・いちかわあつき氏によるひとり語り。心安らぐ口演だった。(文責 古賀大助)
横浜詩人会六十周年記念講演会
日時 2018年10月28日2時半
会場 ブリーズベイホテル桜木町

講演する中村不二夫氏
六十周年記念講演会は、実行委員会が設けられて、横浜詩人会の会員でもある中村不二夫氏に依頼した。
七十数名というご出席者を得て開催された。
講演要旨は創立の最も原点の、近藤東・篠原あや・長島三芳、三氏の詩的活動とその原点を語り、プリントの詳しさ、内容の貴重さから、大成功であった。
まず、近藤東・一九〇四年岐阜生まれ明治大学をでて鉄道省に勤務。同年春山行夫らと、「詩と評論」創刊。
翌年「レーニンの月夜」で改造社の詩の懸賞に入賞。以後、モダニズム詩の旗手として活躍。わが日本現代詩人会の一期の幹事長でもある。
篠原あやは、戦前「令女界」の投稿の常連で、根っからの文学少女。だが戦後は、ヨコハマファーストを掲げ、横浜詩人会では、近藤東を助けて旗挙げの手伝いを果たしてきた。会計も一手に担い事務から会報から大活躍をしてきた。「大岡川」という詩の素晴らしい連作がある。昭和二十年代後半から「象」という同人誌を創刊。多くの詩人を擁してきた。
長島三芳氏は、一九一七年横須賀生まれ、横浜専門学校【現・神大】を卒業。詩人会発足当時は、大手の印刷会社に勤務していた。
規則に厳しい近藤が、横須賀の詩人を仲間に入れた理由は、ホースネック文化という横浜の詩人文化人のたまり場での友人であったからで、長島三芳は、日本未来派発行の「黒い果実」の詩集でH賞の第二回目の受賞をした。
日本現代詩人会からは、講演会に当たりご後援を頂きました。感謝申し上げます。(横浜詩人会 植木肖太郎)
ちば秋の詩祭
充実した大会に!

講演する 山田隆昭氏
11月4日(日)「第40回ちばの秋の詩祭」(主催:千葉県・千葉県詩人クラブ、後援:千葉市、日本現代詩人会、日本詩人クラブ)を千葉市生涯学習センター・小ホールで開催した。この詩祭は毎年、千葉県県民芸術祭の催しの一つとして行っているものだ。
会は午後1時に始まり、第一部として5人の会員が登壇し詩の朗読を行った。新会員や新しく詩集を刊行した人たちで、聞くものをそれぞれ個性的な詩世界にいざなった。
第二部は文芸講演。山田隆昭氏による「山頭火と放哉の俳句 ―出家と遁世―」である。
ともに荻原井泉水の弟子であり同時代を生きた二人の自由律の俳人。行乞して全国を徘徊した稲田山頭火、各地の寺に移り住んで句作をした放哉。山田氏はこの二人の生涯と代表的な俳句を対比的に取り上げ、分かりやすい解説を加えていった。まず井泉水を中心とした自由律俳句の運動と、内面性や精神性を重視した俳句の魅力を紹介。
次に山頭火のこと。放浪と行乞を重ねて転々しながら「秋風、行きたい方へ行けるところまで」「風鈴の鳴るさへ死のしのびよる」「笠にとんぼをとまらせてあるく」といった句をつくり、死と向き合い、酒を欠かせなかった。
放哉は人間の本質的な淋しさに向き合った人。「久しぶりの雨の雨だれの音」「わがからだ焚火にうらおもてあぶる」といった句のように孤独な寺住まいの暮らしの中で作句した。山田氏は二人の生と句から詩人に通じる精神のありようを提起されたと受けとめた。
第三部は詩劇「中原中也物語」。当会会員の末原正彦氏の脚本で、中也の生涯を丁寧に辿ったもの。語り手の上手さ、中也、長谷川康子、小林秀雄の各演者を中心に総勢12人もの出演者の熱演で会場を沸かせた。
会場内で展示された恒例の詩画・詩書展では特別展示として県内の同人誌や文芸誌19誌集めて紹介、各誌との交流を図った。各詩画も独特な組合わせやアイデアに溢れていた。
第40回という歴史的節目の会を充実した内容で行ない、会は新たな一歩を踏み出すことができた。(根本明・記)
群馬詩人クラブ
第31回「秋の詩祭」

講演する原田道子氏
「秋の詩祭」は、十一月二十五日、前橋テルサに於いて開催した。当会幹事の三枝治の司会で幕を開け、川島完氏の講師紹介後、和装ではなく洋装の原田道子氏の登壇で、演題は、いま、原田氏が取り組中のディキンスンに纏わる「エミリ・ディキンスンを読む―ことばの綱目―」です。言葉の綱目とは、言語の綱次第で砂地には様々な模様が描かれるが、綱を取ってしまえば元の砂地であり、翻訳詩は翻訳者次第で変ってしまう。その国の文化を理解してないとできないものと言った、各国の歴史を生きてきた文字、その文字を活かすこと、即ち各国の文化を置き去りにできないのは翻訳にも言えると言うのだ。そして、ディキンスンの話になると熱を帯び、一八三〇年にアメリカはニューイングランドのアマスト生まれで、ほとんど人と会うこともなく、五十六年の生涯を信仰告白を拒否し、思考を深め、三十代なかばに一番詩を書いたが、詩集は出さなかった、と話を進め、タンスに残された一七七五篇は、妹のラビニアにより世に出された。詩の一行目がタイトルで、大文字の多用、ダッシュの多用が特長だと言う。外に出ることの少なかったディキンスンの世界は狭く、花や木、虫たちとの触れ合いで、小さなもの(ミクロの世界)から大きな意味(マクロの世界)を見い出したと言う。源詩を朗読テープで紹介しながら、資料での講演に会場はディキンスンにか、原田道子にか、どちらに魅せられてか熱心に聞き入っていた。原田氏にとり久しぶりの故郷、そう言えば「たまには群馬に帰っておいでよ」が、私からの講演依頼であった。講演なかばで「嵐の夜―嵐の夜」でWildを〝嵐〟でなく未来に広がる自然の風景を感じると言い、theeは〝あなた〟でなく、〝神〟と訳したい。ディキンスンの詩は短いが、そこに多くが語られていると言う。ディキンスンの詩に触れたことがない私でも、読んでみたくなる、そんな講演であった。(文責 堀江泰壽)