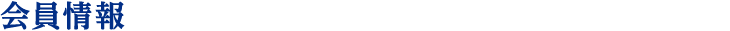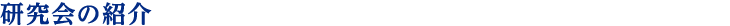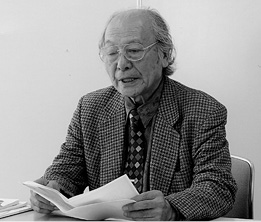各地のイベントから(2016.12.20受まで)
各地のイベントから(2016.12.20受まで)
●“いのちの余韻にひたる〟
―菊田守先生を三重にお迎えして
「みえ現代詩の会」 代表 津坂治男
私たちの「みえ現代詩」が一〇〇号を迎えたのを機に、この九月二十五日、鈴鹿市白子のホテルに日本現代詩人会元会長の菊田守氏を迎え、〈生きものたちの詩〉というテーマの講演会等を催した。
参加者は、会員中心に、地元の芸術文化協会や三重県詩人クラブのメンバー、また東海地区の同人誌の有志(中日詩人会を含む)など二十数人が最後まで聴き入り、意見交換など行った。氏の代表詩集である『日本昆虫詩集』等をもとに作成されたテキストに描かれた小さな生きものと人間との関わりなど、自然が豊かな当地の人々の共感を呼んでいた。
「みえ現代詩」同人の朗読などをはさんで、五時からは、テーブルを囲んで一時間にわたる懇親会。菊田氏が赴かれる各地の模様などもお聞きし、ともすれば「井の中の蛙」になりがちな私たちには、認識を明らかにすることも多かった。興深まったところで散会、この収穫を今後必ず生かしていくことを誓いながら……。
なお、日本現代詩人会からは催しに対し過分の賛助金をいただき感謝いたしております。
●岩手詩祭2016
岩手県詩人クラブ会長 東野 正
「静かな言葉が、心の中に嵐を呼び起こす」をテーマに、「いわて詩祭2016」を花巻市市民交流センター(花巻市)で10月16日に開催した。参加者は24名である。
詩祭の第一部では、岩手県詩人クラブの第5代会長で日本現代詩人会員でもある渡邊眞吾氏が「自作詩を語る」と題して講演を行った。講演の中では、その詩作の成立の背景や書こうとした時の動機などに触れながら、自作詩7編が朗読された。最近の詩作のテーマとしては、東日本大震災で亡くなった友人への想いや、反戦・非戦の訴え、そして老を見つめることなどに変わってきているとのことで、それをテーマとした詩作品の完成度の高さを、参加者は感受することができて有意義な講演となった。
第二部では、岩手県詩人クラブが毎年刊行している年刊アンソロジー詩集「いわての詩 2016年版」に収録されている作品の朗読会を行った。このアンソロジーは一人40行以内という制限の中で編集しているもので、朗読する側そして聞く側にとっても適当な長さであるため、参加者の意識の集中状態が継続した朗読会となった。
第三部では、四グループに分けて合評会を行った。グループ分けしたことにより、一作品に三〇分近い時間をかけてじっくりと作品を鑑賞しながら合評することができた。合評会の最後の全体会で、グループ別に討議内容の報告を行ったことで、合評会の討議結果の全体が共有された有意義な時間となった。
終了後は別会場で懇親会を開催して充実した祝祭日となった。
●現代詩セミナーin神戸2016
「新しい文学視像を求めて」
と き 10月22日(土)13:00~15:20
ところ 神戸女子大学教育センター
講 演 藤井貞和氏
講演を巡っての討論:藤井貞和・京谷裕彰・たかとう匡子・松尾省三・会場全員
毎年、神戸女子大学を拠点に開催して、今年で10年目を迎えるこのセミナー。主催は現代詩セミナーin神戸実行委員会ですが、毎回神戸女子大学・思潮社さんに共催していただいておりますが、今年は日本現代詩人会の後援をいただくことができました。
石牟礼道子さんの長い表現言語を通じて、詩の言葉と世界のつながりを再検討するのが今回のテーマでした。詩の言葉でどう社会と、世界と繋がっていけるのか。石牟礼さんの表現活動を見つめることで、新しい言葉、新しい表現について考えてみました。
藤井貞和氏は3/11の原発の事故後『苦海浄土』を読み直して「自分もああいった正確な日本語で表現できたら…」といった若松丈太郎氏の言葉を引いて「正確な日本語」について、また、石牟礼道子氏の言葉「近代詩でも古典の詩でもない、違った表現が欲しかった…」から、新しい詩の形について話された。また、「祖たちの邑」へつながる石牟礼道子氏の高群逸枝論、森崎和江「からゆきさん」から「慰安婦」へと話は広がりました。
シンポジュウムになると、「石牟礼文学からロマン主義を考えたい」「科学に対して詩人はどう立ち向かうのか」「言葉が届かない。内と外とを結びつけるのが困難」「言葉が衰退している。状況の中に巻き込まれることをおそれないこと」などと言うパネラーに対して会場から「言葉は現実を切り離す。個の声を拾い上げるのが石牟礼文学だ」「近代の呪術師にならねばならない」「詩には批判が必要だ」「津波で失ったものは人・物・人と人との関係・習慣など…。失ったものを石牟礼さんは書いている」など活発な意見が出されました。
仙台・長崎・東京・鳥取・徳島・岐阜・松山・広島・岡山など遠方からの参加者も交え総勢100人。熱い議論に沸騰しました。
その後15人の有志(一瀉千里・今西富幸・植山和美・大倉元・大西隆志・神田さよ・斎藤恵子・柴崎修平・白鳥真・野田かおり・福田知子・藤井貞和・藤井雅人・船曳秀隆・渡辺めぐみの各氏〈五十音順〉)による朗読に耳を傾けました。
場所を移しての懇親会では、各地から参加された方々のご挨拶、最近の活動などが話され、大変有意義な交流ができました。ご後援ありがとうございました。 (文責 中塚鞠子)
●いばらき詩祭2016 古河(茨城県詩人協会主催 日本現代詩人会後援)
十月二十九日に開催され、古河市在住の山本十四尾氏、粕谷栄市氏の両名誉会員の講演が行われた。
山本十四尾氏は「詩の会を続けて十六年~花話会について」という演題で、百十九回続く「花話会」の活動について講演した。
「花話会」は、現在、全国の詩人の、詩に対する考え方や創作の姿勢など(詩姿と呼んでいる)を実際の作品と併せて学び、冊子としてまとめる活動をしている。
また、人生の幸、不幸につきものである花を取り上げた詩を募り、優れた花の詩を後世に残そうという活動も行って来た。
その結果、全国の二百五十人を超える詩人の「詩姿の原点」と花の詩の『アンソロジー花音』を継続して出版している。
粕谷栄市氏の演題は「詩と私」。
『アンリ・ミショー詩集』との出会い、石原吉郎に散文詩をほめられたことなどがきっかけで、散文詩ばかりを書き続けて来た。
『世界の構造』の後、十数年、詩を書かなかった間に、自分の詩を読んでもらいたいと思う人たちが亡くなってしまい、詩は人間が生きていてこそのものだと痛感した。同時に自分が同時代の人と生きている手応えを確認するために詩を書いていたことに気づき、死ぬまで作品を書こうと思った。
詩を書く時に心がけていることは、内容が自分にとって新鮮であること。書くのはいつも散文詩だが、中身は常に初めて書くことでありたいと願っている。
詩を書いて生きている人間には、詩のことを何でも相談できる友人が必要だという粕谷氏の言葉が印象に残った。
(文責 茨城県詩人協会 生駒正朗)
第三十八回ちば秋の詩祭から
千葉県詩人クラブの平成二十八年度秋の詩祭が、十一月六日(日)、千葉市生涯学習センター、小ホールにおいて開催された。好天に恵まれ、参加者七十八名という、立ち見が出る程の盛況であった。
講演の講師には北畑光男氏をお迎えした。講演の題は、「詩のリズムについて~村上昭夫から現代まで~」。戦中と戦後の動乱に翻弄され、また胸の病とも戦いながらという、村上昭夫の人生と詩作についてのお話が中心であった。大陸で捕虜となり、引き上げを経験し、病で入退院を繰り返して、四十一歳の若さで亡くなった村上昭夫。常に死と隣り合わせている中であったからこそ、生あるもの全てに底通する、深い悲しみを湛えた詩が産まれたということがよく分かった。このほか、村上昭夫と行動を共にした同時代の詩人たちや、現在活動中の新進の詩人たちの詩も紹介され、広く目の行き届いた講演であった。
詩祭ではこのほか、千葉県詩人クラブの会員五名により、自作詩の朗読発表が行われた。また、「日本の詩を歌う」と題して、千葉市音楽協会の会員有志、総勢三十二名による合唱もあり、盛りだくさんの内容であった。
今後とも、詩を中心とした活動の活性化を図るとともに、県内の他の文化団体とも連携を深めていきたい。(文責 秋元 炯)
「詩に戻る」
2016 熊本詩祭に触れて
甲斐ゆみこ
2016熊本詩祭―とどまる声、うたう耳―は、震災後七か月の十一月十二日の午後のひととき、カフェレストラン「みなみのかぜ」(熊本市)において、詩画詩稿展、朗読、講演、バイオリン演奏など三部構成のプログラムで開催された(出席者四十名)。今回、地震後の詩祭ということもあり、日本現代詩人会(新延拳理事長)の後援を受けることができたのは幸運であり、大きな力となった。紙上を借りて感謝したい。県内外の詩人も駆けつけ、県詩人会の催しとしては、異例の内容の濃い充実したものとなった。
第一部、詩の朗読では、県詩人会会員十四名がそれぞれ自作詩の朗読及び話とバイオリン演奏とのコラボレーションを行った。四月の熊本地震という経験から七か月の時間を経て、作者ひとりひとりの眼差しが内と外へ深くひろく向けられたことで、その結晶としての詩情が豊かに感じられるものとなった。小さなもの、大きなものへの視点、さまざまの心象風景が、詩人の視力を経ることによって作品化され、読者及び聴き手の胸に確かに刻まれたのではないか。また、詩と音楽(バイオリン演奏)とのコラボによる朗読では、言葉と音との相乗効果、意識と精神とふたつの耳を研ぎ澄ませて受けとめることによって、そこに言葉だけによらない名状しがたい緊張感と歓びが加わる。芸術の神秘を体感する瞬間であった。
第二部、バイオリンソロ演奏は、県詩人会主催のイベントではすでにおなじみとなった、若きバイオリニストの清水琢己によるテレマンの「無伴奏バイオリンのための12の幻想曲」から「第七番変ホ長調TWV40:20」。聴衆を惹き込む音楽の力、ジャンルを超えた演奏者の表現力を堪能した。
第三部は、新延拳氏(日本現代詩人会理事長)の講演で始まった。堂々とした体躯から発せられるエネルギッシュ"な語りくち、サービス精神あふれるユーモアと優しさ(のち、かなりの酒豪であることも判明)。時はあっという間に過ぎた。「詩は経験を超えられるか」というテーマに沿って、冒頭「詩は感情ではなく経験である」(「マルテの手記」リルケ)の一行の引用。「経験が大きすぎたり、思い出が多いときには、それを忘れることができなければならず、ふたたびそれが蘇ってくるのを待つだけの大きな忍耐が必要なのだ」(同前)という一節は、詩を書く者としての基本的な姿勢であろう。血となり、眼差しとなり、言葉となるまで待たなければならない。
そこで新延氏が提示したのは、聖書の放蕩息子の比喩である。いやでたまらなかった家(父)を、一度は捨てて出ていったものの、様々の苦難の経験を経てのち、帰るべき家を持っているということ、父は何も言わず息子を受け入れ待っていてくれる。ということ。詩人にとってその″戻れるところ〟が詩である、ということ。詩さえあればそこへ戻ってゆける、と思っているのが詩人(傍点筆者)。新延氏の放蕩息子の帰還の解釈はまさに詩人ならでは。本来、宗教的比喩であるところの、通常の聖書解釈をさらに詩に視座を移したという点に、筆者は深く共感した。
プラトンの「国家」から引かれた。“洞窟の囚人"の喩えは、詩の本質を言いあてている。「人間は洞窟の奥に顔を向けて縛り付けられた囚人である」。人間は生まれつき洞窟のなかにいて背後の灯火によって壁に照らし出された影を眺めているに過ぎない。そしてその影が実在であると思い込む」。その背後の光を感じとり、この洞窟から光のなかへの脱出を試みるものが詩人、なのではないか。そこで得たものをいかにして伝えるか(傍点筆者)。「宗左近の詩人としての自覚がそこに見える」(新延氏)。詩人宗左近と晩年近くにあった氏には、宗の青年時代の辛い経験が詩人の心の底深く常にあって、数十年を経たのち、はじめてその経験をのりこえ詩として作品化した「炎える母」を紹介。ゴミとして捨てられた言葉を黄金に変えるのが詩人、というのは確かだろう。しかし、“黄金〟とは詩にとって何だろう。「きらめくような言葉の群れに幻惑され、威嚇され、食傷している」(新延氏) のは、読者だけであろうか。
3・11から生まれた子供の詩を、もし存命の宗左近が読めば必ず共感したにちがいない「ままへ。いきてるといいね。おげんきですか」(昆愛海、当時四歳)というフレーズはマスコミでもひろく紹介された。涙なくしては読めない。「おとうさん、ぼく、泣かなかったよ」(ささきそうたろう七歳)(西嶋好美朗読)の詩も、ひらがなだけの、ほとばしる心の痛みに胸を突かれる。
時間を奪われた現代人。詩を思い、死を思う時間を持つことが希望である。詩は経験を越えられるか。広瀬大志氏(熊本市出身)の朗読とスピーチでは、大きな震災を経験して、「詩に何ができるのか考えつづける」「詩には何もできないが詩を書き読む時間が人間の尊厳であり、詩の力である」(広瀬氏)との言葉に深くうなづかされる。また、生地はかけがえのない場所であるけれど「同時に暖かさと呪縛を孕む」(同氏)存在であるのも事実だろう。
熊本の詩の今後について、経験がいかにして作品化されるのか、一人ひとりが考えつづけなければいけない。
懇親会は遠来の詩人杉本真維子氏の朗読が宴に華を添えた。