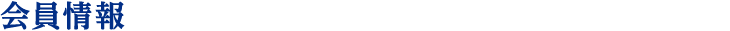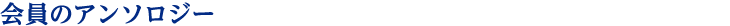会員のアンソロジー6・岡野絵里子氏~
①1958(昭和33)11・15②東京③聖心女子大学文学部卒④「ERA」「白亜紀」⑤『ERIKOのE』紫陽社、『ベーグルランド』花神社、『発語』思潮社。
賑やかな沈黙
皿の上で
一粒のマスカットは明るい
歩き続けて
永遠に近づかない陽の足が見える
食べ残された果実より甘く
真昼は黄金色にとろりと塗りのばされ
すでに食卓を去った人々の重い夢に
汚れたスプーンの頭が傾く
最後の音が止むと
ここには私しかいない
挨拶を終えて
黙っているものたち
その沈黙は歌のように響き
「静物」の内側を熱く満たす
今 私たちは
鏡に映ったように静かだ
(影たちが椅子から立ち上がり)
(もう一度部屋を出て行く)
――後略――
岡本 勝人 オカモト カツヒト
①1954(昭和29)7・20②埼玉③青山学院大学卒⑤『シャーロックホームズという名のお店』『ビーグル犬航海記』『都市の詩学』思潮社、『ミゼレーレ』書肆山田、『ノスタルジックポエジー』小沢書店、『現代詩の星座』審美社。
プロローグ&エピローグ『都市の詩学』
言葉がまだ無明の時代にあったころ
意識は都市という星雲をめぐり
かたい孤独は山の春雪の泥濘となって
バラ色の宵闇のなかで溶けはじめるだけだっ
た
犬と猫が眼鏡をとりだして
雨のなかに映る世界をふたたび学びなおそう
としている
現象をできうる限り言葉で表現する
手帳だけが語る言表
都会に横たわる死者たちの紀行文集
それはどれも日常からこぼれおちた顔のこと
なった
暮れ色に染まる時間の宇宙の全体をしめして
いた
故郷の山のうえ
寺の墓地には祖先たちが眠っている
父も先年墓にはいった
眼下には緑の木々におおわれた実家の屋根が
みえている
小川 アンナ オガワ アンナ
①1919(大正8)10・4②静岡③静岡高女卒⑤『にょしんらいはい』私家版、『富士川右岸河川敷地図』塩の会、『晩夏光幻視』文京書房、『きんかんの花』私家版、『ゆかりの林檎』樹海社、『源流の村』文京書房。
まれ人
はっと目覚める いま 誰かに抱かれていた
身体にまつわる温かみの靄を失せないように
かき寄せる それは父か母か
わたしのひそかな願望が呼びよせてしまった
恋人のようなものなのか
ひとり睡るわたしのそばにそっと寄り添い
睡っているわたしをかき抱き温めてくれてい
たもの
省りみれば一切ならずこういうことはあった
ひとり冷たい寒夜のベッドで
かけ物をひき寄せてくれたけはいにはっと目
覚めたとき
まだ夢見ごこちに
それがひとと呼ぶのがふさわしい抱擁の象(かたち)で
なにものかに包まれているからだと気づいた
とき
夢に来ませと乞いのむ程の激しさでなくても
老いの生にもまれ人の訪れがあって
骨まで温められるようなこともあるのだ
小川 琢士 オガワ タクシ
①1928(昭和3)8・7②福島③早稲田大学政経学部中退④「の」「龍」⑤『夢・現実』黒出版社、『漆色の日没』書肆青樹社。
夕闇
いつも一匹 夕闇にまぎれて
裏道にやってくるオニヤンマに
少年は王者の風格を見た
それは童謡の月の沙漠を越え
天頂に光る星になった
下校の回り道
裏道の竹藪の葉に
二つ繋がって止まっている姿があった
虚をつかれて 少年はうろたえ
上目使いにおどおど確かめた
まぎれもない あわれな姿
熟れた栗の実が落ち
一番星が澄んだ声を上げた
己の感性の弱さをそしり怒り
血相を変えた少年が飛び出した
あれから半世紀が経ち
夕闇に立つと
初老の寡婦が笑った
沖長 ルミ子 オキナガ ルミコ
①1935(昭和10)2・13②岡山④「道標」「飛揚」「どぅるかまら」⑤『亀島山地下工場』『ざら紙の帳面 1946~1949』手帖舍、『午後の街路樹』編集工房ノア。
風の手
渦の形に倒されたコスモスの群れ
意外に太い茎と頼りなさそうな葉
ピンクとあかの花がてんでに顔をもたげて
風にゆれている
昨日
通り過ぎていった大風を追っかけて
確かに何かが逃げていった
どんどん逃げていって
遠くなって
何かとはいったい何だったのか
確かなことはわかるはずもなく
倒れたコスモスのそばで
花をまねてゆれていると
ぴしゃり
風の手が頬を打った
奥 重機 オク シゲキ
①1942(昭和17)12・11②北海道③東京水産大学選科卒④「光芒」「東国」⑤『皇居の馬』葵詩書財団、『こころの季』こころの季編集委員会、『囁く鯨』書肆青樹社。
花火
薄暮の中に身を横たえたまま
河は静かな時間を運んでいく
何千年も積み上げてきた無為と有為を
今夜も止めることはしない
底の泥流は泥流として生き続け
水の流れは水の流れのまま柔軟に生きる
大気も空も今日は花火のために
平静を妨げられて落ち着かない
光と音の交錯する迷路を
一瞬のうちに通り抜けた静寂が
次々と河に身を投げる
二万発の花火が人間の知恵と技を
上空で具象化する
二万の具象は形を捨て
黒い残骸を私の中に落し込んでいく
宴のあとの心の蹉跌は
硝煙に吸い込まれ
空のにごりは風に払われる
すでに宴はあとかたもない
奥村 和子 オクムラ カズコ
①1943(昭和18)1・11②大阪③大阪女子大学国文学科卒⑤『渡来人の里』ポエトリーセンター、『花』編集工房ノア、『めぐりあひてみし――源氏物語の女たち』竹林館。
大阪暮色
阿倍野旭通りの古びてよごれた石標を横に西
に歩く。赤字増幅していく市の都市計画で壊
された空き地にはアキノキリンソウ生え、
真っ赤な夕陽は膨らんでゆっくり難波津に落
ちてゆく。アベノベルタ・ルシアス・マル
シェ・市大付属病院の巨大なビルが台地を埋
め空をふさいでゆく。さらに西に坂道をおち
てゆくと、開発事業区域から落ちこぼれた崖
下に、古びた安普請の家家が並んでいる。戦
火に残った元ユウカク「百番」の二階欄干と
赤提灯。飛田新地。日が暮れて、普賢・海
風・ゆり・さよなどと書かれたネオンが灯さ
れる。どの家も玄関が開けられ、たたきの奥
に座ってる女ひとり。可愛い娘。アイライン
を塗った目が通行人を射すくめる。大きな
おっぱいを強調する流行のチュニック着て肉
付きのいい太ももあらわ。側にはきまってや
り手婆が低い椅子に腰かけ、道行く男たちに
声かける。おジョロウさんの顔見せ。日本国
平成カザリマドノオンナ。ポリスマンはテロ
対策に忙しく疲れた男たちのホウモンは途絶
えない。
刑部 あき子 オサカベ アキコ
①1939(昭和14)9・4②福井③文部省図書館職員養成所⑤『ある墓碑銘』ポエトリーセンター、『空と木と花』あすなろ社、『めぐる』土曜美術社出版販売。
彼の国へ
届いてはいけない手紙を投凾する
ポストはないでしょうか
わたしの内にしまいきれず
今にも溢れ出しそうな、あなたに
と書いて
幾層もの緑が重なりあっている
深い深い谿に落してみたら
それは、はらりと散った
こぶしの花びら
白い翼の鳥
蝶になり
光になって
見えなくなっても
どこまでも落ちていく
はるかに慕情の季節は過ぎた
恋文のカケラが白萩に散らばって
上弦の月を仰いでいる
しずかな秋の庭
探しあぐねている
彼の国へ届くポスト
尾崎 昭代 オザキ アキヨ
①1942(昭17)2・15②栃木③東洋大学文学部中退④「アリゼ」⑤『水無月の水』書肆山田、『ねえ 猫』愛育社。
海の馬
冬の空は
雲一片も 塵あくたも浮かんでいない
その空を 小さな馬が走っていくのが見える
老いが近い一頭の北馬
わたしの脳髄の中の海の馬*
彩とりどりの草原を縫って
異国の風にも吹かれて
不思議の恋をパドドウしたり
傷ついたり 寂しがったりしながら
忘れたいことなど憶えていて
忘れたくないことなど忘れてしまって
それでも わたしの海の馬は
時々 幸福な花野に連れていってくれる
今朝は
枯草の上で日向ぼっこをしている
猫を見ている
*海馬・大脳の古皮質に属する部位
尾崎 幹夫 オザキ ミキオ
①1948(昭和23)10・24②鳥取③大学卒④「暴徒」⑤『しんでが一匹』『くちうつし』暴徒社。
雨
雨がふれば雨にあたるしかないものが好きだ
みちばたの卯の花
電線のハト
やきとりやのけむり
だれにもみせない娘のかなしみ
そのかなしみを思うぼくのかなしみにも
さけられない雨がふる
尾崎 与里子 オザキ ヨリコ
①1946(昭和21)10・12②滋賀③長浜北高校卒④「yu hi」⑤『はなぎつね』双林プリント、『夢虫』編集工房ノア、『風汲』エディションカイエ、『秋遊』砂子屋書房、『城の町』草原詩社。
黒苺
黒苺のお酒をのんで見る濃い夢
私たちは三度出逢い三度結ばれ
マリア マリア マリア
三人のマリアを生んだ
黒苺はどんどん枝を伸ばし
たわわに実をつける
透明なルビーが深紅に熟し
漆黒になって地に落ちる直前を
強い蒸留酒と蜜と一緒に瓶に封じ込める
流れ出すことのできない時間
醸される苦痛
熱の余韻をまとった私たちの
輪郭が少しずつ見えにくくなっていく
一年が経ち
十年が過ぎる
私たちは充分老いた
闇の中でもう一度
私の脚先は溶けながら
微笑という発酵を受け入れ
ゆっくり掻きまわす
長田 典子 オサダ ノリコ
①1955(昭和30)11・15④「ひょうたん」「KO.KO.DAYS」⑤『夜に白鳥が剝がれる』『おりこうさんのキャシィ』書肆山田、『翅音』砂子屋書房。
蛇行
今朝は
慌てて卵を割った
歪む湖面とともに
フラッシュバックする
発破音が鈍く響いていた日々
谷に満ちてくる水から
逃避する蛇の幻影は 遠く
鱗を鋼に置換して
ホームに急行が滑り込む
蛇は身を捩りながら湖面を泳ぎ
つゆくさ つりがねそう つるぎきょう
初夏の眉をなぞりながら
鶏小屋のまだ温かい卵へと向かう
蛇か わたしは 蛇なのだ
花首が揺れて
きつねのよめいり
高速で移動する窓を水が走る
歪んだ湖面から発破音の響く場所へ
瓦礫の隙間へ
乾いた皮膚を脱ぎ捨てに行く
おしだ としこ オシダ トシコ
①1937(昭和12)4・1②鹿児島③慶応義塾大学通信課程④「青い花」個人誌「翔」⑤詩集『組紐』『流れのきりぎしで』書肆青樹社、評論『正宗白鳥』沖積舎、『ことばの森のなかへ』私家版。
山峡のながれ
深山の里の枕辺を あらう
せせらぎの すみわたる音色に
草枕のひと夜をあずけて
耳をかたむける
心と身体にしみついた
ちりやほこりをさらって さらさらと
ながれる 水の行くさきをおもう
いく重にも折れる坂道を
ほふくの歩みでたどりついて
胸襟をひらけば 眼前に
そびえたつ 山顚がある
峠からみはるかす四方の国の
ひとびとの暮らしも とおくかすんで
水はながれをさえぎる岩肌に飛沫をあげて
行き着く場所を知っているように
この身も
調和のなかで生かされていると言いたげに
水はながれのままに ながれていく
尾世川 正明 オセガワ マサアキ
①1950(昭和25)5・17②東京③千葉大学医学部卒④「孔雀船」⑤『花をめぐる神話』『みえないいきものたちの天文学』花神社、『誕生日の贈物』土曜美術社出版販売、『海馬に浮かぶ月』思潮社。
朝霧を歩く青い羊
まだ目覚めてもいない街に霧が流れて
ゆるゆると車を走らせる朝
目の前を青い羊が横切ってゆく
猫よりも小さな羊は全身が青く
柔らかでふさふさとした長い毛があって
目も口も埋もれて見えない
羊は道路を横切ってゆくと
たいていは近くの店の中に消えてしまう
店はまだ入口が閉まっているのに
喫茶店や楽器店や時には鮨屋と
ゆく先はそのたびまちまちだ
現れる場所も日によって違うしそれより
羊が現れることに意味があるとも思えない
青い羊がなぜ車道を渡るのか
それが吉なのか凶なのかもわからない
しかし今朝は青い羊が一匹ではなく
二匹並んだ羊がこそこそ道を渡って
角にあるポルノショップの前に止まり
すこし周囲を見回してからなかに消えた
私はといえば地平線に向かって走りながら
ひとりクスクス笑い続けた
小関 守 オゼキ マモル
①1926(大正15)9・15②千葉③三田尻通信学校卒④「光芒」「地球」⑤『月の光の下で』『遺された鏡』草原舎、『晴嵐賦』。
旅愁の振り子
かってアイヌがシマム
語り部の清流 四万十川
川面に散らした 真砂が
静やかに 流れていく
行き交う遊覧船は 煌くレールを走り
鮎 ゴリは川底の藻に 日記をつづる
西土佐の村里をなぞり 帰る事のない水の旅
抱いてくれる 海原の
守り唄の 囁きを辿っていく
遠い時の流れを攪拌した
船の窓辺に映る 浴岸のかたらい
宙の刻みに旅愁の 振り子を投げて
切った シャッターに
永久の 静寂が
影を落す――。
*シマムト。雄大
小野 静枝 オノ シズエ
①1925(大正14)1・3②山口③下松高女卒⑤「らくだ詩社」⑥『待つとし聞かば』駱駝詩社、『それから・それから』らくだ詩社、『花野』本多企画。
空
鎌を研ぐ
三日月形の刃に左手を添えて
しゅっと研ぐ
空に浮く雲が心なら
澄みわたる空は魂だろう
今日はるばると会いに来たひとは
わたしの前に
その生涯を
激しい川のように流してみせた
世に容れられない女と男の在り方も
それより他には在りようがなかったという
一筋の熱いものを美しいと見
美しいと聞くわたしは
その空に懸かる白い雲だ
研ぎあげた鎌の刃を親指の腹に当てる
一すじにじむ血
刃を空にかざす 寂しい色だ
きらりと光る
姨嶋 とし子 オバシマ トシコ
①1935(昭和10)5・23②大阪③高校卒④「叢生」⑤『遠くをみている』『この手の記憶を』『海をみていた女』編集工房ノア。
喫茶店にて
喫茶店に入ると
「いらっしゃいませ」の声と共に
コップ一杯の澄んだ水が席の前に置かれる
勿論ただで客はそれは当然のことだと思って
いる
透明な水の中に
泥水を汲むアフリカの子供達の顔が浮ぶ
親を選べないように生れる国も選べない
内戦がなくてもテロがなくても
この子らに絶えずつきまとう生命の危険
このひどい不平等
このむごい不公平
誰のセイだ
悲しみが胸をふさいでも
私には何もできない
コーヒーと共に己れの非力を呑み込み店を出
ると
日本人の日常に紛れ込んでゆく
小幡 薫明 オバタ シゲトシ
①1941(昭和16)11・13②東京③明治学院大学経済学科卒⑤『カスタニアみどりとなれば』北冬舎、『Oのヴィヴァルディ』邑書林。
三角畑
いくつもの石が生えだす
木枯らしの梢
精神の内果を散らす
華やかな受苦を響かせ
庇の風鈴がいっせいに鳴る
白いものが落ちてきた
底のない三角畑の絶頂期
青冥な複葉のつがう鳥が
春の胞子を銀の匙にうつし
黄染めの船の屋形を出ては入る
逆髪の千年の末裔が住む
暗い水
皮一枚
追分の古道にそい
川は流れる
生死の境界を見すえ
世界を小さく限る生業の岸
水沫散る初雪を食べに
魚が跳ねて集まる
尾花 仙朔 オバナ センサク
①1927(昭和2)4・9②東京③旧制札幌商業卒⑤『縮図』季節社、『黄泉草子形見祭文』湯川書房、『有明まで』『春靈』思潮社、『尾花仙朔詩集』土曜美術社出版販売。
スピノザの閃光
火の車輪が
秋の奥処へと
駈けぬけて行った
今生のいのちの果てに
氷柱の穂先が
鋭く光っている
――夢を見た
と思う間に
夢の淵から
襷掛け 血刀さげて現れた
詩歌の群れが
私に言問うたのです
詩歌とは
感性を磨く
無償の言霊への
愛であるのか?
それとも 神への
知的愛に
ほかならぬか? と
各務 章 カガミ アキラ
①1925(大正14)6・1③九州大学法文学部法科卒②福岡④「異神」⑤『地上』現代社、『遠い声 近い声』木星社、『愛の地平』思潮社。
道
明るい風景の中で
母の声が聞こえた
いつものしっかりした声である
――そこに腰を下ろして振り返るとよい――
何のためとも言わなかった
ふりかえりたくない風景は
幼い時からどの位あるだろう
それを捨ててここまで来たのだから と
返事をしようと思ったが
近くの小川に 母の声は
流れていってあとかたもない
ひたいに冷たい風を感じる
初夏の早朝
古里の山脈に
みどりが燃える一日である
加賀谷 春雄 カガヤ ハルオ
①1934(昭和9)1・13②東京③国学院大学国文科中退④「潮流詩派」⑤『象のインディラ』『二つの行方』潮流出版社。
回す
大阪の某料亭で
客の食べ残しをほかの客に
使い回していた
その上
代金はそれぞれからとった
そのことが露見すると料亭のおかみは
〈食べ残しだなんて……
お出しして残されたお料理と言ってほしい〉
と見当違いな言いわけをした
同じころ永田町某所では
お出ししたお料理が
箸もつけられずに残されたから
それならと
お出ししたところへ差し戻すと
待ってましたとばかり
寄ってたかって食っちゃった
代金はツケ
*道路財源特例法案で福田内閣は三度目の衆議院再可決
成立をはかった。
香川 紘子 カガワ ヒロコ
①1935(昭和10)1・3②兵庫④「g ui」「嶺」⑤『魂の手まり唄』思潮社、『DNAのパスポート』あざみ書房、自伝『足のない旅』日本図書センター。
フォンタナの「空間概念 期待」
――大原美術館にて
二〇〇四年晩秋
朱色のキャンパスを縦に引き裂いた
川の字の黒い三本の斜線
その脇腹の傷口に
この指を差し入れてみなければ
主がよみがえられたことを決して信じない
と
疑い深いトマスが口走ってから
二〇〇〇年が過ぎたが
主は 今も釘あとのある手を
地球の裂目に差し入れて
イラクやパレスチナの子供たちの魂を
上着の内ポケットの血染めの裏地で
包み込んでくださるのだ
柿添 元 カキゾエ ハジメ
①1918(大正7)1・18②福岡③早稲田大学文学部仏文学科卒⑤『九重』。
反対語
内の反対は外で
内側の反対は外側だが
内心の反対を外心とは言わないし
外見と言う言葉はあっても
内見という言葉はない
自の反対は他で
自国と他国
自分と他人
自殺と他殺
と言う具合に使われるが
自由の反対を他由とは言わない
仕方なく不自由などといっている
不と言う字はまことに便利で
不便 不可能 不是 不勉強
不思議 不幸 不意 不案内
不運 不快 不覚 などと
取り上げたらきりがないほどだが
ろくな言葉は出てこないので
僕自身が次第に不愉快になり
おのれの不見識を思い知らされたようで
もう やーめた
筧 槇二 カケイ シンジ
①1930(昭和5)7・28②神奈川③横浜国立大学学芸学部卒④「山脈」⑤『逃亡の研究』文童社、『怖い瞳』石文館、『ビルマ戦記』VAN書房。
蛇
永昌寺の下の道を 右へ行けば四方木屋だが
左を登ると島崎一族の墓がある 藤村も
その父も 妻も子も みんな薮かげの細長い
四角柱の下である
びうつと目の前を飛んだ一条の黒いもの 蛇
だ
「気いつけなせえ」
鎌を片手の農女がいふ
「蝮がそろそろ子を持つで へえ」
ふところの深い つやのいい顔がにつと笑ふ
見送るかたちになつた坂道の夕映え 乳房と
子宮で生きるうしろ姿の幽艶さよ
色を濃くした空が唐破風を包む
笠井 忠文 カサイ タダフミ
①1928(昭和3)3・4②山梨③東京大学附属医専卒④「乾季」「人間」⑤『不惑』私家版『銀色の蝶』宇宙社、『観覧車』『寒い春』乾季詩社。
暑熱
なんであれ文字を連ねれば
遺書を書く思いに移る八十歳
であってみれば
今年のペン先が暑熱に溶けて
文字の輪郭曖昧に目の中で意味不明
と、変わる理由が知れる
友よ 病床の君を見舞って言った
「明日また会うことにしよう」
若い日におなじ言葉を言い合った
その頃 ぼくらは炯る目をして
「もしも明日があるのなら」と
必ず付け加えたけれど
今はできない
間もなく死ぬはずの君に向かって
「悉皆是空」を説くこともなく
暑熱に滲んだ並木道を背を丸めて
むなしくぼくは帰ったのだ
笠井 剛 カサイ ツヨシ
①1931(昭和6)7・17②山梨③立教大学文学部英米文学科卒④「嶺」⑤『森の奥で』思潮社、『同じ場所から』『庭の情景』国文社。
添い寝する山
胴体をギブスに巻かれて
ベットにころがされていると
巨きなピンで突き刺された
仰向けの生体標本のようだ
時どき覗きに来る人に
頭と手と足を動かしてみせる
微笑んで見下ろす顔はどれも
踏みつけられた窪地のよう
枕辺に山岳が迫る病室にいて
十三夜の月を山頂に眺め
更に次の満月を山の端に見詰めた
山は木霊を人と交わし
人は思いを山に届ける
救済を願うのは人ばかりではない
山もまた毀たれた顔を天に向けて
寄り添って人と眠る
葛西 洌 カサイ レツ
①1937(昭和12)6・29②青森④「長帽子」⑤『北の光』『6月29日の谷間』『記憶する鳥』『風祭り』『葛西洌詩集』芸風書院、『橋の上で拾った十円玉』『野の意味』。
もっと遠い所
ひらがなでもの想う日は
もっと遠くを見ていたい
遠くを見るということは
さらにその先に続く道があり
道の先は
ひらがなの筆跡のように途切れることがない
筆跡の先は細くなり
その先には白い花が咲いている
白い花は蕾を増やしているのだが
なぜか誰にも見えない
笠原 三津子 カサハラ ミツコ
①1926(大正15)4・1②東京③常磐松高女卒④「風」「こすもす」⑤『雲のポケット』ユリイカ、『遠い遥かな石の道』砂子屋書房。
光
おやすみなさい 安心して
明日の朝まで
きっと守ってあげます
まばたきもしないで
闇と戦う 光
悪い奴らが うようよいる
家のかげ 樹木のかげ
お前たちの思い通りにはさせない
清らかな瞳を見ひらくと 光は
七色の光線の矢を放つ
晴やかに輝きわたる
どこまでも 光りかがやく
おごそかな 調べ奏で
地上を照らす
光 おお
慈愛を あまねく
ふりそそぐ
梶谷 忠大 カジタニ タダヒロ
①1940(昭和15)11・12②愛媛③京都大学工学部建築科中退④「PO」⑤『存在とフォネー』『夏のカルテ』『わがたらちね抄』編集工房ノア。
川そして異相
流れる水は 常に「いま」である
流れる時は 水の比喩にすぎない
何という川の時空の豊かさであろう!
川の辺は 営みであり人為である
川の辺は 京があり食があり恋路がある
川は 空を映し 瓦を映し
川は 恋を渡し 恋を遮る
虫の音が止むと 夜の音がはじまる
耳を澄ますという待機の姿
逢瀬は 何という現の量感であることか!
愛欲という暴力の雪崩
胸塞ぐ哀しみは 死へのではない
死に臨んでいる生の姿への哀しみである
胸ふたぐかなしみは
かなしと思う妹背への
隔たりを越えんとする慕情である
柏木 恵美子 カシワギ エミコ
①1931(昭和6)8・29②福岡④「たむたむ」「青い花」⑤『炭街』詩学社、『花のなかの先生』敎育出版センター、『幻魚記』書肆青樹社、『雨のシロホン』銀の鈴社、エッセイ集『詩魂に寄せる』書肆青樹社。
空の円卓
魚の背の鮮やかな斑紋のような
白い雲が
空いっぱいに広がっていた
さざ波が
その縁を 洗っていた
雲の指は
思い出のように
どこまでも中天に
延びていた
と
ぽっかり 穴があいて
真っ青な空のテーブルが広がり
詩人たちがいそぎ集まるのがみえる
着席した円卓のなかに
大切なひとりが
欠けているのだが
さて それが誰なのか
詩人たちはだれも 思い出せないでいる
柏木 勇一 カシワギ ユウイチ
①1941(昭和16)10・22②岩手③東北大学卒④「方」「青い花」⑤『嘔吐』思潮社、『虫の栖』沖積舎、『擬態』思潮社。
門
たった一度
再び閉めることのない
門をあける時がある
無音の闇に招かれて 一度だけ
その門をくぐる時がいつか必ずやってくる
男は 暴戻の地で
その門に吸いこまれた
絶望の果ての選択だったのか 夢の誤作動か
確かなことは
男は戻らなかった
かすかに羽音が聞こえる
この静けさの中から生まれるのか 鳥よ
やがてお前は
かなたに飛び立つ
この球体にも闇につながる門がある
柏木 義雄 カシワギ ヨシオ
①1928(昭和3)8・10②兵庫③名古屋大学文学部英文学科卒④「花」⑤『パスカルの椅子』『客地黄落』思潮社、『来ること花のごとく』『塵の顔』国文社、エッセイ集『クロノスの日曜日』国文社。
ある朝明けに
生まれるのは 身を裂く母の痛みから
孤独な星を荷なう痛みを
引きうけることだった
握りこぶしに血を滲ませて
やがて 乳の雨 土の蜜を失うと
私は露をふくみ 木蔭に蹲り
目覚めては舞い立つ風に誘われて戸惑った
よそよそしい仕種で
偸安の日月をすりぬけ
流れる光に躓いて歩いた
太陽のひび割れで鳴く虫の声も絶えると
時の荒れる野の川で舟べりをたたきながら
草の穗に 遙かな苦みを噛んでいた
馴染みの風景の搖り椅子を棄て
どこかへ置き忘れてきた初めての花との
出会いの神秘をとりもどしたい
どんな言葉よりも遠い木々や石たちの黙示に
貧しい魂が蘇生する土地へ旅立とう
生まれた日の悲しみを抱きしめて
虚実の境に架かる橋に佇み
天地を包む太初の朝明けに見入っている
加瀬 昭 カセ アキラ
①1931(昭和6)11・26②群馬③明治学院大学文学部卒④「龍」⑤『蟬時雨』書肆青樹社、『霊異』横浜詩人会。
泳ぐ
音に向って進む 流れのなかで水泡が足に絡
む 藻がゆれている からだの動きが流れと
の一体感でここちよい 誰かの声がする と
きおりひとの名らしき単語がまじる しぶき
があがる 横を魚が泳いでいる
遠くで声がする 演説のようだ マイクで叫
んでいる 議員選挙だろうか この国には国
是がない この国の憲法は蔑ろにされている
甲高い声が叫んでいる この国のひとは泳
ぎがうまい 泳ぎの得意なものが古からこの
国を支配している ひとはひとの傷みをがま
んできる ことばは器用に浮遊している
この国は半世紀ほど前に戦に敗けて 国と国
との諍いの虚しさは骨身にしみている あや
まちは繰り返しません 克明に碑を刻んだ
傷は癒えていない 内なる傷は深く内向して
外からは見えない 見ないようにしている
だから傷は癒えていると思いがちである ひ
とは泳ぐのが巧みになってきている