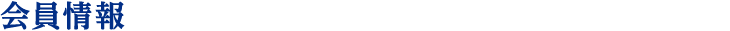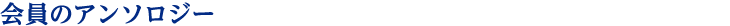会員のアンソロジー7・片岡伸氏~
片岡 伸 カタオカ シン
①1953(昭和28)11・20②千葉③日本工業大学工学部電気工学科卒④「覇気」⑤『陽炎』『夷隅川』草原舎。
鍵
小指ほどの細長く薄い一枚の金属板
その長辺の片側或いは両側に刻まれている
暗号の凹凸
「錠の穴に挿し込み開閉するための道具、物
事を理解するための最も大切な事柄」と
広辞苑には――
ささやかな家を建てて十年 帰宅しその前に
立つ
ドアの取っ手の脇にある小さな穴に一日を入
れて
回し 手錠を解く
娑婆に戻る毎晩の儀式だ
余白を埋めるみたいに女がやってきて
ふたり抱きあい夜が始まる
深い穴の底から
「カチリ」と吐息が聞こえるだろう
――鍵
それだけでは用をなさないが
娑婆に戻る儀式のように
男と女の出会いのように
合わせて初めて闇がひらき 夜が灯る
片岡 直子 カタオカ ナオコ
①1961(昭和36)11・25②埼玉③東京都立大学人文学部卒⑤『産後思春期症候群』『おひさまのかぞえかた』書肆山田、『曖昧母音』思潮社。
かわしも(短縮形)
向かい合った喫茶店の席で
「聞き上手だね」って言わないで
話したいことが沢山あるみたいだったから
黙っていた
(きくひとのこえ)
その単語に「ボランティア」が付いて
胸が 痛かったよ
聴くように話すひと 私の憧れの
牧子さん が 最近 始めた
お年寄りのための 日課
(きくひとのこえをきく)
話す人の声に耳を傾ける 牧子さんの
心がプールに なってしまう 私は
あなたの 川下に いる
(きくひとのこえをきくこえ)
消え入りそうな心も オトになる
引き潮の 耳 で
片岡 文雄 カタオカ フミオ
①1933(昭和8)9・12②高知③明治大学文学部文学科卒④旧「貘」「カシオペア」⑤『地の表情』『帰郷手帖』。
蛇をめぐるノート
蛇は嫌だ
生理的に
手足も無しに
平然と川を渡っていくのだもの
枯葉の上を
音を引き摺りながら歩んでいくのだもの
あの無音の体内に卵を抱いて
きっと子を産む崖の
そのひっそりとした穴を探して
いや 蛇が
世界から消えてしまったのでもない
渡るべき川が
とっくに涸れてしまったわけではない
流れと蛇とは
もともと一体のものだったのだ。
片羽 登呂平 カタハ トロヘイ
①1923(大正12)②岩手④「新日本詩人」⑤『片羽登呂平詩集』。
空から降ってくる
昨日九つの花だった辛夷は十一を数え。
梅は疾うに遠ざかり。
椿がいさぎよく花を落としはじめ。
菜の花も咲き。
桜が五分、七分と。
少し寒さのある風が。
四階の窓のおれと猫のアパッチを吹いている。
猫と老人の。
窓から見おろす風景を縫って。
人影がちらほら見えるが。
入院した女房のいない時間の帯に。
からだをぐるぐる巻きにされ。
お花見の肴を探すばかりの。
おれとアパッチは見飽きた顔を見合わせて。
東京でいちばん孤独な場所に居座っている感
じが。
花びらのように空から降ってくる。
①1933(昭和8)4・20②東京③岡山大学法文学部国文学科卒④「Para bo le 」⑤『堂宇』『どこ』花神社、『日仏対訳・そこ(Là)』ふらんす堂。
擦過
擦過
は 由来を曳かない
ひと刷毛の雪
凍える路面
高層の窓窓の灯り
一夕の夕餉
一閃のまばたき
はばたいて
称号 なく
なすこと もたず
ショッピングモールに
獣躯 掠めて
闇から 同色
カートが
跳ねる。
①1929(昭和4)1・3②東京③早稲田大学文学部卒⑤『加藤郁乎詩集成』『坐職の読むや』みすず書房。
とよみづほひだのやますそ
飛騨の山裾には大小七十からの城趾が残る
その大方は古代祭祀の磐座に発し
位山の北方松倉城趾へは奥七曲り道がある
松倉は祭座の約言だとは村童でもわかる
乗鞍岳すなはち祈座の峰々を正東に眺めて
岩屏風があり神を祀る御座所があった
このあたり昭和まで巨石群で知られたが
廻り洞の立石群をすでに採り上げた御仁に
ひだ生まれの詩人歌人福田夕咲があった
霊能たぐひまれの詩人の行実を探るべく
飛騨日報またツチグモ誌を掘り出し繰った
古神道は念力考証にとどまらず脚力が要る
宣長翁の正しき継承者であった田中大秀
この売名を嫌ふ国学者は松室岡に眠る
ひそかに諡して豊美豆穂八束足穂大人と曰ふ
加藤 栄子 カトウ エイコ
①1948(昭和23)10・28②愛知③愛知大学現代中国学部卒④「環」「孑孑」⑤『笑う椅子』書肆青樹社、『林檎の期限』詩学社。
ペンギンがお風呂に
いるのだ あいつが
分厚い脂肪にお風呂はまずいんじゃないか
と言っても 丸い目をして
ペタペタ足音させて洗い場を歩いている
なぜ どこから来た
飛べないはずなのにどうやって
しかし いるのだ
それだけのことだ
いては困る………ことはないのだ むしろ
いてほしい ここに
いなくてもいいはずなのに
いなくてはならないのだ もう
一緒にお風呂に浸かろうよ
ほう と
一日のおわりに吐く息を
ほぉーう と一緒に
それだけのことなんだ ペンギン
加藤 幹二朗 カトウ カンジロウ
①1934(昭9)7・4②新潟③東京神学大学修士課程卒④「詩人会議」⑤『牢をえらぶ自由』(自費)『リパブリック讃歌』詩人会議、『彫られた名』青磁社、『焦げた玉葱』『追って来た人』視点社、『塔の鐘』詩人会議。
青いバッジ
私の教え子大沢孝司を ずっと覚えている
新聞部の写真班、一枚の優れた写真の為には
校則なんか屁のように無視し、身の安全に
病的に臆病な校長に 私は何度盾突いた事か
曾我さん親子の拉致とほぼ時を同じくして
佐渡の職場の寮から消えた君が
北鮮の工作員に誘拐されただろうことは
正式に拉致被害者の認定を受けられなくとも
間違いないと私は確信してきた
君の生存に 私は半分しか自信がない
自由がシャツ着て歩いてるような君は
多分 下手な抵抗をして簡単に殺されたろう
しかし一週間、膝を屈して生き抜けたら
あとはお前の才覚で今も生き抜いている筈だ
君の為に青リボンを付け 今はそれに替え
同色のリボン型をしたバッジを付けている
講壇で説教をする時もこれを外さない
生き抜いていろ 私たちの声が届くまで
加藤 千香子 カトウ チカコ
①1932(昭和7)10・1②三重③早稲田大学文学研究科仏文科博士課程前期修了④「三重詩人」「火牛」「ブラックパン」⑤『ギプスの気象』三重詩話会、『塩こおろころ』思潮社。
人間のもとの形
規制されるのに慣れてきたから みないふり
しているうちに みないことに網膜は
慣れてくると気がついた時には眼は退化して
あらぬところについている
噛まなくてよい食品ばかり食べているので
もう何十年か先には顎の骨が細くなり蛇の顔
立ちになる人間なぞ想像したくもない
それでも情報の嵐は聞かねばならないから
ラッパ耳 そう 象の耳のようにそういう顔
を子供が画いた 子供のその先の子供の子
供の顔を画いた子供が泣きじゃくる
ツバルの子供たちは泣いてはいられない
マナティのような人魚ひれをつけてもらえる
だろうか
透けるわかめやもずく 藻の迷宮にかくれ
いつか陰湿な恋は巡ってきて もとからそん
なものだったと
生命は何がどうであれ万能細胞のいとなみで
したたかに突起を繋げていく
人間のもとの形はどんなのだったって
門田 照子 カドタ テルコ
①1935(昭和10)4・9②福岡③修猷館高校卒④「東京四季」「花筏」⑤『抱擁』『桜桃と夕日』書肆青樹社、『終わりのない夏』土曜美術社出版販売。
戻る
おとこは老人になった自覚がない
おんなも老女になった自覚はない
けれど 砂時計からこぼれ落ちた時間は
過去を降り積もらせ陋屋は傾いている
再び地が揺れると潰れるのではないか
寝はぐれた活字たちの不安な囁き
おとこは六十年前にいつでも戻る
おんなも戦中戦後にたちまち戻る
兄を二人も殺した太平洋戦争への憎悪
焼夷弾を浴びて逃げた空襲の夜の恐怖
生かされてきた危うい不可思議に
飢えていた子供の頃の記憶はめぐる
病む肩に置かれている温かい掌があり
大いなる手の中にある明日のいのち
自覚がなくても戻れはしない
Uターンのない一本道は細く険しく
独り歩いて行くしかないのだ そして
突然か徐々にか 道は消え失せる
金井 雄二 カナイ ユウジ
①1959(昭和34年)2・8②神奈川③帝京大学文学部国文学科卒④「独合点」⑤『動きはじめた小さな窓から』『外野席』ふらんす堂、『今、ぼくが死んだら』『にぎる。』思潮社。
止まっている深夜
ここにこうして
自分が
在る
微少な睡魔とまぶたの疲労
明日に移行する前の
たくわえの時間を
大切にしたい
鉛筆一本
床に落ち
耳の中に響いてくる
そんな静けささえも磨いていたい
めくるめく陽のまぶしさに耐えかねた
早すぎる時間の中で
止まっている深夜が
あってもいい
塗り固められた秒針の中で
ぼくという鏡を
のぞきこむ
もうひとりの
ぼく
金沢 星子 カナザワ ホシコ
①1917(大正6)2・10②兵庫③頌栄保育専攻学校卒⑤『ありか』宇宙時代社、『夜の国』現代詩工房、『花を踏む死者』地球社、『五月の動物園』。
コロ
夫が逝って幾月かがたった
さびれた盆栽のかげに
子猫が一匹 うずくまっていた
小さな魂のように
たどたどしい歩みで
いつも 私の後について来る
眠っていると
耳たぶを吸いにくる
意外に強い生きる力だ
私の心の隙間に
すんなりと入り
私の言葉に
甘えでこたえてくれる
時には
一人と一匹の鼓動と息が
静かな夜の深みで重なり合い
生きて行く道の彼方に
ほのかな 明りがともるのだ
金堀 則夫 カナホリ ノリオ
①1944(昭和19)②大阪③立命館大学文学部卒④「交野が原」「石の森」⑤『かななのほいさ』土曜美術社出版販売、『ひ・ひの鉢かづき姫』彼方社、『想空』白地社。
龍木
森に杜がある
木木が水脈から虚空に噴き出している
幹は枯れているのではなく
龍になって 蛇になって
無数の吐き出し口を持っている
この手に握る一本の木には
蛇口から覇を競うように木から落ちていく
葉は水滴の跡となって
なぞの鉱山を包み込んでいる
人として守らねばならない霊気の森は
一本の木にも 二本の木にも昇っている
この木を切り倒すな 切ってはならない
噴き出る水は 木木に流れている
耳を澄ませて聴いてみろ
お前の立っている位置から
水が虚空に噴出している
切り倒すな 切って火を放すな
燃える炎に水は燃え滾る
水の木が昇っていく
焼き果てた 涸れた この杜に
まだ水の木が生えている
金子 秀夫 カネコ ヒデオ
①1933(昭和8)6・25②神奈川③法政大学日本文学科卒⑤「原形」「あいなめ」等を経て「焰」⑥『内臓空間』青土社、『人間の塔』福田正夫詩の会、『生命凝視の詩人たち』書肆青樹社、『福田正夫・ペンの農夫』夢工房。
ザォ・ウーキー印象
写実から抽象へと変化していく形が見える
激流でもがく画家の
対象を正確に写すことに満足できなくなった
眼だ
ザォ・ウーキーは だから水墨画の手法をと
りいれ
吸った気を刺す筆致で だぐだぐと
たくみに街を描き 山野を描いた
スカイブルーと白の点在
水没した村の悲劇
死者たちの悲鳴を記憶図に再現した
水を制する権力者ども 権力は悪だ
中国五千年の網目にかぶさってくる
とにかく光を墨のなかにさぐるのだ
青光りの水音
ひっくりかえる蟇の腹
印象の境目に水溶液の点点
金子 秀俊 カネコ ヒデトシ
①1934(昭和9)11・4②台北③福岡学芸大学卒④「異神」⑤『讃え歌』『大宰府』パルナシウスの会。
落日の賦
あかあかと日はつれなくも秋の風 芭蕉
松尾芭蕉が北陸を旅したおりの
故人追善の句である
わたしたちは 仲間で佐渡を旅した
仲間の中に この旅を楽しみにしていて
それを果たせなかった一人がいた
はからずも 追善の旅となった
わたしにとっては 母の追善の意味もあった
十四年前 妻と母と三人で佐渡を旅したが
それが母との旅の最後となったからである
相川というところで落日の時を迎えた
日は海面に光を反射させながら
ほとんど瞬時に沈んでいった
その夜 佐渡おけさを見た
あれは亡き人 追善の舞である
狩野 敏也 カノウ ビンヤ
①1929(昭和4)9・17②北海道③北海道大学法学部政治学科卒④「火牛」「花」⑤『おほうつく』風社、『二千二百年の微笑』土曜美術社出版販売。
曼珠沙華のアリア
ああ、なんというひどい名で、わたしは
呼ばれ続けてきたことだろうか
来る秋も来る秋もお彼岸の野を
美しく染めてみなの後生を祈る私なのに
幽霊花に死人花、捨子花だなんて
私は、しっかり足で立っている
そしてしっかり生きている
それなのに幽霊花に死人花、捨子花だなんて
いち度も人をだましたことがないのに
狐花と呼ばれたり
毒のある私の根を勝手に食べて
舌しびれと名付けたりして…
たくさんの忌まわしい名前をみんな忘れて
私の名は曼珠沙華、ただ曼珠沙華だけでいい
摩訶曼陀羅華、曼珠沙華
それぞれにちいさな空を掴みながら
草叢を燃やし、田の畦を燃やし
竹林に燃え移り、私の想いが
いまお彼岸の野を朱く染める
まか まんだらげ まんじゅしゃげ
壁 淑子 カベ ヨシコ
①1935(昭和10)2・13②東京③日本社会事業大学中退④「日本未来派」⑤『ふりるのどれすでこんにちは』モリイチ、『黒い太陽』横浜詩人会、『砂の降る町で』詩学社。
海へ 鳥のように
脳こうそくの後遺症で
左の足が
地面にぴたりと着地できない
歩行するとき
からだの重心が揺らいで
視線が宙空を遊泳する
わたしは錘を引き摺る鳥だ
正面に海浜公園の門
園内には
幾歳月を逍遥した
足跡が刻まれている
記憶の道を辿る目前に
〈海岸へ〉の道標が立ち
見知らぬ築山の上に
砂の階梯が伸びている
防砂林を削って車道を造ったのだ
午後五時を告げる鐘が鳴っている
変貌したわが風土を背後に
家路に着くとしよう
かべ るみ カベ ルミ
①1940(昭和15)1・5②神奈川③駒沢大学文学部国文学科卒④「ティルス」「はそう」⑤『時のてのひら』『梂』詩学社、『十姉妹』『羽』ふらんす堂。
花束
宅急便がとどいて
野原色の箱から
深紅のバラの花束がこぼれでた
ふつうの いちにちが
にわかに
灯をともしたよう
海のみえる町にすんでいる人の声が
電話の向こうから聞こえてくる
「隣が バラ園なの……」
花瓶にさして テーブルに置くと
わたしのなかから 蝶が
とびたった
かなしいことなど あったろうか
やさしさに
つつまれている
神尾 和寿 カミオ カズトシ
①1958(昭和33)4・17②埼玉③京都大学大学院文学研究科後期博士課程④「ガーネット」⑤『神聖である』文童社、『水銀109』白地社、『モンローな夜』『七福神通り』思潮社。
とかい郵便局
くらやみの
なかの ぼくの郵便局では
せっせと小包を運んでいる
爆弾魔なんか恐くない
リストラだってへいちゃらさ
平等は望まないし 家庭の団欒も顧みずに
緑色のワッペンを胸元に光らせながら
目の前にある物体を
遠くへ移動させる
遠く
といえば
たとえばあの山や川の向こう側
道徳が生まれることのなかった ところ
上手 宰 カミテ オサム
①1948(昭和23)6・12②東京③千葉大学文理学部哲学科卒④「冊」⑤『星の火事』版木舎、『追伸』青磁社、『夢の続き』ジャンクション・ハーベスト、『上手宰詩集』土曜美術社出版販売。
裏地
何かをふかく諦めた
そんな夢から目覚める朝がある
思い出せない気配のようなものが
おぼろげに香って私の心をよぎっていく
眠りの部屋を出る瞬間
夢の衣装は朝の光に溶けて消えるのに
思い出のような影が去りぎわ
ふと立ち止まってこっちを見ていた
手が届きそうで触れられない何か
もっとも近くまで行きながら失ったものは
人の深い眠りの中にいくども訪れるのだろう
失ったものの堆積が、この世の幸せという裏
地をつくる
誰に見せることもなく 華やかさもないが
生きることの温かさがわたしを包み込む朝だ
禿 慶子 カムロ ケイコ
①1932(昭和7)10・1②神奈川③実践女子大学国文科卒⑤『彼岸人』『ジオラマ』勁草出版サービスセンター、『我が王国から』砂子屋書房。
川岸の家
開け放された窓から
静かに川が流れ込んでくる
水がときをかけ岸を削るように
ときが持ち去った傷跡を見ていた
近くの広告塔が点滅すると鎧戸が血を流す
残光が二人を青年と少女にする
不意に水嵩が増し橋脚が流れた日のような
ゆるゆると水は巡り
少し泥臭い魚などをつかまえていた
窓を開け放ってみたが
川は流れ込んでこなかった
水は青くよどみ魚の影も見えない
それでも広告塔に火がはいると
黒服がしばし赤いドレスになる
遡れない川は暗く
見えない対岸のあかりを
ひっそりと水の面に
散らしているようでもあった
亀川 省吾 カメカワ ショウゴ
①1947(昭和22)3・29②宮崎④「焔」「川崎詩人会」「新しい風」⑤『穀物階段』『鳥の噂』『木製少年』福田正夫詩の会、『逆町水牢鳥女』『鮫月』詩学社。
活字の海への身投げ論
詩とは 神の急所の 袋掛け
詩人は妊婦である 逆子しかできぬ
長すぎる臨月
それにしても 詩とは何か
もっとも みだらな蝶(開閉)を
捕獲するための夏帽子
失敗すると 蛇がでる
タイトル・マッチの誤解であろう
試合前にへたりこむ
耳にしただけでKOされてしまう
出版とは小さな身投げ である
とめなくて どうする
神の急所へ
射精しなくて どうする
スタミナ不足か
バケツの中の雪ダルマ
みまかりしとき 死者を犯す花よ
(* 高村光太郎)
亀谷 健樹 カメヤ ケンジュ
①1929(昭和4)9・28②秋田③駒沢大学文学部社会学科中退④「密造者」⑤『柩』秋田文化出版社、『しべぶとん』私家版、『白雲木』書肆青樹社。
うらぼんえ
ひょうたん 天にぶらり
ひょうたん 水にゆらり
ひょうたん 地にごろり
ひょうたんの般若湯をそそぐ
これを呑むと
かならず生きて帰ってくるぞ
いうた老僧
信じた応召兵
ともにあの世へいったきり
洒々落々も 六十年すぎた
うらぼんえ
むかえ火たくと
きなくさい風に ぶらり
なおやまぬ せかいの火種
施餓鬼壇に ごろり
おくり火たくと
とおい銃声に また ゆらり
香山 雅代 カヤマ マサヨ
①1933(昭和8)3・1②兵庫④「地球」「Messier 」⑤『楕の埋葬』ブラックパン社、『空薫』『慈童』季節社、『雪の天庭』銅林社、『露の拍子』書肆青樹社、『虚の橋』『粒子空間』編集工房ノア、『風韻』湯川書房。
無言頌
く くるぅ くるぅ鳩が 地に 星じるしを刻んで 歩いている
星じるしの相似形が いくえにも ひろがり
をみせるだろう
時の漣に 揺蕩う 風紋となって
音叉のひろがりの果て
枕辺に 一枚の少年の写真
凝視めていると どこからみても まるい水
の惑星の鎮もり 煌めく 波の面に
自分を突き抜けてゆく自分といったひとが
あらわれ
わたしは 此處と
月代とともに 揺れ動く 罔象女の芯となる
神の不在を 確かめる場所にいるかも知れな
い いま際
覚醒した抒情が
ちかづいてくる気配のまま
いまを 耀いている
水の器に 星屑ひとつ
時の沈黙の 蒼い記憶の影を 満たして
河合 すみ子 カワイ スミコ
①1930(昭和5)12・4②愛知③旭丘高校卒④「山繭」「風紋」⑤『空の川』原像の会、『夜の鶴とぶ』花神社。
秘境
騒音も遠く 目の前に盛り上がる山々は
その呼吸さえ聞こえそうに身近だった
山は静かに紅や黄に粧を変えようとしている
自然に恵まれた村での暮らしを
――いいわね
売店のお姉さんに話しかけると
――でもね 見て この空の狭さ
笑顔での応えだったが
軽はずみな言葉を恥じた
湯殿の世話をしていたおじいさんが
――山の上で塩がとれる 七不思議の一つだ
で
この村には七つの不思議があるという
――星はきれいか と訊ねると
――星もいいが月もいい ゆっくりと舟みた
いに空を渡っていく
その夜 月の舟に酔って寝つけなかった
ひょっとしたらあの古老 深夜エイッと山を
突き抜けて どこかへ遊びにいっているかも
知れぬ あくる朝そしらぬ顔で
――おはよう
ふうわりとした声をかけてくるだろう
川井 豊子 カワイ トヨコ
①1958(昭和33)8・7②鹿児島③ノートルダム清心女子大学文学部国文科卒④「どぅるかまら」⑤『水車のめぐる家で』手帖舎、『朔太郎の耳』思潮社、『眠る理由』新風舎、『スーパーポエム21』銅林社。
連詩眠る女より〈扉〉
眠る女の目の前に、いくつもの扉がある。
いつも同じ扉、無機質の冷やかな手触り。そ
の向こうには、いつも同じ一つの部屋。決し
て眠らない、天井の高いだだっ広い部屋と、
その中で白い影のようにうごめく人たち。
何台もの機器と画面。絡み合いそうなほどの
何本ものチューブ。足音、息、匂い、あるい
は声、のようなもの。
それはたぶん、境目である。
生と死の。人と物との。わかり合えることと、
わかり合えないことの。ゆるし合うことと、
ゆるし合えないことの。
何枚もの扉が、女の目の前で開かれては、閉
じる。
(おとうさん)と女は呼ぶ。あるいは(おか
あさん)と。
そしてこれが肝心なことなのだが、眠る女は
〈それら〉には決して触れえないのである。
川内 久栄 カワウチ ヒサエ
①1931(昭和6)②大阪③大阪女子商業学校中退④「ネビューラ」⑤『石粉干し』大阪ポエトリーセンター、『はながやいち』岡山手帖舍、アンソロジー『四土詩集』『木箱の底から ふ号風船爆弾』。
最期の一球
一九四五年
一九四三年十一月から始まった太平洋戦ふ号
風船爆弾攻撃は約五ヶ月で終了 うさぎ飛び
しながら勇姿を鼓舞した最期の一球は 少女
だった私が貼り合わせ作業に専念した和紙
一九九一年
ある人の詩集「ばら窓に光を」の一行に〝よ
ろこびの風船にぶらさがり雲の上を歩く〞と
書かれていた
一九九二年十一月二十三日
太平洋を渡りたいと飛び立った通称風船おじ
さん 宮城県沖で消息を絶つ はげしく変動
する気圧は計り知れず
二〇〇〇年
バルーンアートショウの花盛り
蝶やトンボの風船アートをつめこむ花畠の
チュウリップも風船だ
二〇〇三年八月一五日
終戦以来ひっそりとアメリカのスミソニアン
博物館に保管されている
おまえよ
川上 明日夫 カワカミ アスオ
①1940(昭和15)9・8②旧満州③東京測量専門学校卒④「木立ち」「歴程」⑤『哀が鮫のように』北荘文庫、『彼我考』『白くさみしい一編のホテル』紫陽社、『蜻蛉座』土曜美術社出版販売、『夕陽魂』『雨師』思潮社。
雨法師の花
涙はいつか じぶんの空の真ん中で そっと
雲を 浮かべてはひとり 泣いていたかった
よろこびやかなしみも 行く雲だから あま
りに あふれては さざ波のよう 泣きすぎ
たから
眼に見えるもの 眼に見えないものの 辺で
は すこし隣りを 遠慮しながら ひっそり
翔んでいた わたしは魂 いつかとおく空の
ようにと 風の願いをひろげては泣きたかっ
た
人生の野原では もう秋 おおぜいの 魂の
中から たった一人の 魂を みつけるよう
に 耳をすましては 幸福をつくし 不幸を
つくして 四つ葉の クローバーをさがして
いる
はんぶん生きたふりしてはんぶん死んだふり
して きょう 雨法師の花が咲いていました
河上 鴨 カワカミ カモ
①1940(昭和15)8・22②島根③広島大学三原分校卒④「青い花」「沙漠」⑤『夢の井戸』『河上鴨全詩集』鉱脈社、『不安な美神たち』『老僧』『海辺の僧侶』書肆青樹社、日本現代女流詩人叢書第51集『河上鴨詩集』芸風書院。
「ジル・ベルケ写真論」
知らない街で ジル・ベルケの写真集を買っ
た ジル・ベルケが 何者か知らない 写真
の女達は ラバー・レザー・黒のストッキン
グ・コルセット・ハイヒールと黒ずくめでポ
ンテージ系の衣裳を身につけ ロープで縛ら
れている 三年前 ヨーロッパを旅したおり
貸し切りバスがブリュッセルの街に入って飾
り窓の前を通った 乗客は騒いだ 男も女も
カメラを向けようとして添乗員に止められた
飾り窓の女の一人は 黒髪で東洋系の顔立ち
をしていてこわばった面持ちのまま 黒い下
着姿で堅い椅子に腰掛けていた ウンダー
リッヒの絵が目に浮かんだ 荒れはてた屋根
裏部屋の粗末な腰掛けに坐っている一人の狂
女 周りを数匹の鼠が飛び回っているのをも
のともせず別の世界に住んでいる ショー
ウィンドーの中に見たものは 娼婦の「荒ん
だ心」だったのかもしれない その女に重な
る見ず知らずの老女の死
川口 昌男 カワグチ マサオ
①1930(昭和5)6・21②東京③明治学院大学文学部英文学科卒④「未開」⑤『海の群列』『奪われた人間』未開出版社、『雪の旅・北の旅』花神社。
汐留の今は
汐留の今はぼくの少年が生まれ育った
時の汐留とはまるで違った街のようだ
残っているのは線路のわきの変電所と
散りぢりにされた遊び仲間たちの記憶
大空襲を免れた後 この街区を高射砲陣地に
するのだと兵隊たちが群がってまたたくまに
打ち壊した懐かしい家々と日々の暮らし――
(三か月後に国が破れるのを誰も知らず?)
強制疎開で隣り近所は離ればなれに――
彼も遠く丹沢のふもとの町の中学に転校し
麦秋の風に光る川沿いの道をひとりたどり
未知の教室へ、麦刈りにも駆り出されたり
親と離れ海軍の工場に動員されて衰弱し――
(一か月後に国が敗れるのを誰も知らず?)
汐留の今はぼくの少年の目にはきっと映る
まるで乱反射する巨大な蜃気楼のように
川島 完 カワシマ ヒロシ
①1935(昭和10)4・25②群馬③日本大学理工学部卒④「東国」「日本未来派」⑤『挿話』太田詩人クラブ、『ピエタの夜』紙鳶社、『ゴドー氏の村』日本未来派、『甲乙人』紙鳶社。
重さについて
〈重さ〉はすべて タテ社会である
バネ秤も 皿つきの竿秤も
古来より判事の顔つきの天秤も そうだ
量るとき みな少し短歌風にざわついて
すぐ 幾何級数の天命に 従う
だから 横になった体重は
本当の値ではないかも知れない
謀り計るに マジシャンが その舞台で
人体を 特に髪の長い美女を浮かせる為には
是非とも 横にする必要があるのだ
少しでも〈重み〉を等比級数的に並べ換え
少しでも見栄えを良くし
少しでも漂う気分にさせ
タテ社会の観念を固定させるためにも……
そして また
決まり切ったように薄布をかける
あれは〈重み〉より体積が
容積より空間が
さらに タテ社会より自由が欲しかった
最初の人の 発案ではないだろうか
河田 忠 カワダ マコト
①1935(昭和10)4・26②岐阜③岐阜大学国語国文学科卒④「存在」⑤『負の領域』宝文館出版、『暗愁の時』存在社、『福永武彦ノート』宝文館出版、『萩原朔太郎論』存在社。
夕凪の海
夕月が鈍く光り
薄紫色の海に
浮遊しているかのように
小舟が静かに横切っている
たそがれ時の
明るさと暗さを
くぐるように
小舟は確かに動いている
はるかな距離を隔て
灯台の明りが
狂いのない時を回転させて
止まることはない
この静けさの中
沖の海の底では
流れが流れを呼んで
激しく揺れているに違いない
ホテルの窓から眺めていると
海の底の明るさが見えてくる
夕月の鈍い光が
吸い込まれている
川田 靖子 カワダ ヤスコ
①1934(昭和9)12・16②兵庫③京都大学文学研究科修士課程卒④「嶺」⑤『北方沙漠』思潮社、『クリスタル・ゲージング』青土社、『風の薔薇』書肆山田、『わたしの庭はわたしに似ている』水売社。
その翌朝
下ぶくれのグラスには小花模様が
下から上へと花の粒を小さくしていく
生けてあるのは大輪のアマリリス
きのう 花束からこぼれ落ちた
縞目の花びらがひとひら垂れている
その向うにシャンパン・クーラー
そこにもさらに小粒の花々が
水玉模様をなして遠ざかる
目をおとすと 花模様のクロス
やっと 大きな丸テーブルに気づいた
混乱から放心へと 体じゅうがほどけて
前夜の言葉の修羅を たどりなおす
活字にすれば 飾り気ない十八世紀の名文
同じ模様が三様にサイズをかえ表情を変える
光の曲線が グラスの水をふちどる
テーブルをかこんだ人物たちはいない
ふくらんだ水の上には わずかの空間
その上をアマリリスが覆っている
血管を浮かせた花びらの一枚は
横一文字に傷ついている