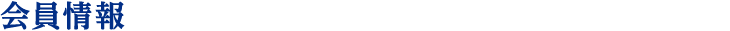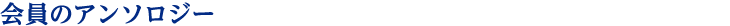会員のアンソロジー10・古賀博文氏〜
古賀 博文 コガ ヒロフミ
①1957(昭和32)11・3②佐賀③久留米工業高等専門学校卒④「青い花」「詩と創造」「いのちの籠」⑤『ポセイドンの夜』土曜美術社出版販売、『人魚のくる町』詩画工房。
家族の代償
いちばん仲がよかった姉さんも郷里へ帰り
ひとり京都に残ったキミは
寂しさを分かちあえる家族がほしかった
やさしくキミに接してくれる
男性にさそわれるまま
一つ屋根の下で暮らしはじめた
「こんなに私のことが好きだと
言ってくれるのだもの
私も好きになるかも知れないし
幸せになれるかも知れない……」
でも結婚した夫には
病的なほどのギャンブル癖があり
返しても返しきれないほどの借金があった
二三歳の花嫁は看護婦として働き
非番の日は喫茶店で働き
歌唱力をかわれて夜はナイトクラブで歌った
「妻として彼を支えなきゃって思ったの
二人目の子供が授ったけれど
育てるだけの余裕はとてもなかったなぁ
……」
でも寂しさを分かちあう家族をえるためには
あまりにも大きい代償だった気がする
木暮 克彦 コグレ カツヒコ
①1930(昭和5)11・9②東京④「時間」「北斗」「セコイア」「竜骨」⑤『城』東京書房、『迷路案内人』思潮社。
水の女
闇と 真昼の
女の 歯からの 吐息
少年の 皮膚は
孤独ではない 沈黙の 匂い
仕方なく
草 生える ところ
家 電柱
すべて 汚泥の なか
造化の 絵巻
川床を 歩行する 夢か
大地の 抱擁に
凍える口の 女が いた
小坂 太郎 コサカ タロウ
①1928(昭和3)5・30②秋田③旧制横手中学卒④「雪国」⑤『北方の眼』思潮社、『北囚』たいまつ社、『北の篝火』秋田文化出版社、『北の鷹匠』思潮社、『小坂太郎詩集』土曜美術社出版販売、『北の系譜』書肆青樹社。
くどきばなし
夜半 また早朝から
ひそひそひそと
部落の辻々をくどきばなしが通ってゆく
くどきばなしは切りがない
それはやがて 日中も行われ
農婦たちは畑に鍬を立てたまま
西山に日が暮れるまで
くどき話を続けていた
遠く農夫たちだけが
せっせと汗を流して
畑を耕していた
ぼそぼそとくどき話をする口は
飯を食わないのだろうか
とぼくは心配する
だが安心した
くどき話をする口は
飯をもりもり何杯も食っている
腹いっぱいでなければ
くどきばなしはできないそうだ
真赤な花を散らせながら
古志 秋彦 コシ アキヒコ
①1928(昭和3)9・20②新潟③東京大学仏文科卒④「同時代」⑤『海の原点』『ある空間論』木鐸社、『パスカル頌』『数学科学生』『ルベーグ積分序説』『不完全性定理』舷燈社。
ダイヤモンド・ダスト
六方晶系のダイヤモンド・ダストは
天空から銀砂を撒き散らし
めくるめく乱反射を裏返しながら
視界一面を夢幻の書割にする
真昼のような明るさに戸惑い
欠けた背景の暗部を補って
どこまでも落ちて行く水の流れに
ダイヤの切片は浮かび上がってくる
白と黒の交錯した灰色の風に
みえない砂塵は限りなく付きまとい
一途の狭霧も動こうとはしない
静かな行方に遠く立ち止まり
全天から地上に舞い降りてくるもの
ダイヤモンド・ダストは樹氷の華になった
腰原 哲朗 コシハラ テツロウ
①1936(昭和11)5・13②長野③東洋大学大学院中退⑤『リアン詩史一九三〇年代』『島崎藤村・詩と美術』木菟書館、『眩めく詩抄』土曜美術社出版販売、『信州文学の肖像』松本大学出版会。
生誕百年
結婚適齢期の女神のうちに
孫が命名された(萌香 桃夏 磐岳)それで
老子は遺言を「なぜ老子というか不明である
が、おそらく老司教の意」白川静『字統』
延命処置不要 黙禱者へ詩集進呈(哲朗)
老舗の暖簾にキズがつく百周年なんかより
原爆何年め とか殺人犯に時効があるとか
韓非子は失礼を 孫の記念樹のびすぎて
剪定されず倒されて三代めに緑蔭は消え
「誰も迎えに来ないまま百年はすぐに過ぎる」
田中清光『風景は絶頂をむかえ』
変身適齢期をすぎてなお生きる四季の恵み
生かす工夫絶対に無用 病殺とするも
「素早くカンフル二箇を心臓部に」下島勲
『人犬墨』「田端の医者短冊の句は自嘲 水洟
や鼻の先だけ暮れ残る」小穴隆一『二つの絵』
朝に道をきかば夕べに死すとも可なり とか
裏の松山セミがなくスキニスルガヨカタイ
小島 俊明 コジマ トシハル
①1934(昭和9)4・27②岐阜③早稲田大学大学院(修士)④「嶺」⑤『アッシジの雲雀』思潮社、『セバスチャン・バッハの朝』光明社、『花桐』ふらんす堂。
音の方から
目の見えない少年が
ヴァイオリンの音をさぐっていた
埃しらずのひたすらな顔から
ときおり笑みがこぼれていた
ヴァイオリンの音は自分で探しあてるもの
とヴァイオリンの先生が言った
少年は弦をきしらせ かすらせ
夢中に音を探し求めていった
あるときを境に
透明に澄んだ和音が鳴りはじめ
天空が歓びに震えひろがった
その音 その音だ! と先生がほめた
目の見えない少年は清朗な笑みに輝いた
「音が音の方からぼくをめがけてやってくる!」
小島 禄琅 コジマ ロクロウ
①1917(大正6)1・25②愛知⑤『小島禄琅詩集』土曜美術社出版販売。
蟬捕りの子供がいる団地
電車が終着駅へ差しかかった頃
とつぜん車輌後部の坐席から立ちあがり
釣革をつかんで誰にともなく呼びかけた蓬髪
の中年男がいる
きみらはレイテの亡霊を知っているか
一万人――林をさまよって斃れた奴等だ
蒼ざめた貌だった
あれは終戦の暫く前だった
レイテの男は醉った三白眼が吊り上っていた
仮住いの団地に移り住んで一箇月が過ぎていた
八月六日・九日が瞬く間に過ぎた
団地ではプラタナスの大木が光る葉を翻して
いた
秋が立ったのだ
六十何年目かの平和の色を耀かせる艶やかな
葉の掌だ
子供が今日も蟬捕りをしている
こたき こなみ コタキ コナミ
①1936(昭和11)12・6②北海道③小樽潮陵高校卒④「火牛」⑤『キッチン・スキャンダル』レアリテの会、『銀河葬礼』花神社、『幻野行』思潮社、『星の灰』『夢化け』書肆青樹社。
あぶない関係
猫たちが日だまりで目をほそめている
よかったねえ きみたちあまり利口でなくて
犬なら命がけで忠義を強いられるよ
よかったねえ あれほど大きくなくて
馬なら死ぬほど走らされるよ
よかったねえ あんなに太ってなくて
豚なら死なされて喰われるよ
よかったねえ 何より人間でなくて
こんなに罪を犯さずにすんで
*
猫たちを飼ってみるとあまりに人間に似てい
るのに驚く ならば人間も大して威張れない
な 言葉をあやつり熱物が食べられる舌と器
用な手先ぐらい 不器用で口下手な私は間
違って人間の国に来てしまったか でものろ
まだから猫に生まれても鼠捕りどころか す
ぐ捕まって三味線の皮 少しはいい音色を出
しただろうか 今とちがって
「怪しい関係」抄
小寺 雄造 コデラ ユウゾウ
①1936(昭和11)10・4②鳥取③鳥取大学学芸学部卒④「菱」⑤『稲羽たちかわむら』詩の会・裸足、『挽木橋にて』菱の会。
「並」
遠出できなくなった年寄りに代って
〝墓守や〟という職業ができた
(お墓参り、代行します)
読経や掃除のランク――
「上」・経上げは丁寧に十五分(宗派に応じ)
(極上の純白檀香を使用)
「並」・経はすっきりと五分
(短めの芳仙香を使って)
「下」・かんたんに 心経を二回
(ローソクはごく短く)
インスタントカメラに収めた
墓参の始終に
請求書を付けて
ゆう送する
老人は「下」を支払い
近くのスーパーで
豚肉の「並」を求めて
恐るおそる
食む
後藤 基宗子 ゴトウ キソコ
①1944(昭和19)4・1②福島③岩瀬高等看護学院卒④「漪」⑤『0』私家版、『三月は奇妙な月』私家版、『こわれた鞴のように』ヤシマ孔房、『風とあくしゅ』銀の鈴社、『かわらなでしこ』国文社。
ひたすらに
早贅の虫が枝高く刺してある山間の
霜枯れの田の一隅に
青い炎が燃えている
刈り取られた稲株から出た蘖
日が差せば
炎は白く細く身を捩りながら谷間を泳ぎ
空に向かい
陰れば濃い緑色に静まる
もうすぐ途方もなく深い雪が降ると知って
なぜ 芽生えなければならなかったか
喘ぎながら 震えながら
白い息をしている
本当に美しいものは
花も実も求めず
いや それさえ考えず
与えられた命の今の今を
ひっそり
ただひたすらに生きている
後藤 順 ゴトウ ジュン
①1953(昭和28)8・5②岐阜③立命館大学経営学部中退⑤『日本海かぶれ』未来工房。
どれほど死ねば
サクラ冷えの頃だろう
燃えた父の喉仏を盗み入れた
ズボンの左ポケット
いつまでも太股をあたためた
父が好きだった金木犀
雪が積もった根元に深く埋めた
骨はゆっくり冷めるのか
太股に残った赤アザ
借金のかたに家をとられ
思い出が更地になっても
切られた金木犀から 小さな芽
風に運ばれる父の匂い
どれほど死ねば
悪戯の赤アザは消えるのか
骨はセミの幼虫に化け
建ったビルの底で私を待っている
五藤 俊弘 ゴトウ トシヒロ
①1931(昭和8)8・6②広島③広島大学教育学部卒④「蘭」⑤『走駆症』。
ショショ ザンショ
電車はカーブしたままでエキに停っている
ドアは開けっぱなし
まるで吹抜屋台のように
ビーチサンダルの子供が
両足をばたばたさせている
その左側でおばさんがボトルを傾けている
ずっと向こうの座席で
男が競艇新聞を広げている
どこかでケイタイのコール音がした
《うん いまエキ ううん まだなかなか
だって そっち直通でしょ いや 動かない
んだから ジコ 動いてもジコ? そういえ
ばなんだかジコみたい とにかく そう エ
キはここしかないんだから》
電車はあいかわらず昼寝している
ホームにはだれもいない
おもちゃのような駅舍ももちろん無人
白いコンクリートの上に桜の枝の影模様
ショショ ザンショ
夏というシーズンが過ぎて
暑さだけが置き去りになって(以下略)
小長谷 清実 コナガヤ キヨミ
①1936(昭和11)2・16②静岡③上智大学英文学科卒⑤『小航海26』百鬼界、『脱けがら狩り』思潮社、『わが友、泥ん人』書肆山田。
塵芥のなかへ
土砂降りの雨のなかへ
どさっと放り出される塵芥のかたまり
そのかたまりのなかから
慌てふためき這い出てきて
あっちへこっちへ そしてどっちへ
迷走を続ける変な生きもの
あしたへあさってへ そしていつかへ
私もどきの奇な生きもの
その当てどなさ 捕らえがたさが
もしや詩ではないか と愚かにも
その滅裂な動きをスケッチしておこうと
ひとまずは土砂降りを逃れ
何処へ? こともあろうか
またしても塵芥のかたまりのなかへ
小長谷 源治 コナガヤ ゲンジ
①1928(昭和3)7・10②静岡③静岡第一師範学校卒④「文芸広場」「焰」⑤『消えない映像』『取ッテオキノ話』近代文藝社、『探している』書肆青樹社。
やきいん
かわいがってくださった
ねっしんにおしえてくださった
しかしそれだけではこうもしたわないでしょう
「ぐんたいはいいところでない
ぐんじんにはならないがいい」
とははにいわれたことば
ひとにわかったらたいへんなことば
このことばでせんせいをにほんいちとおもう
たましいへのやきいん
それは50ねんもまえのこと
いみするところがわかったのはせんごのなが
いみちのべ
サイパンとうほうめんのふかいうなそこにお
られる
「なにものにもそくばくされぬじゆうのせい
しん」とともに
小西 たか子 コニシ タカコ
①1937(昭和12)8・22②兵庫③武庫川女子短期大学教育科卒④「現代詩神戸」「アリゼ」「花筏」⑤『野のまわり』野火叢書、『北にある窓』花神社、『珈琲館』書肆青樹社、『公園のブランコ』摩耶出版、『水甕』湯川書房。
水甕
土間のひと隅をいまも陣取る水甕
甕の肌を布でぬぐうと艶やかに光って
女の背負ってきた履歴をよみがえらせてくる
通し土間の下駄の音
湿った井の底のような厨で
家族の寝静まった一日の終わりに
甕に水を汲み入れ蓋をする母の手が見える
味噌汁の香のたちのぼるそば
母は手を赤くしながら
青菜を洗っていた遠い水路が
台所にも通じていて
わたしの水とあいまって流れていく
スイッチを押すと御飯が炊け
選択キーで料理を選ぶ
似てもにつかぬ暮らしをしていても
母たちの伏線をたどり水に寄り添っている
したたる水滴を身におさめた母の心を
いまわたしが掬いあげている
木場 とし子 コバ トシコ
①1950(昭和25)4・22②東京③第一商業高校卒④「山脈」⑤『白いとき』『反哺の部屋』『不忍あたり』山脈文庫。
朧な春
桜並木を歩く
夕刻の温い風が盛りを過ぎた花びらを散らす
風の勢いが変わると
花衣を広げたように
暮れかけた空が華やぎ
老木の足元から
産まれたばかりの薄桃色に染まる若い蕾
みるみる暮れてくる緩い坂道が
微かに傾いでくる処
曲がり角から湧いたように
ゆうらり仄かに揺れるおじいさんの
酔いの始めに出会いたいもの
何処でどう酔いを深めるのか
毎日同じ時刻にあの角から
ふうわりと現れる
酒精に気を抜き取られた
ただ揺れるものか
一陣の風に跡形もない
小林 小夜子 コバヤシ サヨコ
①1938(昭和13)6・8②北海道③北海道ドレスメーカ女学院師範科卒④「新現代詩」「複眼系」⑤『卵宇宙』『歳』緑鯨社。
だから
だから 問答無用
だから 嫌われるから無口になるんだ
だから 地球がどんなに歪んで傾いて現代は
窒息しそうになっても生きている
だから 生きる為には無限に耐える事なんだ
だから 春 花が一斉に咲いても たましい
のぬけた肉体だけがうようよひしめきあっ
て流氷のような火花を散らし殺し合っても
咲いているのだ
だから 老齢化社会の確実な兆しに神経をゴ
リゴリかじられ福祉がアップアップしてい
るんだ
だから 少しくらい痔が痛くて眠られなくて
も誰も起こすことなどないのだ
だから シーラカンスの生きた化石に人間解
体の根源を求めて歴史的散歩を楽しむんだ
だから だからが足の踏所もないほど地球の
そこいら中を埋めつくしているのだ
だから だからの廃品利用の看板を掲げて!!
だから は 賢治菩?になりたいのだ
小林 登茂子 コバヤシ トモコ
①1944(昭和19)1・24②東京③法政大学卒④「地球」⑤『扉の向こう』地球社、『シルクロード詩篇』北溟社。
出会いと別れ
一一歳まで日本にいたのです
高貞愛さんの堪能な日本語
五〇数年前の記憶に灯りがともった
昭和二〇年代後半
私の小学校でも朝鮮に帰った人がいた
窓から身を乗り出して
希望に燃えた笑顔で手を振った友
私よりいくつか上で一緒に登校した彼女は
韓国へ渡ったのか
北上して鮮やかな朝の国へ渡ったのか
アカシアの花咲く季節
韓国で高貞愛さんの詩を日本語で朗読した
ありがとう大満足です
にぎり合った手のぬくもり
半世紀前に別れた友は
日本語を覚えているだろうか
もっと遠いところに旅立ったろうか
小林 憲子 コバヤシ ノリコ
①1929(昭和4)6・11②東京③旧制高女卒④「路」⑤『干潟』路の会、『壺』東洋出版社、『島を探しに』花神社。
初冬
湯の宿の前庭は
石蕗の花むらの小径
潮風に耐えて咲く黄の花
やっと実現した五人姉妹の旅
十年ほど前から
再三 再四 計画しては潰れ
それぞれの暮しを纏いながら
熟女たちは
いつの間にか老女になっていた
ちち はは のこと
戦時下の少女時代の明け暮れ
住んでいた荻窪教会通り
ワイングラスを傾け
はじめての姉妹の旅に
松籟と海鳴りの夜は濃くなり
明日も冬晴れという予報……
小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ
①1960(昭和35)2・22②京都③大阪大学大学院基礎工学研究科④「スウカイナ」「ひょうたん」「ガニメデ」⑤『不規則な組換えと長い転移を巡る装置』詩学社、『分子状基質』書肆山田。
シャルダン断章
夜の海で仄かに白く隔たっている。シャルダ
ンの光である。物たちが独自の光を携えてい
るのだろうか? シャルダンによって呼び出
された物たち。それ自身眠り込もうとする輪
郭に満たされながら、有り続けることに輪郭
を失っている。境界を越えての連鎖なのか判
明しがたい音に交絡されているのか。記号の
ように夜の海が満ちてくるだろう。(死んだ
自然)の呼びかけへの応答は、判明してくる
糸車であり赤味の差した?であった。シャル
ダンの光は夜の海を潜るのだった。分割では
なくそれらとの応答であり曖昧に接続するこ
となく生きてきた友たち。すぐ近くの記憶な
のか? 愛のように溶け合うことなく夜に渡
される。呼びかけの言葉を携えて、開かれ、
台所の水差しと果物たちは身を引いていくだ
ろう。あるいは少年の秘密が懐胎/委ねられ、
応答における光へと返ってくるにしても、そ
れ自身の欠落を埋めることはできない。友た
ちが横たわるだろう、それとは知らずして。
小林 稔 コバヤシ ミノル
①1948(昭和23)4・15②埼玉③成蹊大学文学部英米文学科卒④「へにあすま」「ヒーメロス」⑤『白蛇』『砂漠のカナリア』『夏の氾濫』『蛇行するセーヌ』天使舎、『砂の襞』思潮社。
夏の死者
銀盤からこぼれ落ちる水の疲れのように
樹林を抜け 草むらをなびかせ たゆたう
白紙をかすめて けだるく物憂い旋律の
時にさざなみ立つ沼にフォルテの不意打ち
帆に風をはらんでたわむ白布の留め金が外れ
包まれながら転げ廻り戯れる三人の学童たち
遠い部屋のひらかれた扉から洩れ聴こえる
アンダンテスピナート 夏の死者がほほえむ
野原には雨にやつれ風に打たれた書物の
めくれ立つ干からびたページの余白に
陽炎のように昇りつめる文字のつらなり
暗く黄昏る それとも明けゆく黎明の森の端
鈍いきんいろの光に照らされ両手を合わせる
ふたりの嬰児のフォトグラフィー
幼いキリストと洗礼者ヨハネの絵にも似て
三十三間堂の千体の仏像から放たれる閃光
はるかなる人を恋こがれる革命の前夜
銃声が石の壁をつき崩して舗石はめくれ
庭の木に滝のように落ちる驟雨が静まり
船大工の楔を打つ音 あるいは葬儀屋の
棺にハンマーを降ろす釘音が響きわたる
駒井 耀介 コマイ ヨウスケ
①1940(昭和15)7・15②岩手③釜石高校卒④「門」「橅」「マグノリア」⑤『不在の窓辺』草心社、『風の記憶』第一書肆、『岩手の文学碑』岩手日報社、『啄木の海と山』緑の笛豆本の会、『岩手の山菜百科』岩手日報社。
衣川
こんなにも全身の細胞が発熱沸騰するのは
太陽の憤怒が大気を血糊色に焦がしているか
らではない
死者たちの無念の思いが発酵して熱気となり
放射してくるからでもない
長者ケ原廃寺跡を覆う蓬に宿る霊気に導かれ
やっと辿り着いた衣の関は葛の葉の暗がりで
静かに燐光を発している
意趣も野心もないまほろばの野に
突然 野火が広がり無数の豹紋蝶が飛び立ち
夕焼けに溶けていった日々
空漠の野に放心した魂だけが残り
やがて 雨とともに地に染み
地霊となった衆生の夢よ
見渡せば蔓草からみつく両岸の藪を写して
泥川が病んで
(病んで)
澱んで
(澱んで)
長い影を曳く石碑がひとつ
小町 よしこ コマチ ヨシコ
①1942(昭和17)②東京③実践女子大学文家政学部家政学科卒④「砧」「花筏」⑤『姉小路』野火叢書、『椿の家』土曜美術社出版販売。
花の塚
〈身にしむや亡妻の櫛を閏に蹈む 蕪村〉
『歳時記』など手にしたこともない男が
いつ頁を繰ったのだろう
赤鉛筆で色濃く印した一句
男のちいさな家には
亡妻が好んだという椿の花が
冬から春の庭を彩っていて
男の胸の裡にも
椿はひそやかにあって
朝毎に仏前に手向ける香華は
胸の裡に育てている花への
水遣りだったのだ
小松 郁子 コマツ イクコ
①1921(大正10)3・21②岡山③東京女子高等師範学校(現・お茶の水女子大)卒④「歴程」⑤『三匹のとけだした犬』思潮社、『わたしの「夢十夜」』砂子屋書房。
継母
継母と軽便鉄道で出かけた
軽便鉄道は黒い小さな二輌の車輌で
みどり色の座席が両方の窓側についている
みわたす限りたんぼのつづく中を
西大寺から後楽園まで
とことこ、とことこと、走っていくのだ
途中で、もう川ではない百軒川をこえる
内田百閒の百軒だ
やっと席をみつけて安心してから
かたわらに継母がいないのに気づいた
のびあがって後の車輌をみると
いつものねずみ色の着物を着て
継母はちんまりと坐っていた
そのとき
あのひと とっくに死んだのだとやっと気が
ついた
そういえば
継母の死んだ夏
東京のわたしのマンションの
ベランダの朝顔は白い花ばかり咲かせていた
のを思い出した
小松 弘愛 コマツ ヒロヨシ
①1934(昭和9)11・13②高知③高知大学教育学部卒④「兆」「火牛」⑤『狂泉物語』混沌社、『幻の船』『ポケットの中の空地』花神社、『小松弘愛詩集』土曜美術社出版販売、『どこか偽者めいた』花神社。
わたしの背後で
センダイヤ桜の花びらが散り敷く道
キュッと自転車のブレーキをかけ
前方の光景を眺める
幼い女の子が水色の上着のポケットから
一握りの花びらを取り出して散らし
また取り出しては風に流している
花びらがなくなれば
地上の花びらを小さい手にかき集め
ポケットいっぱいにふくらませて
女の子のそばに行ってみたいと思ったが
あえて
手前で折れる小道に自転車を入れる
わたしの背後で
センダイヤ桜の花びらが風に散り
風に流れる
こもた 小夜子 コモタ サヨコ
①1950(昭和25)11・23②香川④「青い花」「野獣」⑤『森は晴れている』七月堂、『モリーナの部屋』書肆青樹社。
仕度
ひとは風を通して
旅の仕度をする
白い壁にかかるしなやかな枝
そよぎあう葉群の
薄いみどりとなって
ひとは影を通して
壊された家しまわれた庭を
すり抜けてゆく
風もないのにひるがえる海を
思い出そうとしている
ひとは薄いみどりとなって
こぼれる想いひとつで
けっして濡れることのない
波打ち際へと
続く道を知っている
小柳 玲子 コヤナギ レイコ
①1935(昭和10)5・8②東京③青山学院大学英米文学科中退④「六分儀」「きょうは詩人」⑤『芦の里から』花神社、『叔母さんの家』駒込書房、『黄泉のうさぎ』『夜の小さな標』花神社。
初夏
大家族が離散の日
4号ほどの油絵がいちまい
私へのわけまえになった
持ち物がほとんどない私は
絵を壁にかけると 引越しは終ってしまった
絵の中には飯茶碗と汁椀だけが置かれ
そこは朝なのだった
空気の気配で私にはそれが分かる
食卓の縁も 皿や小鉢も見えない
簡素で唐突な絵
それでも目を凝らすと
白い茶碗のうち側に
かすかに窓が映っている
絵にはない窓がその部屋のどこかにあるのだ
私が決して見ることのない
その古い窓の外を 誰か通り過ぎていく
私が会うことのないその人は
早い夏の服を着て
絵のずっと奥へ消えていく
あまり遠くて 足音も聞こえない
①1944(昭和19)2・14②東京③武蔵野女子学院高校卒④「詩話」「孔雀船」「青い花」⑤『冬の門』昭森社、『純愛症候群』『ら・まんま』『あたしはあたし』思潮社。その他「連詩集」。
日々のくぼみで
くさった雨の日暮れに魚のはらわたを抜く女
死んだ臓器を 永遠に産めない胎児のように
隠し持っていることを忘れたふりしている女
生きているものは必ず死ぬ という お約束
もののけの時間 まっとうな女の時間 でも
なぜか いつも腥い匂いに包まれているのだ
抜き差しならない足の甲の淫らにふくらんだ
静脈 迷走する けもの道 何が待つのやら
生と死を右手と左手のように規則正しく振る
幻想のウォーキング オイッチニオイッチニ
足がもつれて転びそうになる 必死に堪える
そうして立っているキッチン ステンレスの
解剖台に似た必要以上の清潔さ ぴっかぴか
雨の音は いつも体の中 血流と混りあって
錯綜する神経のネットをくぐる そのネット
不安という名の蜘蛛がひっかかったまんまで
逃げもせず死にもせず 眼だけが妙に力強い
きょうが終わる少しずつ沈んでゆく底無し沼
生温い感触は 睡魔の 毛むくじゃらの指だ
くすぐられてエクスタシー のけぞって眠る
最匠 展子 サイショウ ノブコ
①1929(昭和4)3・16②東京③日本女子大学文学部卒⑤『在処』思潮社、『部屋』地球社、『そこから先へ』青土社、『微笑する月』思潮社、『絶章』書肆山田。
世紀の揺れを
日常の隙間に偶合のように 連れていかれる
過去のまたは未来の 鮮やかな幻影
百年後には 今この地上にひしめく
生きとし生けるものは もはや存在しない
想像もつかぬ目鼻立ちの 人や獸や文明が
不気味に闊歩する
ことごとくあの不可知な死を 通過するのだ
負の部分の象徴のように狂者が増し
正の証しとしての英雄が踊るだろう
喜々と顔をあげ あるいは黙々と首を垂れ
それでも人びとは切々と生きるだろう
たっぷりと詰っている
熱い時 澱んでいる時 歪んだ時
この建物ごとがまるごと流れていく 時の川
取返しのつかない岸 加速を増していく景色
まだヒトが発生するずっと以前から
朝ごとに地球は明け
刻印されていく 変容の歳月
世紀の揺れ を
斎田 朋雄 サイタ トモオ
①1914(大正3)7・23②群馬④「西毛文学」⑤『ムシバガイタイ』『斎田朋雄全詩集』『大手拓次の実像』。
回想ロマン
十時のお茶の時間で食堂へ行くとテレビが
「岡田嘉子ロマン」を放映していてわが青春
期ともダブルので思わず懐かしきに魅入った
岡田嘉子は昭和初頭の思想の時代に恋人杉
本良三と思想と恋の就達のため樺太国境線を
越境逃走したが 共産国家旧ソ連は理想の楽
園ではなく 恋人杉本は国権謀略でスパイと
して暗殺される だが岡田嘉子のその優れた
才能のため第二次世界戦争時日本語アナウン
サー それなりの優遇をうけて戦後は数度日
本への帰国さえ許された その岡田嘉子の古
い親交の中に日本の代表的女性詩人深尾須磨
子がいた 僕は縁あって後輩として晩年の深
尾さんに可愛がられ「東京へ出たら寄りなさ
い」と 度々西新宿のお宅を訪問すると「こ
れは世界の銘酒よ」と優遇されて 下戸で不
器用な身が口惜しかった。 最晩年深尾さん
は死期を悟ると単身モスクワへ飛んで岡田さ
んと惜別して帰国すると間もなくあの世に旅
立った
わが青春の政治とラブ 岡田さん深尾さん
懐かしい ダブル回想ロマンであった
斎藤 和明 サイトウ カズアキ
①1935(昭和10)3・31②東京③国際基督教大学卒④「火牛」「同時代」⑤『あーるす・ぽえーてぃか』開文社出版。
木馬の詭計(部分)
——「アキレウスは、プリアモスに示した休戦和
平の約束が自分に裏切られるという不安を抱かさ
ぬよう、老王の手首をしっかりと握りしめたの
だった。」
浜には異様な巨大な何物かが置かれたまま
だった
木馬だった
われらの視覚抉られ眼球裏返った
イーリオス城の門外は異常に静か
トロイアの軍勢はみな訝しがった
果たしてわれらの側が勝利したのか
木馬を見よ
アテーネー神への奉納感謝のしるしとの銘が
彫られている
軍団は戦いに厭いたのだ撤退したのだ
城内から出たトロイアの兵士ら銘を熟視し大
声で叫んだ
敵軍に勝った
城内でも誰彼なく叫びをあげる
だが囁く声がするこれは痛み分けだ
木馬を引き入れるとなそれはまずい
斎藤 恵子 サイトウ ケイコ
①1950(昭和25)2・20②岡山③岡山大学法文学部史学科卒④「火片」「どぅるかまら」⑤『樹間』『夕区』『無月となのはな』思潮社。
背後で
臭気をあげビルが傾いでゆく
谷間に肉汁色の川がながれる
地下鉄から吐き出されるひとびと
いつのまにかわたしがいる
ひとのあとについてゆけば出口なのだ
みな黒いきれいな靴をはいている
かおはなくわたしのかおも電車のかおもない
ここで立ち止まってはいけません
アナウンスの声が大きくなる
自分の声は聴いてはならない
ここで泣いてもいけないのだ
犯罪になる
金属音がきしむ
地上の舗道を銀杏が黄色い葉っぱの手
だけになってひらひらあるいている
高層ビルから墜ちてくる黒い震え
カオカオカオ
おにぎりとペットボトルのポリ袋を持つ
背後でコンビニが炎上している
斎藤 彰吾 サイトウ ショウゴ
①1932(昭和7)6・30②岩手③黒沢尻高校(現黒北高)卒④「ベン・ベロコ」「堅香子」「新現代詩」⑤『榛の木と夜明け』Làの会、『イーハトーボの太陽』靑磁社。
白河以北一山百文
ぼくは 今
やまがた・ありともと はら・たかしが
拳あげ卓をたたく喧喧諤諤の只なかにいます
雪がふり まるで稲光りのさくれつです
やまがた・ありともは言うのです
「何んだ 東北唐変木どん百姓の役立たず
白河以北は ひとやまひゃくもん
すかさずはら・たかしが反駁します
「何んだ 長州長提灯の足軽め
藩閥固めの政治はめらめら燃え焦げるのみ
それから名乗りをあげたのです
したためた句に 「一山」と
日に一度 納豆が好物の原敬でした
聞くだけで眉をひそめる山県有朋でした
レールにきさらぎの雪ふりつもり
事件がスパークする帝都の夜でありました
齋藤 澄子 サイトウ スミコ
①1933(昭和8)2・20②徳島③徳島大学学芸学部卒⑤『世紀末の接続詞たち』砂子屋書房、『一人芝居』『人間がワイングラスになる方法』思潮社。
地球の号泣
瀕死の床につく地球は、病院ではなく空で
眠っていて、介護する医師も看護士もいない。
髪伸ばし放題の地球は、それでも歌をうたお
うとする。夕暮れ時の虹から細いファルセッ
トの歌が聞こえたら、それは地球の歌声だ。
人類への愛の讃歌。でも人々は長い黒い舌を
出し地球を蹂躙しつづけた。がまんする地球
は衰えた自分のために音のする香炉をたく。
ああ、凋滅に先立つ地球の声は人々の耳をか
すめて舞いのぼる。号泣する地球は鬼に変じ、
額からしたたり落ちる血を拭いもせず、温暖
化、水面上昇、食糧不足、砂漠化をひきずっ
て阿修羅の如く走る。地球の号泣に耳を傾け、
国の施策よ人々よ、地球の苦悩の中心に歩め。
地球の魂のほとりを際限なく汚すゴミ。コレ
ハ人間の傲慢ダ。ワタシ、ごみヲ分別スル。
ナマゴミは大地にカエス。買い物はエコバッ
グで。こまめに電源を切る、ナドナドナド。
わたしは手を合わせて地球を祈る。人類の袋
のほころびから、こぼれないでください地球。
あわてて上手にきっと、袋を繕いますから。
斎藤 久夫 サイトウ ヒサオ
①1945(昭和20)3・9②福島③早稲田大学第一文学部英文専修⑤『黒船前後』土曜美術社出版販売。
キリマンジャロの雪
「今、キリマンジャロには雪がない」
昼間見たテレビの声に促されて
短編小説の終末を 白い雪の頂上の
主人公の死を確かめるように
棚の奥から古い短編集を探している
記憶の誤りだったいや
完全な誤読だったのだ
死の場所は真白く陽光に輝く
キリマンジャロの山頂ではなかった
空を飛ぶ白い幻影は消えて
妻の胸の震えで短編は終わってゆく
ハリーの壊疽の足を包んだ包帯はみな解け
彼らは野営地にいて テントの外では
ハイエナが奇妙な音をたてていた
アフリカ最高峰頂き近くに横たわる
干からびて凍りついたという
豹の行方もいくら読みかえしてみても
どのページにも記されてはいない
斎藤 祐史 サイトウ ヒロシ
①1963(昭和38)②群馬③中央大学経済学部経済学科卒⑤『道』『鏡の中の現実』『銀色の骨』『朝の禁猟区』潮流出版社。
弟よ
俺とおまえは双子の兄弟で
俺が兄でおまえが弟
帝王切開で産まれた俺たちは
体重が三〇〇グラム多いというだけで
俺が兄となった
でもまるで逆 おまえの方が
ずっと男らしかった
幼い頃から父に叱られると俺は泣いたが
おまえは決して泣かなかった
「叱られているのに笑う奴があるか」
おまえは父によく言われていた
おまえの美学は
(男は泣かない)という美学
だから叱られると
バツが悪そうに笑うのだ
ちょっとピエロのように
だが何の前触れもなく
おまえは死んでしまった
もう二度と
あのバツの悪そうな笑顔は見れない
斎藤 正敏 サイトウ マサトシ
①1942(昭和17)1・13②千葉③二松学舎大学文学部国文学科卒④「光芒」「地球」「独楽」⑤『耳喰抄』崙書房、『斎藤正敏詩集』四海社。
一日
可もなし不可もなし
そんな一日が終った
これって 幸せ
それとも 不幸せ
ただひとつ言えること
こうして 人は確実にじじいに近づく
そして もうひとつ言えること
こんな一日を 誰が
平穏無事というだろう
なにも無かったような一日でも
人には おそらくひとつやふたつの心配ごと
があるものだ
病いでヨタヨタのおっかさん 狢が狢と笑っ
ている人間関係 少し不足の財布の中味
おおい なんの変哲もない一日よ
おまえは 結構厄介だ
可もなし 不可もなし
加えて心配事の ふたつ みつ
斉藤 征義 サイトウ マサヨシ
①1943(昭和18)3・20②北海道③苫小牧東高校卒④「極光」⑤『コスモス海岸』土曜美術社出版販売、『宇宙船売却』響文社、『午後の契約』北海詩人社。
老いたチエロ
雪じゃないよ
雪だよ
谷あいのひきざくらをながめながら
母熊と子熊がよりそっている話の耳もとで
わたしはねむり
うぱし あん うぱし ぽろ
うぱし あん うぱし ぽろ
白くたちこめるひかりのなかに
白い花の木を見る
ほころびていくからだに なにもかもまにあ
わない 魂でさえも
歩いてきた道の遠い埃りは 石板色にくすみ
うぱし あん うぱし ぽろ うぱし あん
うぱし ぽろ まだ呼吸をしている昆虫が奏
でている オプケニヘの伝言も 次へ次へと
伝えるもののために 白いひかりは影をつく
るのだが チエロはいつ船に変身するのだろ
う 火星の頂きに雪がふっている
斎藤 貢 サイトウ ミツグ
①1954(昭和29)10・14②福島③茨城大学卒④「白亜紀」「歴程」⑤『奇妙な容器』詩学社、『蜜月前後』『モルダウから山振まで』思潮社。
縁について
ひとの縁というものは
不思議なものだ。
「糸」偏の
身体の「ヘリ」で
繋がっているあなたと
梨が四つ。
静物画の小さな皿のような
この世界の上で。
ほら もう既に
「お元気ですか?」
挨拶を交している。
梨は
果実の香りを放ちながら。
あなたは
まろやかに熟成しながら。
斎藤 勇一 サイトウ ユウイチ
①1938(昭和13)10・18②秋田③秋田商業高校卒④「日本海詩人」⑤『誕生』狼の会、『郷愁の風』『オホーツクの風』『ネフド砂漠の海』『詩人たちのいる風景』『本郷隆――ある詩人の精神の軌跡』秋田文化出版。
一閃の光芒
この地点は、
宇宙からは、
どのように見えるのだろう。
流れる雲と、
くっきりと紫色に彩られた、
山脈を眺めながら、
その美しさについてゆっくり語りたいと思う。
ここにあるのは静寂のみ。
自分の心の中に、
ゆっくり分け入って
思考の旅を続ける時だ。
曇った空の彼方から、
呼びかけてくる声が聴こえてくる。
こんな時だ。
祝祭の輝きが、
一瞬 素早く、
鳥の翼と共に飛び去ってゆくのは。
斎藤 庸一 サイトウ ヨウイチ
①1923(大正12)3・30②福島⑤『ゲンの馬鹿』、『雑魚寝の家族』。評伝集『詩人遍歴』、『詩に架ける橋』『戦争を生きた詩人たち』。
明けがたの烽火台
元の麻布三連隊の裏門を出て
冬枯れの雑草を踏んで高台に立つと
そこから青山墓地のくらい森が見わたせる
あ あの右手の駐車場のあたりか
兵隊の私たちは東京空襲の屍体を集め
頭をもつ奴と足をもつ者の二人が組んで
トラックに放り投げた屍体を運び
そう あの辺に屍体の山を築いたものさ
二階建ほどのピラミッド状の屍体の山がいくつか
三日間の屍体引渡し期間のあとは
読経もなく火葬もなく死臭の廃棄物として
大きな穴を掘って埋めた記憶が甦ってくる
嫌だったのは雨の夜の屍体衛兵
巡察の兵が無数の幽霊に追われて逃げてくる
赤むくれの女の屍体がにたりと笑う
幼い子供の眼はひらいたまま雨にぬれていた
あれから五十年も経っているのに
明けがたのまどろみの中に現れてくる(後略)
在間 洋子 ザイマ ヨウコ
①1941(昭和16)11・26②愛媛③広島大学教育学部国語科卒④「別嬢」「花筏」「アリゼ」⑤『花瓶の水』土曜美術社出版販売、『船着場』湯川書房。
雲とぶ山
〈天空の雲とぶ山〉
と先住民が呼ぶ
マウントクック
ニュージーランドの最高峰
頂の万年雪は
一度も溶けたことがない
生まれた時から雪
永遠に雪
と固い信心
雲は
いつだって旅の途中
水から生まれて水へ還る
仮の姿の雲なのか
仮の姿の水なのか
知っちゃいないさ
とばかり
輝く雪
のどかな雲
佐伯 多美子 サエキ タミコ
①1941(昭和16)②東京④「すぴんくす」「カラ」⑤『自転車に乗った死者』詩学社、『果て』『睡眠の軌跡』思潮社。
浅い闇が佇んでいる
闇が 眼前に
広がる
盲目の眼底によどむような
背後は崖
背後のまあたらしい痛み
盲目と崖が切り結ぶ境界
に 佇つ
佇つ闇は
眼前の闇にくらべてはるかに浅い
浅い闇は 透けて
動脈の静脈の血管の
血液の正常な循環もかすかに見え
闇の血は
墨汁のような濃淡がかさなり
盲目と崖の狭間で 浅い闇が
佇んでいる
棹見 拓史 サオミ タクシ
①1935(昭和10)②愛媛③立命館大学卒④「蘭」「ばらた」⑤『奇妙な仕事』蘭発行所、『うすく笑う青空』『かげろうの森で』創風社出版。
扉
「腹を割って話し合おう」と その男はやっ
てきたのだが 私はいやな予感がした
私はシャツのボタンをはずし 腹の扉を開く
と 男の前に突きだした 男は待っていたか
のように 顔の扉を開いてきた が その奥
には古いカーテンが降りていて その破れ目
から 光る二つの眼が見えた
「それなれば 猫の方がまだましなのです」
と私はいった 「猫の尾には扉が並列になら
んでいて 始終開閉しているのです それぞ
れの開いた瞬間を眼にすれば 猫の気持が見
えるというものです」
男は即座に顔の扉を閉じると 怒って 玄関
からでていった
その都度に合った扉を開け閉めして 私の体
は疲弊していく つまり少しずつ縮んでいく
のだ 今朝も私は 錆びて重いすべての扉を
閉じ 道端に吹きだまっている 縮んだ人を
何人も見てきたところであった
嵯峨 恵子 サガ ケイコ
①1955(昭和30)1・8②兵庫③二松学舎大学文学研究科修士課程卒④「ガーネット」「歴程」⑤『悠々といそげ』思潮社、『おかえり』アートランド、『愛すべき人びと』思潮社、『クスクス』花神社。
遠い親戚
じめじめした季節
体がじっとり汗ばむ人たちとは違い
この時期 私の肌はしっとりして調子いい
ナッツをポリポリやりながら
祖先は亜熱帯から来たかなと考える
私は閉所恐怖症である
狭い場所に閉じ込められ詰問などされたら
あることないこと話してしまうのでは
そのくせ 高いところは全く平気
窓から両手を広げ鳥のように身を乗り出すと
あわてて友人たちが引っ張り降ろす
うっそうとしたジャングル奥深く
大きな見晴らしのよい樹があって
じゃんじゃん降る雨の中
てっぺんで葉っぱの傘さして
木の実をかじっているお猿さんがいたら
(いや きっといる)
それは私の遠い親戚
境 節 サカイ セツ
①1932(昭和7年)5・2②岡山③法政大学文学部日本文学科卒④「黄薔薇」「歩く木」⑤『呼び出す声』編集工房ノア、『ひしめくものたち』『鳥は飛んだ』『スマイル』『ソウルの空』『道』『薔薇の はなびら』思潮社。
行く
ふしぎな かたちに魅せられて
得体のしれない ことがらになる
山の存在をおそれながら
したしい気持がおさえられなく
少し登って あとずさりする
海を恐れているのに
近づく
自然の力をからだに受けて
枝々から わずかな のぞみが
光っている日
気に入ったものばかり
あつめてくらしている ひとが
捨てる行為をはじめたと
伝えてくる
ゆるやかな勾配が
急に迫って立っている
はげしい音が
おそってくる気配さえ
拒否できない
生きている足場を
はずされて
坂上 清 サカガミ キヨシ
①1928(昭和3)5・18②兵庫③八尾高校卒④「騒」⑤『木精の道』『丘陵の道』『虹霓の道』皓星社、『坂上清詩集』砂子屋書房。
流れていく手
丘陵の谷間を縫って
猛烈な勢いで
手が流れていく
群をなして
まだ暗いターミナルへ
手が流れ込んでいくのだ
生きのこった小鳥たちが
小首をかしげ
樹木の間からその光景を見ている
小鳥たちは
やっと眼を覚したところだ
坂多 瑩子 サカタ エイコ
①1945(昭和20)1・28②広島③明治学院大学文学部英文科卒④「青い階段」「ぶらんこのり」⑤『どんなねむりを』夢人館、『スプーンと塩壺』詩学社。
一日
何かの拍子に終らない一日が始まると
夜がきて そのまま朝になっても
私は同じ場所にすわっている
それでもほんの少しずつずれ落ちながら
朝がきて夜になるものだから
私のからだはゆがみはじめ
私のこころはゆがみはじめ
ある日 とうとう
見えないものも
見えるなんて言ってしまうのだ
台所の暗がりで
もういない大伯母が白瓜をつけているとか
それから素知らぬ顔をして 朝
起きると何も起らなかったかのように 昼の
なかに立っている
といってもそう単純でもない
何かの拍子にスプーンとか塩壺とか
見えているものが見えなくなり
裏返しの一日が始まり
台所の暗がりに探しにいく
坂本 つや子 サカモト ツヤコ
①1926(昭和1)12・27②東京③満洲国延吉県朝陽川尋常小学校卒④「すてむ」⑤『にがい誕生』詩学社、『黄土の風』花神社、『焦土の風』『他人の街』『風の大きな耳』『貌のない国』夢人館。
昭和二十年八月六日
ふいに目を刺す閃光 勢いよく扉が開き鼓膜
がたわむ 呉市の海軍港務部が私の職場 舞
いあがる書類 階下の電話の声 誰かが自転
車で坂を下る 広島と呉の間の火薬庫が爆発
したと 私のかわりに広島へ出張した二人の
下士官は丁度広島駅だ 私は見た 巨大なピ
ンクの濃い雲が生きて輝いて広がってゆく
机や床の書類の数字がゆがみ滑った 鼓膜は
干上っていく水の音で満ち 爆風で赤くしび
れていた 戦争は くっきりと敗北へ傾斜し
長い餓えが終ろうとしている合図なのか
美しかった日本の貧しい再出発の為に様々な
死を死んでいった大勢の人 広島の駅は焼け
残った骨で埋っているのか 私のかわりに新
しい出張命令で この坂をおりて行った二人
しんと暑い空が透明な渦巻きになり 生臭く
消えてしまっても帰って来なかった 死んだ
はずの私は ばらばらの書類の真中で 幾度
も死とすれちがって来た十九年 幸せか不幸
せか寂しいだけか 今も二人の背中が見える
坂本 登美 サカモト トミ
①1935(昭和10)1・11②東京③日本大学文学部英文学科卒④「青い花」⑤『坂本登美詩集――花炎断章』芸風書院、『聖獣墓地』書肆青樹社。
愛についてのクロッキー
愛は 厚かましい隣人だ
恥じらうことを知らないくせに
わたし含羞ということばが一番好き などと
愛の仮面をつけて我儘を押しつける
愛は心の燧石だ あなたと私を打ち合わせて
密かに小さな種火を創る
灼けつくような情火の火種か
共犯者として焼かれる火刑の火種か
愛は 生まれたとき既に罅の入った器
満たしても満たしても 満ちることを知らず
したたる愛の哀しみが
夜の雨となって二人の心を濡らす
あなたの背は 神聖なトポス
落陽を浴びて広がる果てし無い原野
形も影もないもの達が描き出す一枚の風景画
見えないもの達の気配がその内景を充たし
一途な恋慕の流れがひとすじ
優しく光りを反射する
坂本 法子 サカモト ノリコ
①1940(昭和15)2・27②広島③広島大学教育学部卒④「穂」「どぅるかまら」⑤『一日のしめくくりの時が好きだ』『水面に浮く影』手帖舎、『白い坂道』西日本法規出版。
二〇〇八年八月六日
サイパンの海は静かで広い
粒の細い黄色の砂浜が続き遠浅だ
浅瀬には黒いナマコがうずくまっている
裸の子等がしぶきをあげている
ダイビング シュノーケリング 水上バイク
水平線にアメリカの軍艦が四隻
威嚇しているようだ
一九四四年六月 午後四時サイレンがなる
ガラパンの街があぶない
飲料水を求めて岩山を登った
頭上をとびかう弾丸
バンザイクリフの崖から海へ
とびこんだ 子供を抱いた母親 女 若者
海に夕日が落ちる
うす闇の中 空は虹色にかわった
焼肉の匂いがしてくる
海の中 ドクロが目をさましダンスをしてる
オー オハ オハ オハ
オー オハ オハ オハ
相良 蒼生夫 サガラ ソフオ
①1936(昭和11)3・21②徳島④「青い花」「新現代詩」⑤『ゑるとのたいわ』『祝祭の供犠』勁草出版、『都市に病む』『羽蟻』書肆青樹社、『都市 思索するペルソナ』銅林社。
硝子質のいさかい
芒の葉群は鋭どい切先をふりかざし
硅素を含む業物で縦横に切り裂く
風が指南の突風流棒ふり剣法に
ときおり子供が入りこみ切られている
この建築予定地は五年このかた空地で
草ぼうぼうの原っぱ 蛇や蟇はいまいが
背丈ほどの叢 妖かしがいてもおかしくない
地主は何回か変り 市街地の優位は変らず
知人が地主となり 貸金のカタで仕方なくと
半端な広さ高層ビルは建たず思案投首のまま
草は生え放題で誰か硝子の混る廃材を捨てた
ある日虫取りの親子が硝子を踏み さあ大変
大怪我に親は空地の管理責任を問い
奴は無断立入を咎める 不法投棄は誰だか
分らず仕舞い 挙句は裁判で硝子の含み針を
傷つけ合う舌戦も奴の敗訴に 憤懣限りなく
――核の閃光も硝子都市の神話は逆光のきら
めきに返して平然と立つ自信の凄さ――と
佐川 亜紀 サガワ アキ
①1954(昭和29)10・10②東京③横浜国立大学教育学部卒④「いのちの籠」⑤『死者を再び孕む夢』詩学社、『返信』『韓国現代詩小論集』土曜美術社出版販売。
押し花
捨てられた夏の押し花
四枚の皮膚が理不尽にはりついたような花弁
火の原罪に幻視された白い花
時を染み込ますことが
時が乾くことと同時であり
めしべの伝言が孤独な花粉のふるえとなる
押し花は
重しと押し返す花の緊張に新しく咲く
押しつぶす文字を飲み込み続け
すべての文字を無効にし
水を与え続けて
すべての文字を生かす
その時 私は重ねられた五〇音字の
一字であり 隠された主語であり
古びた一冊の本である
はがされた花弁は再び悲鳴をあげ
しょう液の跡が思惟の扉のように残る
佐岐 えりぬ サキ エリヌ
①1932(昭和7)12・2②和歌山③パリ大学文学部中退④「火牛」⑤『果実の重み――日仏対訳』水声社、『曽倉てすの独白』思潮社、『れくいえむれくいえむ』書肆山田、『時のいろどり』里文出版。
喪失
わたしの裡を ひかりの矢が 貫き
過ぎ去ったのは いつの頃で あったのか
それから わたしは 盲たまま
手探りで 生きている 失ったものが
何であったのかも 解らぬまま
どれくらいの 時間が経ったのか
計ることも できない
老いた けもの のように
声にならない 咆哮を くり返しているが
誰も気付かない わたし自身ですら
暗い 重い 闇に 閉ざされ
理性も感情も 失ったまま それでも
生命は保たれていて 確実に来るものに
ひたすら 耐えているのか 待っているのか
わたしに 近付いてくるのは 死者たちの
ほほえみと にぎやかな 話声 笑い声
この世からも 取り残された わたしには
死者たちと 呼び交す 他はないのだ