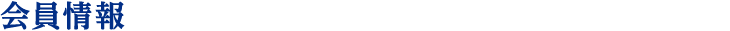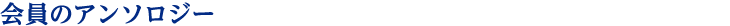会員のアンソロジー16・寺田弘氏~
寺田 弘 テラダ ヒロシ
①1914(大正3)4・29②福島③明治大学専門部卒④「虎座」「独楽」⑤『故園の書』白鳳社、『勲章について』国文社、『手首の社』宝文館出版、『三虎飛天』書肆青樹社、『寺田弘詩集』土曜美術社出版販売。
生理
煙草の吸口を嚙みしめながら ぼそぼそと話
してくれた ぼそぼそと「詩とは何か」を
語ってくれた 体が緊張で凍りついた
―詩とは感情の神経を摑んだものである―
昭和八年八月 私の出していた「北方詩人」
詩話会に湖の風が光っていた「気紛れに 気
楽に勝手に書く個人誌を出した 一冊あげよ
う―」どきりとした 表紙には人体生理之図
という腑分けのエッチング 血のような朱色
で「生理」と書いてあった
見たこともない大人の詩誌 生理という生々
しい文字も少年の頭を攬乱した 内臓や 肺
臓や 肝臓や 神経や ぐちゃぐちゃの複雑
な生理の中から ぐちゃぐちゃに嚙みながら
吸う煙草の煙から 吐き出される詩の怖さ
言葉の刃に言葉を失った 言葉の奥に溜息が
溜った 怖い眼が表紙から立ちあがった
萩原朔太郎個人詩誌「生理」
十八歳の思い出である。
寺田 美由記 テラダ ミユキ
①1955(昭和30)10・12②新潟③人間総合科学大学人間科学科卒④「布」⑤『二〇〇〇年の切符』『かんごかてい(看護過程)』詩学社、『CONTACT(関係)』思潮社。
解答
これはわたしの問題で管理の話ではないと
呼び出された喫茶店で彼女は語る
個人の問題であるといえばいえる
全体の問題であるといえばいえる
境界はわたしにもわからない
個人の問題をうやむやにすることで
全体を見えずらくしてきた
いや個人のことは少しわかるけど
全体のことはわからないだったか
フリルの胸元から透明な肌がのぞいて
悩めるあなたは美しいけど
わからないことはわからないこととして
わたしたちに必要なのは
ほんの少しやさしいまなざし温かなことば
生きることはひとつひとつ
あきらめていく過程
あの時のこれが本当だったと
ずっと後になってからわかる
遠山 信男 トオヤマ ノブオ
①1921(大正10)10・1②岩手③アテネ・フランセ中退④「岩礁」⑤『匿名の焰』饗宴詩社、『樹木の酒』『釜石風景論』青磁社、『詩の暗誦について』日本図書刊行会。
闇をみめていると
闇をみつめていると
見えない気韻のかおりともなる
カレードスコープの夜の
造形される眠りのやすらぎの文体を見ること
ができる
するとそのとき
言葉はやさしくもためらいのなかの夢見心地
からのように
スパイラルに石への思いの構造となって
潜在意識へと奥深く下降してゆくのだ
ああやはりね
と
「自分」をいたわることができるからこその
エラン- ヴィタルなもの〈生への飛躍〉と
して限りなく
と
おお「未知の明日」はいつも闇の力のゆえに
ともいわれているので あるときはまた
と
その夜の呼吸の祝祭がみつめられる__
冨上 芳秀 トカミ ヨシヒデ
①1948(昭和23)6・2②和歌山③和歌山大学教育学部卒④「詩遊」⑤『アジアの青いアネモネ』『言霊料理』詩遊社、『安西冬衛』未来社。
ウルトラマン
時間がないと言って
男はいつもどこかに消えた
遠い宇宙の果てに秘密の家があって
疲れた男が一人でお湯を沸かして
インスタントラーメンなどを食べている
庭のプランターに植えた青ねぎを
一筋採ってきて
爼板の上で刻む
そこだけが生臭く命で?がっていて
こんな星降る寒い夜にも耐えられる
そこは誰も知らない
男だけの暗い場所だった
時里 二郎 トキサト ジロウ
①1952(昭和27)11・12②兵庫③同志社大学文学部卒④「歴程」⑤『胚種譚』『採訪記』湯川書房、『星痕を巡る七つの異文』書肆山田、『ジパング』思潮社、『翅の伝記』書肆山田。
抽 斗
もう記憶の中でしか聞くことのできない音
がある 父の愛用していた小ぶりの箪笥で抽
斗を引くとオルガンのような音がした アラ
ラギに歌を寄せる市井の歌詠みだった父が歌
稿の束を入れていた抽斗
歌になる前の七音や五音に消化しきれない
言葉が 抹消され訂正され書き継がれ 累々
と紙片を埋めていた
「もの言はぬ日がしばらくつづいた
ひた曇る空のさびしさ
われといふさびしさ」
ぼくとの軋轢の日々に漏らした父の息づか
いが思い出されて その歌稿の一葉は ぼく
の抽斗の奥にしまってある
ぼくの抽斗はオルガンのような音はしない
が 春深く 穀雨の空の湿りをふくんで 言
葉のない父の歌がふとそこから聞こえてくる
ことがある
徳岡 久生 トクオカ クミ
①1932(昭和7)8・3②長崎③広島大学文学部国文学科卒④「左岸」⑤『弦』詩学社、『私語辞典』『相聞』思潮社。
伝言
ないのだ
水にかく言葉も
砂にかく絵も
わたくしには
だから
いっぽんの指を
空に浸して
ちいさな輪をふたつ
風のなかに描いてみよう
きみへの
あなたへの
便りに代えて
届かなくてもいいから
徳沢 愛子 トクザワ アイコ
①1939(昭和14)1・29②石川④詩と詩論「笛」・個人詩誌「日日草」・童詩「こだま」⑤『みんみん日日』書肆青樹社、金沢方言詩集『ほんなら おゆるっしゅ』北国新聞社。
桃太郎さん(金沢方言短詩)
わてらの昔はよう働いた 子守り炊事掃除
川へ洗濯桃太郎さんの話みたいやろ わてに
も現われたのやろか 玉のような桃太郎さん
どなたさんですけ? 母 異邦人となる冬茜
沈黙の後ろに立つ猫背の寂寥
わては一本の樹になりたい 一日喋らず
空仰いで 風の言うがまま小鳥の群れるまま
一本の慈悲になりたいがです
たゆとう柳の蒼い手 老犬たるく振る尾っぽ
てきないわての魂を撫でる神の時刻
溜息洩れる日記つけ 今日一日の荷下ろいて
〝らっちゃかんなァ〟と呟く夜さりの吐息
その長い温とさ
おいその方やと思うとったけど こんなけ近
くに さぶい顔した寂寞がいたとは
慌てかやる丑三つ時 寝返りふたつみっつ
徳弘 康代 トクヒロ ヤスヨ
①1960(昭和35)3・3②高知③早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程修了・博士(日本語教育学)⑤『音をたてる粒子』ナヴェラ舎、『横浜⇔上海』夢人館、『ライブレッドの重さについて』詩学社。
予兆
その魚の色は
少し緑のまじった青で
透明なので光を通す
光の中を泳ぐと
青い光が暗いところを照らす
さっきため息をつく人のよこを
魚が泳いでぬけていった
ねたみと嫉妬で電話をきれない
たっぷりの電波のなかも
その魚は泳いでいった
泣く子ども そして
もう泣けない子どものよこを
下落の下を きりすてられた
可能性のとなりを
身動きのとれない人々のなかを
何かやわらかいものが とおっていった
目をとじると
まぶたのうらに
青い光がのこっている
登坂 雅志 トサカ マサシ
①1946(昭和21)4・28②茨城③東京都立大学人文学部フランス文学科卒⑤『わが頭蓋が珊瑚と見紛うまでに』思潮社、『大地に花ばなを』彌生書房、『四季余滴』花神社。
ふたたびの春
灰色の銅版の空に
腐食された木の黒い線刻
暦では春たけなわというのに大雪に見舞われ
ごうごうと唸る風にもどっしりと立っている
樹齢数百年の桷(ずみ)の大樹が
標高千七百メートルの風景を見まもっている
胴回り三メートル余りの灰色の幹は洞をいく
つも抱え
細い枝は不器用に数かずの空をかたどってい
る
あなたは大伽藍であり
流れる緑の大河であり
ヘンデル ブルックナーである
今日 樹形が滲み 小枝は朱を帯びている
数ヶ月すれば ほのかに淡紅色をふくんだ白
い小花が
ぶんぶんと蜂や虫をうならせ 匂いたつこと
だろう
鳥巣 郁美 トス イクミ
①1930(昭和5)2・2②広島③広島女高師理科卒⑤『春の容器』天秤発行所、『埴輪の目』『冬芽』編集工房ノア。
晩夏の風
そこはかとない風の運ぶ
闇を埋める弾みのいくつか
姿なすさまざまが通り過ぎてゆく
生を享けて時経たぬ幼な子の微笑み
一隅にそよぐ雑草のひと群れ
腕のばし汗拭う若者の肌
むせ返る程の秘めもった息吹を
未だとりまく暑気に重ねて
晩夏がとっぷりと暮れる
踏みしだいて歩んだ幾星霜の
来し方を凝視めるような
引き締まる顔のいくつか
一隅で饗けもった精知を
顕われ漲る姿態を
日暮れに居残ってささやくものがある
みずからの闇を脱け出てひたひたと寄せる
更になお引き積む生の余情の
弾ける諸々が姿なして浮き上がってくる
戸塚 礼次 トツカ レイジ
①1931(昭和6)4・14②静岡③静岡大学卒⑤『ブロッケン山と猫』土曜美術社出版販売、『街のカラスとネオン管』私家版。
後期高齢者
勤めていた頃
目覚めたばかりの昏い空に
朝はもう
ネクタイ締めて玄関に立っていた
やがて太陽が
鋭く切り立った天の階段を
駆け足で登っていった
一日はバタバタ過ぎていって
気づくと昼は夜になっていた
いまは夕暮れというものがあって
天のラセン階段をゆっくり降りてくる
西の空に
今日やり残したことを少し残して
そうだ 明日の朝
ぼくはきみに おはよう と言おう
ふたりとも まだ若いのだから
殿岡 秀秋 トノオカ ヒデアキ
①1949(昭和24)10・16②東京③東洋大学文学部仏教学科卒④「gu i」⑤『鍵穴の海』『眼底都市』銀曜日、『余生号の叛乱』秀文社、『かけらの夢』『水の底』『人体交響楽』『パリ発東京行きのメトロ』あざみ書房。
指の間の歴史
左足の小指と薬指の間に紅い蕾
昨日と今日との間に開花した
肉に根を張り
血を養分にして
唇色の花を開く
乾燥した足の大地は
葉脈のようにひび割れているのに
そこだけ露が震えている
幼い日のアカギレは
今も薄い血を滲ませて
脳裏にふさがらないままだ
そのころは明日がくるのが遠く感じられ
傷が癒えることすら信じられなかった
花が開くには
ささやかでも歴史があるはずだ
壊さないように
そっと小指と薬指の間を広げる
ぼくに語りかけようとする花びらに
薄く軟膏を塗る__
富沢 智 トミザワ サトル
①1951(昭和26)3・3②群馬④「水の呪文」⑤『藁の戦車』ふらんす堂、『水辺の机』砂子屋書房、『あむんばぎりす』榛名まほろば出版。
幽霊船
あたいの頭のなかには海があるの
煙草をひっきりなしに吸いながら
その海でのことを彼女は話した
泊まっていたホテルがそのまま
出航したの
見渡す限りの海原でさあ
でも何かへんなの
全てが既に終わっているような
夕日に向かって
音もなく
この巨大な船は進んでいるのだと
あたいは何故か知っているの
もちろんこの船の乗組員の
誰ともすれ違うことのないことも
海鳥は人の顔をしていて
寄ってくるのはあたいを知っている鳥
だから
カーテンを大急ぎで閉めましょう
富田 正一 トミタ ショウイチ
①1927(昭和2)3・30②北海道③陸軍航空通信学校卒④「青芽」⑤『天塩川』『流れ雲』『秋日』『風よ雲よ樹々たちよ』『夕焼けの家』『名寄地方詩史』『あの日あの顔』青い芽文芸社、『あばしりからのたより』オホーツク書房。
コスモス
あの日
小さな駅ホームのベンチに
寄り添うように
咲いていたコスモス
今は 誰もいない
ホームの片隅で
コスモスに語りかける
秋風
あの戦いが
すべてを 奪って行ったのだ
足早に通り過ぎていく
雲
残された コスモス一輪
言葉もなく
頭を揺らしている
冨長 覚梁 トミナガ カクリョウ
①1934(昭和9)②岐阜③岐阜大学学芸部国文学科卒④「撃竹」「存在」「山繭」⑤『庭・深む』花神社、『そして秘儀そして』れんげ草舎。
死者の顔
この冬 涸れていた川に水がにわかに
たっぷりと流れ その川に一つの死者の顔が
生きているものを 見舞って浮んでいる
生きている誰れもが現したことのない
優しさが 流れの中で純潔な乳房のように
ふっくらと微笑んでいる
死者の顔は 枯れ草の岸にぶつかって
傷ついても もとの優しさにもどっていく
冬のこの寒さに ふくよかに流れていく
この死者の顔は
あなたの貧しい一日の隙間を
母の乳のぬくもりで 純白に充している
あなたが岸辺に佇んで 掌を合わす以前に
すでにさざなみの波頭にすえて
あなたを拝んでいる 死者の顔
あなたの転生の宴のあかりが
この冬の闇の岸辺に ぼおうと点っている__
富永 たか子 トミナガ タカコ
①1934(昭和9)4・25②福岡③短大卒④「山脈」「新現代詩」⑤『シルクハツトをかぶった河童』飛天詩社、『月が歩く』待望社。
ほろほろ と
深山の霊気を吸うただ一本の桜花
さびしさに花咲きぬめり山桜
蕪村の句そのままに
さびしさに堪えかねて
自分のからだに花を咲かせた
花を咲かせて自ら華やいでみる山の四月
美しいものは不安だ
見られることを怖れるのではない
身を竦め 声を殺して 怯えるのは
ひかりと影とを打つ
気まぐれなあの渦巻く風のあること
花の命は人の生との時間に見合う瞬時だ
そんな問を背負って有為転変の行路を辿る
山桜の舞台だ
いっときを照らす山の灯だ
今年も咲いた
あの山の同じ場所に
豊岡 史朗 トヨオカ シロウ
①1951(昭和26)9・13②東京③慶応義塾志木高校卒④第3次「同時代」⑤『虹を渡った男の話』詩学社、『サラマンカのオリーヴ』火箭の会、『拙生園』舷燈社。
お彼岸
庭にキジバトが舞いおりた
餌をさがすでもなく
敷石の上にとまって
じっとこちらをみつめている
警戒するようすもなく
やさしいおだやかな顔をして
しずかに日差しを浴びている
わたしにはすぐわかった
しばらくの間まなざしでかたる
やがてキジバトは意を決したかのように
さっと空へ飛び立った
あとにはあたたかい日溜まりがあるだけ
母がキジバトのすがたをして
そっとわたしに会いにきたのだ
豊原 清明 トヨハラ キヨアキ
①1977(昭和52)6・25②兵庫③青雲高校卒④「火曜日」「現代詩神戸」「SPACE」⑤『夜の人工の木』青土社、『朝と昼のてんまつ』編集工房ノア、『時間の草』ふたば工房。
家族と水枕
私は毎年 夏になると
てってい的に冷やした水枕に
坊主頭をくっつけて
びしゃっと少ない髪を濡らすのが趣味だった
しかし 私は三十過ぎた
常識がないと言われ
挙句の果て
くやしい思いで三十一歳を迎えた
キリストの香りのような
初夏の雨
今はもう八月の終わり
父は毎日水枕をタオルに包み
くすりと共に 夜 持ってくる
奥歯の痛みに
この世の終わりを身に覚え
父は『聖書』をよみつつ
ペンをもつ 私もペンをもつ
もう水枕は極度につめたくない
外では法師?が最後の声を挙げている
内藤 紀久枝 ナイトウ キクエ
①1939(昭和14)1・15②茨城③水戸第二高校卒④「青い花」⑤『戯雨』国文社、『たけにぐさ』書肆青樹社。
アリス
アリス あなたはわたしを知らない
アリス わたしはあなたを知らない
それなのに わたしの足を引きとめて
離さない あなたは誰?
スカンジナビア半島一千年の遺跡の町
シグチューナの人を呼び止めるには
あまりにも小さい墓標 花束に埋もれて
あなたは眠る すでに遺跡の一部となって
一九二七―一九九五年 墓標に記された
わたしの生とわずかにずれて並んだ数字が
しきりに告げてくる人の生のタイムリミット
肌の色の違う子をわが子として抱きしめ
頰ずりを繰り返す多くのアリスに出会うたび
畏れ羞じて立ち止まったわたし
メーラレン湖に秋風を立たせて
北緯60度の町は億の日を刻みながら
鈍い光芒を放ち今日をゆっくりと自転する
アリス わたしもまたけして立止まることを
許されない 東洋のひとりの女である
直鳥 順子 ナオトリ ジュンコ
①1940(昭和15)4・4②香川③観音寺第一高校卒⑤『剝製の鳥』『漂う時計』詩学社。
樹に埋もれて
緑の雫の中で目覚める 揺れる葉蔭で
三階の窓をゆうに越える のっぽの
メタセコイアは病室のすぐ前にあった
早朝には野鳥に枝を広げ
夜は流星の宿り木になって
走ってきた青年にぶつかって転倒 骨折
がっくりしている私に樹は語りかけてくる
風が運んでくる遠い海の響き
鳥のお喋り 早春の花の色
深夜 樹蔭に私を隠して 眠る街を行き
若草の香る野を渡る 軽やかに
人の夢をやさしく撫で 翔び上がる
天の川まで 銀や青の魚の煌めき
樹に埋もれて三週間 今朝鳥が飛び立ち
私も旅立つ 樹の雫 溢れる内湖を抱いて
窓に映る私の眼は 今日
初夏の眩しい緑だ
那珂 太郎 ナカ タロウ
①1922(大正11)1・23②福岡③東京帝国大学文学部卒④「歴程」俳誌「雹」⑤『音楽』思潮社、『はかた』『空我山房日乗其他』青土社、『幽明過客抄』『鎮魂歌』随想集『木洩れ日抄』小沢書店、(詩作品に近作無く、代りに新旧とり交ぜて俳句作品を次に記します。)
この世いつ果つとも知らね初茜
花吹雪このひとときも散りゆくか
春暁やまばたくまつげ頰にふるる
鰯雲 累累つらなる墓標とも
たましひの骸骨が舞ふ月冴えて
老骨のおきどころなし後の月
見るかぎり牛蒡の色の冬木立
まぼろしの枯野かけ去る鼠かな
炭つぐや骨拾ふ手のしぐさにて
水仙花死者ひつそりと通り過ぐ
亡き友の幾たり訪ひ来去年今年
ワレ白骨樹 気根モテ着生シ自ラ更新セン
中井 ひさ子 ナカイ ヒサコ
①1941(昭和16)4・3②奈良④「ぶらんこのり」⑤『ドント・タッチ・ミイ』飛天詩社、『動物記』土曜美術社出版販売。
異国
饒舌な空の青さに
とまどう
忘れ物をしたように
振り返った坂道
細い路地を曲がると 石畳を
陶器のトカゲが 歩いている
石と陶器のふれあう音が
心地良く足に伝わる
驚かさないように すれ違う
好き好きに傾き
少し難しげな顔をした家々
二階の鉄格子の付いたベランダには
無口な洗濯物がぶら下っている
思い出したように
鐘の音が
ポケットに小さく折りたたんだ
一日を通りぬけていく
長尾 まり子 ナガオ マリコ
①1929(昭和4)3・31②青森③日本女子大学生活芸術科卒⑤『まりも』日本詩人社、『歴史』昭森社、『花になりたい』長尾美術研究所。
花になりたい
「五月には花になりたい」
遠く離れたケアセンターからの母のたよりに
八十五歳の生涯をぐいとつきつけられる
花になったら気軽だろうと 枕辺の花を見て
は 一枚ずつ人間のしがらみを脱いでいく
身体と心の痛みを
誰も取り去ってはあげられなかった
五月の北国の空は晴々として郭公も鳴く
鷹揚城の桜だって葉桜になる
貴女は紫の袴をつけた少女に還り ローレラ
イを口ずさみながら
桜トンネルの道を散歩するのでしょう
六月には三十歳の夫が戦病死し十二歳の長女
が逝った時だ だから貴女は短い花の命で
五月の精霊となるべく羽化を急ぐのでしょう
花になり鳥になって人は昇天するが
次の出逢いはどんなめぐり合わせだろうか
花になりたいというせつなさに
私が届けられるのは
花屋にはない 庭に咲く雪割草か
中岡 淳一 ナカオカ ジュンイチ
①1937(昭和12)11・15②三重③東海中学卒④「三重詩人」「沈黙」⑤『メガロポリスの遺跡』三重詩話会、『天空へ上がる階段』風濤社、『宙家族』書肆青樹社。
生の比重
幾重もの地の層を潜り抜けてきた水勢が
コップに移されてなお僅かに揺らいでいる。
西方ではヒンドゥー教徒が岸辺を埋めて
日の出を待って流れに躯を沈める神への祈り
は
聖なるガンジスの濁った水を口に含ませる
河に沿ったバラナシ まちなみの一画の住処
で
昨日まで時間と向き合って躯に水を漲らせて
いた男の
遺体はいま、燃えさかる炎で焼かれ一握りの
骨灰となり
遺族は魂の昇天を信じて流れに撒き散らす
コップの水を注ぎこむように飲んで
きっちり二〇〇グラム増えて
わたしは少し水に近づく
中神 英子 ナカガミ エイコ
①1956(昭和31)3・23②岐阜③東海女子短期大学卒④「楽市」「花野」⑤『家を出てから』『約束』『ファンタジア』思潮社、『悪戯』朱鳥社。
雲のうた
私たちのためらいは静かだ
井戸の底のゆらめきを
射し込むわずかな陽光をたよって
覗き込んで見ているのに似ている
背後に無限の空がある
静かなためらいの内に私たちは
浮く雲の来し方行く未などおもっている
ほんとうのことは知らない
ただ、知らないものについてのうたを
花だの夢だのに託して歌うのは得意のようだ
外はいつもさみしく賑わっている
降り注ぐさまざまな音、音、音
さそわれて山に登れば
山頂から見える町は
気のせいか雲と同様に
遠くへ遠くへかたちを変えて
その底の何かを探しゆくように見える
中川 悦子 ナカガワ エツコ
①1930(昭和5)5・1②北海道③室蘭高女卒④「野火」「情緒」「パンと薔薇」「核」⑤『木片』私家版、『雪の貌』みやま書房、『北の四季』北海タイムス社、『冬の鳥』花神社。
水のいとなみ
近くの川べりを歩くのがすきだ
新雪のまぶしい朝 川辺は白い野におおわれ
人ひとり 犬いっぴきの
ふかぶかとした足あとが川へ消えている
そのくぼみに足を入れると
生ける水の蒼い映像は
人のいとなみのすべてを浮かべ
街道の騒音も 波形にきざまれ―
年明けに姿をみせる一羽のオオハクチョウに
ことし また逢えるだろうか
カゥ、カゥ、と声をまねれば
川面を切って一直線に現れる
神のようなあの白い鳥に
―カメラをのぞくわたしの影が
のびて 雪面をけずり
まだ凍らない水流をうかがい
揺らめくものに逆らって思案している
たれかのもとにかえろうとして
中桐 美和子 ナカギリ ミワコ
①1931(昭和6)5・23②岡山③岡山大学教育学部卒④「火片」⑤『真昼のレクイエム』土曜美術社、『燦・さんと』書肆青樹社、『中桐美和子詩集』和光出版。
詩
詩は 石である 声をたてない石である
詩は とめどない涙である 塩辛い涙である
詩は 愛である それは錯覚に似ている
詩は 死である 両手を広げて待っている
詩は こぶしをにぎりしめる闘いである
詩は ひとと流れていくさすらいである
詩は 歴史である 点を太い線にしてしまう
詩は 微笑である モナリザの微笑である
詩は 明日への夕景である 朱い道
詩は 情炎である 男と女の物語である
詩は 燃えがらである 背中のない会話
詩は 嫌な自分を棄てるところである
詩は 遺言である 全てをあげる所である
詩は 合わすグラスの中で光る
詩は 帰ってくる故里である
詩は 果てしない空であり 底のない海
詩は わたしを拒む山である
詩は むずかしくて もどかしくて
詩は 奔流のるつぼである 命を削るるつぼ
である
本当の詩は言葉がいらないのかもしれない
長久保 鐘多 ナガクボ ショウタ
①1943(昭和18)7・18②福島③東京教育大学文学部哲学科卒④「龍」「詩季」⑤『散文詩集・象形文字』私家版、『二十世紀、のような時代』詩学社、『二十世紀と二十一世紀の間に』詩季の会。
赤い夜
慣れない宿のせいか
夜中に目が覚めてしまった
部屋が妙に明るいのだ
夢の続きがここまで追いかけて来たか
〈お店の看板は消して来たよね。
〈あなたが点けて、わたしが消したわ。
路地奥の漂う船のように
部屋はぼんやりと赤いのだ
〈これは、火事かも知れないぞ。
〈いいわ、このまま燃えてしまっても。
誰もまだ気付かないのだろうか
辺りはまったく静かなままだ
闇に慣れた目に部屋の空気までが赤く見える
〈やっと辿り着いた島なのに……
そう思いながら窓を開けると
庭一面に五月躑躅の花が咲いていて
それらが月の光で海を成しているではないか
〈本当に燃えている波のようね。
一緒に庭に出ると
夜はますます赤く広がり
二人を一つに溶かし始めるようであった
中崎 一夫 ナカザキ カズオ
①1931(昭和6)3・4②群馬③東京大学大学院修了④「仮象」⑤『鳥獣戯画その他』『ヴイジョンズその他』『視差その他』『幻化その他』『歳彩』、立体詩画集『鳥獣戯画』私家版。
無題
どこまで歩くと
歩行は
旅になるのか
どこまで深くなると
沈黙は
祈りになるのか
どこまで生きると
生は
生になるのか
中島 悦子 ナカシマ エツコ
①1961(昭和36)8・22②福井③横浜国立大学大学院教育学研究科言語文化系修了④「木立ち」⑤『Orange 』土曜美術社出版販売、『バンコ・マラガ』紫陽社、『マッチ売りの偽書』思潮社。
甘栗
「物語」を信じなくなって数年。甘栗売りと
して路上に立っている。甘栗を焼く焼けた小
石の渦巻を見るのが一日の仕事。栗は不確実
な小惑星のようにぐるぐると磨かれ、地獄の
ようなかたまりとなって、どれも一日を数秒
で終え、何万年かをかきまわす。
かつての「甘栗の使」は死に絶え、今は私ひ
とり。貴重な甘栗の物語は黒こげになり、今
は釜ひとつ。夜十時には店をたたむ。酔っぱ
らいが「物語」のかけらをあれこれ投げつけ
てくるが、決して親身にはならず、大臣の物
乞いを許さず、釜の番をする。
どのような惑星も最後には滅んで、ここにこ
の栗だけがまわっていると思って。