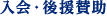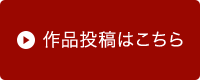日本現代詩人会 詩投稿作品 第35期(2024年10月―12月)入選作・佳作・選評発表!!
厳正なる選考の結果、入選作は以下のように決定いたしました。
■うるし山 千尋選
【入選】
水町文美「模写」
むきむきあかちゃん「私がネアンデールタール人であったなら」
佐田征優「原型詩の試み1:風について」
三刀月ユキ「ぼっき」
こやけまめ「うつくしいものがしつこい」
【佳作】
奥村紘「雨」
三明十種「葛の葉」
小海真「もろもろのひとこぞりて」
未補「CHOKE」
金固歩見「伝統芸能の挑戦」
■浜江順子選
【入選】
三刀月ユキ「マーメイドペイン」
熊倉ミハイ「げんにぬりぬり」
こやけまめ「うつくしいものがしつこい」
未来の味蕾「点滅するネオンサイン」
大庭颯隼「翳らない部屋」
【佳作】
宮本誠一「トライトーン」
柿沼オヘロ「藤棚」
古森もの「記憶は白い」
メンデルソン三保「たくあんの人」
阿呆木種「Romance」
■雪柳あうこ選
【入選】
緒方水花里「ターミナル」
佐々木春「ホイール」
長澤沙也加「振り返らないアパートで」
むきむきあかちゃん「マンダリン」
安藤慶一「海月」
【佳作】
熊倉ミハイ「げんにぬりぬり」
三刀月ユキ「ぼっき」
泉水雄矢「布団が吹っ飛んだ」
関根健人「葬葬」
早乙女ボブ「二十一歳」
柴田爽矢「恋は茄子」
【選外佳作】
遠野一彦「ひかり」
雪水雪枝「からめる」
メンデルソン三保「キティちゃんと核爆弾」
佐藤百々子「nuit de verre」
吉岡幸一「死んでいる米田さん」
投稿数676 投稿者370
僅かに欠けてしまった
小さな部品は
小さな欠陥を生み出しながら
傍目からはいつもと変わらぬ運行を続けている
細く開いた隙間は
足を踏み外すまでではないにしろ
僅かに浮わついて
内臓を揺らす
それは聞き取れない語尾であったり
場にそぐわない剥き出しの笑いであったり
ちょっとした目眩であったりもするのだが
何しろ鈍感な連中には
気付かれないものであるので
ひとり意識を
意識の尻尾を
細い迷路に迷わせて
居心地が悪い
帰り道は分かっている
けれども家は
知らない人がなぞったような
太くて妙な輪郭をしている
もし私がネアンデルタール人であったなら
大きな産声をあげて生まれただろう
誰かが焚いた火花が散っていただろう
寒空の下 母が私に微笑んだだろう
もし私がネアンデルタール人であったなら
風の声を聞いただろう
風の声に応えただろう
でもいつか風は 大きくなった私に
何も教えてくれなくなるだろう
もし私がネアンデルタール人であったなら
恋をしただろう
相手はクロマニョン人かもしれない
けどきっと振られたのだろう
泣いているのだろう
もし私がネアンデルタール人であったなら
何も成さないのだろう
何も成さぬまま 誰かが死ぬだろう
誰かが死んだということ
私が死ぬということの
意味を考えて夜を明かすだろう
もし私がネアンデルタール人であったなら
やがてとしを取るだろう
昔より少し暖かくなったようだ
暖かいと眠くなってきて
何も成せなかったことを思いながら
首のしこりを思い出しながら
それでも何故か満ち足りたような気分で
青空を眺めながら
死んだのだろう
男、冷える日の午後に自転車を漕いでいると、肌をかすめて風が向こうへとゆきすぎた。風を受けると、男の精確な大脳辺縁系の機能により、ヨハネ伝三章六節のフレーズが起動した。
「風は自分の好むところに吹く。
あなたはその声を聞いても、
それが何処から来て何処へゆくかを知らない。
すべて霊から生れたものはこのようである。」
男は七日前から、根本的には遥かに前から、近代的人類に普遍的なむなしさに心を浸していたが、風を受けて、ヨハネ伝三章六節を口に漏らして、それは瞬きを待つ間もなく寛解した。風は自分の好むところに吹く、そのことを感覚してしまった男はもはや男ではなく、詩人であった。己を拘禁する肉体の独房はもはや男の関与するところではなく、男は男の好むところに吹くことができた。風であった。詩であった。こうして男は詩人になった。
脚のひとふみごとに車輪は回る、ママチャリは直進するが、車輪は同じところをぐるぐると回る。クロートー、ラケシス、アトロポス、三人の女が紡ぎ車を回している、そうして運命の糸を紡いでいく、男は自転車を漕いでいる、回る、回る、ぐるぐる回る。時間は回り、環をなして、男の車輪は詩を紡ぐ。
西暦三〇年のエルサレムの臆病なユダヤ人議員の肌をかすめた風が今、二千年の時を挟んで詩人の頬をかすめる。詩人は夕の風のなかをママチャリで走った。ママチャリのまっすぐな時間とその車輪のめくるめく時間が同居して、世界は推進する。宇宙はふくらむ。二〇二三年、谷川俊太郎が「二十億光年の孤独」を上梓してから七十一年が経過していた。
三歳の息子
やわらかなはだかんちんで
おフロ場に立ち
ぼっき している
せいぜい 大人の親指のさきくらいの
ぽっこりした 小さな
みずみずしい球根のような
まるっこく すべらかなものが
せいいっぱい しゃちほこばって
といって 背のびにもならず
ぷっくりとふくらんで
かたく もちあがっている
なぜ ぼっき したのか
誰もしらない 本人も
まんまるなあごを傾けて
いぶかしそうに みているばかり
なんなら ママのおなかの中でも
ときどき ぼっき してたんだって……
でも 気づくのははじめて
こんなん ぼっき ちゃうわい
海綿体の体操やがな
と おもうけれど いとしい
こんなに あいくるしい まだ
抱っこもオムツも てばなせない頃から
からだというものは 生きて
かんがえているのだ 来たるべき時のことを
ほどけない歴史の螺旋と
こっけいなまでに真面目に首っぴきして
準備しているのだ 実行しているのだ
待っているのだ 例え無駄になってしまったとしても
飽きることなく 諦めることなく
たゆまず 黙って ていねいに 正しく
命 わたしたちが切ったり張ったりだの
掛けたり捨てたり削ったり投げうったりと
やりたい放題のことにお構いなどなく
幼いくりくりの体 じゃじゃーんとぼっき
命の誠実さは
こんなにもおかしく 微笑ましい
生きること 生かすこと 願うこと
そのためにできることは すべてすること
いつか 誰かと命を交わし ひとつにして
新しい螺旋の律動を産もうという 日がきたら
愛の名を唱えて
思いっきり 祝福のらっぱを 吹くために
今は 蜜をたくわえる花の準備
すくっと立つための 幹の準備
揺れも雨も吸い込む 根の準備
その人の傘になるための 葉の準備
95センチの白い体が ぷるりと震え
湯船に飛びこんだ
ああ 花火
てのひらに キスをしてやる
その時にはどうか その誰かにとって
世界で一番やさしい人であれよ
十二月に飽きて
春をしゃぶっている
記憶の中で造花にしたはずの桜は腐っている
もう会いたくない人たちも次々に腐っていく
このからだは私のものではない、なら
記憶もからだと同じように新陳代謝して
私から離れて
誰かに受け継がれているはずだ
ことばにしなくても
人は、地球の物質は、繋がりすぎた
過去を冷凍保存できるほどタフじゃない
春という
古くなって味もしない廃れた
健康に悪い記憶をしゃぶって
忘れていたい
よろこびにも疲れてしまった
涙とは縁を切りたい
青空を見て溜息をつきたくない
私はいつもそれらに監視されている
こんなに月が真っ青な未明は
波打ち際でうずくまるあなたの痛みが
波動になって肌へと打ち寄せる
どっ どっ 血管打つ
ぐうううーん うぁぁあーん
痛みは人が慣れることのない神経系
あなたの痛みはずっとあなたのそばにいて
嘘をつくことを知らない
あなたのそばにいて裏切ることなく
あなたを見つめて命を刻み
逃れられない魂の鎖となる
あなたの柔らかい肉体の奥深く
銀の針で深く挿し込まれた鋭い欠片
よってたかって打ち込まれた色々な刃物
食らった時は一発だと思ったのに
体内で破裂し無数の傷が骨食い破る弾
これほどの痛みの中では
人の感情も意味のあることばもその出口を塞いで
ただ痛み続ける磔刑のその叫び声だけがひびいている
無言の苦しみの中で
心臓に腹に真珠を育て続けるあなたよ
全ての真珠は人魚の涙 人魚の骸から取り出される痛みの結晶
核になる異物を挿入される真珠貝が
どれほど痛いかを人々は知るだろうか
あなただけがその痛みを知っている
伝えなければならない本当のことも苦しみも愛しさも
語ることのできない沈黙をことばにならぬ声にならぬ痛みを
マーメイドペインを耐えつづけるあなたよ
痛みから少しでも逃れる術を探し四苦八苦し
試行錯誤しやがて堆積した 真球体の あるいは歪な白い光を
人は真珠と呼ぶのだ
あなたの命が分泌する皮肉なほど美しい光の涙
どっ どっ ぐっ 呼吸 鼓動 捩じ切る
うぁ うぁぁー うぁぁあーん
ただ待てばその光を奴らが持っていく
あなたに針を差し込み 痛みの核をねじ込み
殻に閉じ込めた奴らがしたり顔で持っていく
あなたの苦しみを首狩の獲物のように飾るだろう
海の深さと海の底の真実とを知る
あなたのマーメイド・ペインを
感情と表現の分裂するその前の青い未明
わたしたちは沈黙の波打ち際で
ずっと聴いている ふるえながら
少しだけ似ている痛みの欠片を抱えて耳を済ませば
ねじくれた巻貝のような器官ひとつ
ここにあって泡の破裂を聴く
わたしたちは今日 そうして最も古い耳を持つ
街も山も重度の難聴で
涙の落ちる音も聴こえないというのなら
どっ どっ 血管 打つこの血液を
今夜もインクに変えて記すのだ
にんげんに
バターぬりぬり
背骨の切り込み線に沿って
おしりの溝まで
ていねいにぬりぬり
コンベアの先のかまどで
てりてり
にんげんに
バターぬりぬり
ひるがえってぽっかり
おなかを見せるにんげんは
足首をもってひねり
バターぬりぬり
にんげんに
いしきがあるなら ちょん
ナイフでちょんと 切りさいて
すてすて
だから床もてりてり
ゆうれいに
バターぬりぬりは
むりむり
かまどで焦げた
にんげんを食べてもらう
もりもり
へいたいに
バターぬりぬり
ジャムも
どまんなかにぬりぬり
すぐさま軍服着てもらい
工場の外にそのままブイ
同僚に
ゾンビみたいだなと言われた
私のからだはすべてバター
うるさいなあ ったく
同僚に
バターぬりぬりぬり
どんな味かは知るよしもなく
かまどの裏も知るよしもなく
今日も今日とてバターぬりぬりぬり
ふんわりにんげんのにおい
バターに
(バターに?)
バターに
バターぬりぬりは
むりむりですか?
コンベアは一時停止して
けむくじゃらな生き物が来て
さっとバターを持っていくと
ゴウゴウゴウゴウ
またいつもどおり。
深夜のコンビニのひかりに
虫みたいな人影が吸い寄せられてゆく
自動扉が開閉する音
来店を知らせる短いメロディ
性別に囚われない赤ん坊たちが
商品棚に陳列されている
まるでカラフルなランドセル売り場
産声を風船のようにふくらませて
ぱあん、ぱあん、と弾けてゆく
Lalala、love is over……
The machine is ready right now!
24時間営業、年中無休
部品交換、修理致します
気に入った赤ん坊を抱いて
ミルク色の燃料を給油する
【empty(0%)→full(100%チャージ完了)】
『げぷっ』
ーーーピーッ、
客はスマホをかざして、オンライン決済。赤ん坊が月賦を消費して、
はいはいを始める。その動画を S N Sに u p する。サブスクで好み
の子守唄を選んで、ダウンロード。ビル⚫ードランキング上位を鬼
リピート。またメモリが減ったら、 G o o g l e m a p で検索し
て、近所のコンビニに駆け込んでゆく。適度に反抗期、 N o N o N
o! いつか人間は絶滅して、『 はだいろ』なんて、通用しなくなる。
みんないろんな肌色を楽しんでいる。性別欄も死に絶えて、黄ばん
だ戸籍がシュレッダーにかけられる。さようなら、⚫⚫家、こんに
ちは、ファーストネームで呼び合う社会。( 仮 ) の親がつけたファ
ーストネームは、成人になったら自分で正式な名前を選択する。マ
ッチングアプリで恋をして、結婚相手をふるいにかける。結婚相手
も選択して、洗濯する時代がくる。ぐるぐるぐるぐるぐる。
+
深夜のコンビニのひかりに
虫みたいな人影が吸い寄せられてゆく
自動扉が開閉する音
来店を知らせる短いメロディ
性別に囚われない成人たちが
商品棚に陳列されている
まるで都市のネオンサインの点滅
助けて、としずかに叫んでいる
I still miss ”you”
息を吐く、黒い雲ができる
球体は楕円になって
あらぬ方へと飛んでいっちゃって
洋梨みたいだと笑ったよ
少女からテディベアを奪う鉄風
あれに皮をむかれてしまう、と
宙のあかぎれ 強き光を投げる
ばたつかせても前にすすまない
足は絡まり互いの悪口を言い出して
「あれはUFOか?」
指したゆびが折れまがり
こもれびの安寧はいつも一瞬
あたたかな土曜午後の訃報
惰性で口に突っ込んだたらこパスタ
喉に引っかかり水で流す
結構簡単にしんでしまうよ
窓にセロファン、赤に断たれる肌
寝取った日 夜の長いことよ
君がたてがみを揺らして文字をむさぼる
扉がひらくそこには誰もいなくて
閉めるするとまた開いてまたいなくて
ペットをなでる手が充血して
嗚呼、もう近い
すきでもない人のために花を送るのが花屋で
すきでもない人のために停まるのがバス
すきな人のためだけに停まれば良いのに
でもバスに乗るほどすきな人はいないし
バスは人をすきにならないから
すきでもない人のためにバスは停まる
すきでもない景色を見ている
すきでもない人のために名前を変えるのが結婚で
それはすきな人のためか
でも今までずっと一緒にいた名前は
すきでもない人の名前なのだろうか
すきでもない人のためじゃなくて
すきな人のために生きるのが結婚だから
すきな人の名前以外は捨ててしまいましょう
それがすきでもない名前ではないと
言えない社会がすきでもない
すきでもない人のために花を貰うのがマナーで
すきでもない人のために停まらない自家用車
すきな人のためだけに生きられたら良いのにね
すきでもない人のために暑い中
交通整理をしなきゃいけないのはなんでだろう
そんな暇があったら
すきな人にアイスクリームを買えるのに
お金を貰えるからです
すきな人のためにすきでもないバニラアイスを買うより
福沢諭吉のことがすき
結婚したいくらいすき
すきでもない人のために生きないでね
これからは自分のために生きてね
すきでもなくなった人たちはそう言い合って
バス停で手を振って別れるけど今まで
すきでもない名前を背負って
すきでもないバニラアイスを買うために
すきでもない交通整理をしていたのに
そんな自分をすきになって生きるなんて
それはきっとすきでもない人のため
自分のためではない誰かのため
バスターミナルはすきでもない人で満ちていて
誰も彼もが大好きな福沢諭吉を握って
すきでもない街に行ったり
すきでもないお土産を買ったり
皆自分のためだけに生きたら良いのに
すきでもない泣いてる人に
席を譲ってくれたり
バスの出発を遅らせてくれたり
それはきっとすきでもない人のため
そんな自分をすきになって生きるため
すきでもない人のために生きないをしたい
涼しい部屋で丸くなって
チョコミントだけを食べられる
部屋には誰も入って来なくて
すきでもない人のために
交通通整理をしたり
アイスクリームを買ったりしなくて良い
だいすきな諭吉と2人きり
でも諭吉は何も話してくれなくて
アイスクリームも食べてくれなくて
すきでもなくなった人がくれた花が
水を替えるのはすきでもないので枯れて
部屋の外に出るのは
すきでもない人が溢れているから怖い
すきでもない人のために信号を守ったり
すきでもない人のことを思い出したりは怖い
涼しい部屋の中でひとりきりで
そんな自分がすきでもなくなって
赤信号に突っ込みたくなる
すきでもない名前のある紙を
すきでもないのにゴミ箱に入れる
そこらへんに置いとけば良いのに
すきでもないゴミ収集の人と
すきでもなくなった人がそれは
すきでもないかと思って
ゴミ箱にはすきな人はいないので
すきでもない名前とお見合いさせましょう
高速バスの予約表と
アイスクリームの包み紙を一緒に
ベンチの裏に自販機を置いて
諭吉を英世にする社会も
すきでもないと言えないのは
アイスクリームで口が塞がる
交通整理はすきでもないけど
すきでもない人がすきでもない街に
無事に辿り着けるように暑い中
すきでもない景色を見ている
ベランダの白いプラスチックの植木鉢にまっすぐ日が射したからわたしはガラスの球根をきみに渡すと好きなところに植えてきてってお願いする。きみはそれを空色のサコッシュにくるむと次の朝の始発に乗ってわたしたちは生きてるけど死んでることについて書かれた本を読みながら西の方へと向かう。
車両にまっすぐ並んだ窓に流れる手がかりのない景色と見慣れた文字の組合せはトースターのダイヤルを指先で回すみたいにとても気軽にできてるからきみは心を許さないようにサコッシュの上に湿り気のない手のひらを重ねる。
違うラインが引かれた電車を乗り継いで代わり映えのない駅を数えていくけどきみは結局ひとりぼっちでその日の終わりに誰の思い入れもないホームに降りるとぽっかり浮かぶ夜行フェリーの甲板に立ってることに気がつく。
仄かな爪痕が瞬く海できみは潮風に吹かれながら切れそうな月にガラスの球根をかざしてみるとそこに映るのはどこか知らない赤色矮星。か細い光はガラスの面で屈折しながら夜空の片隅に向けて進んでいくからわたしは夜の底を平行して走る新幹線の窓からその一筋のフィラメントを見ている。
きみが乗る船は深い呼吸を繰り返しながら夜を超えて靄に浮かんだ朝焼けのターミナルにたどり着く。開いたばかりの売店できみはアイスクリームを掬ってがらんと空いたガラス張りの天井を見上げると伸び縮みする時間の中でいつかこの場所に来たことがあるような気がする。
わたしときみが出会う前みたいに空気が薄く広がる街をきみはガラスを素手で握って冷たい風に押されながらまっすぐ伸びた道を歩いていく。たまにすれ違う人の姿を球根はブランコみたいに揺れる視点で映すけどきみはいつものぶれないアングルで通り過ぎる。
起き抜けの商店街の長いアーケードを抜けて駅ビルの上の観覧車が見える小さな公園に通りかかると草臥れたベンチに黄色いスコップと赤いステンレスの水筒が忘れられてる。きみは少し迷ってからベンチに腰かけてガラスの球根を水筒の隣に並べてみるとその色合いはいつかわたしの擦り傷に浮かんだごまかしのない水に似ている。
きみはふと携帯をとりだしてわたしたちがこれまで心に削ってきたいろんな図形をぼんやりと眺める。ゆっくり立ち上がって滑り台の下の湿った土をスコップで耕してから洋梨くらいの穴を掘る。ベンチの球根をやさしく深みに下して上からそっと土をかぶせる。
水飲み場で入れた水を円を描くように水筒から落とすと辺りの土の色が変わる。きみは他愛のない自由をこらえながら時間を止めるように公園から歩きだす。
すっかり日が昇ってたくさんの人と行き交うけどきみは心を覆う空の隙間を埋めるように記憶を回す観覧車だけを見つめながら駅に向かって歩いていく。
わたしは視線の先にある古びた白いゴンドラに座って咲くか咲かないかわからない花のことを考えながらきみがわたしを通り過ぎるのをいつまでも待ってる。
冷え切ってしまったお湯を
もう一度だけ沸かすために
やかん片手にあなたが暮らすアパートへ
聞いたこともない路線に乗って
聞いたこともない駅で降りて
歩いていく足は
コンビニの明かりとガードレールに絡めとられ
進むごとに
子どもの靴の反射材に変わり
薄鼠色の空の下
ひんやりとしたモルタルが
祖父の家で過ごした夏休みの湿度に変わる
ぐるりの土間
炭を宿した掘りごたつを囲う
上りかまちの奥にある座椅子は
朽ちた布とウレタン
バネが飛び出た隙間で
今はどこにいるのかわからない祖父は
体の形に黒ずんでへこんでいた
お湯 沸いたよ
動けない祖父に代わり
豆電球だけが灯る台所へ
床に置かれた
鞄の中の暗闇を覗き込んだとき
鈍い光を見つけた
しん、として
いくら指でつついても反応しなくなった
カブトムシの屍みたいだった
光が消える
母の怒鳴り声
汗が混じった手のひらの中に
財布から盗った千円札が湿っていた
話をするだけ
たったそれだけでいい
呪文を粘土にして口の中で捏ね
やかんを左手に持ちかえ
あなたのアパートの鍵穴にスペアキーを差し込む
ドアノブを回す
手のひらが
千円札の湿り気をはっきりと覚えていて
冷え切った湯が
もう一度 沸く温度が知りたいだけ
今度こそは
欲に負けないように
決して振り返らず
靴底の薄いつま先を
ドアの隙間に差し込む
親指の二枚爪がいつまでたっても治らない
マンダリンは滅びぬと聞いて涎を呑む人々が
今日も祈りをささげます
その言葉はある日知れ渡った
それは古典の言葉か
現在の記か
あるいはおじいさんの預言か
誰も知らないのに
誰もがその言葉を望んでいた
かくしてその言葉は聖典のように
人々のまえに出現しました
それは革命だったのかもしれない
幼子も小さな たなごころを擦り合わせ祈る
マンダリンを渇望し
マンダリンを崇拝し
その甲斐も空しく幼子は悪夢を見る
すべての光景は繰り返される
幼子には分からない
マンダリンは滅びないのか
またはもう既に滅びているのか
たとえマンダリンが偽物でも
ほんとのマンダリンを見たことがなければ見抜けない
見たことがあるだろう者たちは
もはや口を持たない
今日も幼子は母に手をひかれ
列に加わり祈る
宮殿はじめっぽく 幼子のひたいに にじんでいる
明日も続く
明日も
その時私は、台灣の街路の匂いを思い出していた
またはエルテレサのワンバースを
すると 甘酸っぱい香りが
街路に ただよって
気づけば私は駆け出していた
スピーカーを片手に
確かな目的を持って
祈りで溢れかえる街を
街を
海のうかべている
ほかげと笑み
光りの鱗
いくつもの潮目をたどってきて
まじりあう
ふたつの水
盲目の手が泳ぎ
さまよう指の溺れようとする
海の肌身のうねり
おなじひとつの夢のくびきに
見えないものの もやいの糸で
からだごと結ばれて
波のおこりの手覚え
やがてくる、潮の横溢に
陽は碧くさしこみ
光りの襞をすりぬける
海の蠕動
かぼそい潮すじの
よれた すきまへしずみこみ
しろく泡だち なみうつ
ひきこむ流れ
はらいだす流れ
流れと流れの腕のもつれ
海の熅れ
身を躍らせて
海藻の茂りをゆらす、汗
洪水と 光りの束が
ひかれるままに高みをめざす
沖へむけて走る
震えるつまさきで
生きていることに汚れながら
反転し たがいを抱えこむ
咥えこむ たがいの苦痛まで
より遠く より大きな解釈を得るために
ひとつになって 奔流へとむかう
突きすすむ、二枚の舌
口をあけて 声にならない声で
たがいの名をはげしく呼びあう
叫びあう、
産まれのような
眩しい出口
光りの柱
とめようもなくあふれ 甕を割って
流れだす舟
見えないもののたぐる もやいの糸で
なぶらは沖へと曳かれていった
鳥たちを連れて
潮目に果てた ふたつの藻屑のこして
とびたっていった
海のなかぞら
うすみず色をした 天上の沖にうかぶ
消えいりそうな半透明の輪郭
ひるまの海月
■うるし山 千尋選評
作品を読みながら、言葉の鮮度というものについて考えました。そしてそれが借り物ではなく自分の体内で熟成された言葉なのか(身についている言葉なのか)、ということについても考えました。新鮮な言葉と熟成された言葉、相反するように聞こえますが、同居させると詩は面白くなります。
【入選】
水町文美「模写」
いつもと変わらぬ日常でありながら、まるで知らない世界に身を置いているかのような感覚を描いている。「小さな部品」の「小さな欠陥」からはじまり、徐々に意識の奥へと拡がっていく。書き過ぎず、うわつかず、冷静に自らの内部へ入り込んでいく姿勢がいい。ラストの「帰り道は分かっている/けれども家は/知らない人がなぞったような/太くて妙な輪郭をしている」は、今を生きる誰もが感じている不安をうまく捉えている。世界が〈切実な他人事〉として静かに襲ってくる感じ、といえば良いだろうか。タイトルの「模写」が、この最後の連に対する想像力をさらに膨らませる。
むきむきあかちゃん「私がネアンデールタール人であったなら」
展開の「仕方」とその「自然さ」が絶妙で美しい。三連目まではよくある展開。四連目「もし私がネアンデルタール人であったなら/何も成さないのだろう」から作者固有の世界へ引き込まれる。人類は(人間は)そもそも何かを成さなければいけないのだろうか。大きな問いがそこに現れる。一歩間違えば凡庸な詩に留まるところを、ぎりぎりのところで回避している。あっけらかんとした虚無が見え隠れするため、「教科書に載りそうだが、載せられない詩」。また、巧妙さにおいて「誰でも書けそうだが、書けない詩」でもある。この作者の別作品「マンダリン」も、突き抜けた感があって良かった。
佐田征優「原型詩の試み1:風について」
私の神話に関する知識は小学生なみだが、それでもこの詩は面白かった。面白かったと言うのは、イメージの拡散がどこへ向かっていくのかわからなかったという点で、新鮮かつ刺激的だったという意味だ。「風は自分の好むところに吹く、そのことを感覚してしまった男はもはや男ではなく、詩人であった」や「ママチャリのまっすぐな時間とその車輪のめくるめく時間が同居して、世界は推進する」の想像力は素晴らしい。最後の「谷川俊太郎」が今回は作品のなかでうまく機能している。だが、この「名前」はそれまでの流れを飲み込んでしまうほどの「色調」を持っているので、扱いには相当の注意が必要。
三刀月ユキ「ぼっき」
生命の輝きをみせてくれた。内へ内へと入り込んでいく詩が多いなか、この作品は外へ、未来へと、希望と愛にあふれた作品だった。2連目と3連目がいい。まだ理由や意味を必要としない生命体(こども)の神秘的なまでの「ありのままさ」をうまく描いている。また、「ほどけない歴史の螺旋と/こっけいなまでに真面目に首っぴきして/準備しているのだ 実行しているのだ」とある。この小さな「ぼっき」を、純粋さとはまた違う、〈新しい生命の律動〉を産み出す起点と捉えていて、当たり前といえば当たり前のことなのだが、歴史って、そういうことなんだよなあと感心してしまった。
こやけまめ「うつくしいものがしつこい」
出だしの2行がとてつもなく格好いい。さらに2連目の「記憶もからだと同じように新陳代謝して/私から離れて/誰かに受け継がれているはずだ/ことばにしなくても」がこの詩の個性を引き立たせている。「記憶」が「ことば」とは別な次元で機能しているということを、あえて「ことば」で表現するところに、この作者の世界に対する距離感とスタンスをみてとれる。タイトルを見て、疲れて街を歩いているときに、こういう感覚あるよなあと思った。確かに昨今、人も地球も繋がり過ぎてはいないか。そこにあるかのように錯覚させる「うつくしいことば」たちに。
【佳作】
奥村紘「雨」
言葉の選択とリズムが嚙み合っていて心地良い。必要最小限で必要なものすべてを書いたような作品。1行目だけに「。」(句点)がついているのは、2行目以降が視覚から流入してくる雨のイメージのみによって構成されているからであろう。では一箇所だけ具体的な感情を描いている部分、つまり「音がするので寂しくない」の一行は何を意味するのであろうか。詩の流れからすると、本当は「音はせず寂しい」というのが本音ではないか。しかしそれではあまりに湿っぽくなってしまう。そこであえて逆に書くことで、イメージの世界と現実世界をこの一点で結着させようとしている、と勝手に想像して私は楽しんでいる。
三明十種「葛の葉」
地味な詩だが暗くはない。短い詩だが世界を持っている。「葛の葉」を「私自身(人間)」に置き換え、「揺れている」を「生きている」に置き換えると、その深さがわかる。
特に第2連がすばらしい。具体的なものから曖昧でぼんやりとしたものへ(最終的には自然へ)とイメージが流れていく。余計な言葉がそぎ落とされていく。生きて老いていくとはこういうグラデーションなのではないかと思えてくる。そして、「湿り気」=「生きているという業(ごう)」は、最後には陽に吸われていく。清らかに空に帰っていくようで、美しい。
小海真「もろもろのひとこぞりて」
祝祭のなかに人間の暴力性を捉えた作品。最後の「冷たい顔の子供」と「あたたかい石」の対比が際立つ。冷たい顔の子供から見られている「わたし」はいったいどのような状態であろうか。「あたたかい石」とは何だろうか。身体は社会の中で自然に生活しながら、しかし心には社会との間に透明な、しかも打ち破ることができない強固な壁が存在する。この詩を読むと、自虐と開き直りと羨望と悪ふざけのなかに、そういう、つまり何とも言いようのない寂しさを感じる。
未補「CHOKE」
言葉にできないものを線や色で表現するのが絵画であり、言葉にできないものを音でもって表現するのが音楽であり、言葉にできないものを言葉によって表現するのが文学である。と、私は思っている。このとき「言葉にできないものを言葉によって表現する」という矛盾に、自覚的であるかということが、詩を書くうえで、とても大切なことだと思う。
この詩から意味を読み取ることは難しい。しかし、ただ思いつきだけで言葉を拾っているようには思えない。意味の伝達とは別な次元の言葉がこの世界には存在することを、この作者は自覚している。
金固歩見「伝統芸能の挑戦」
ある意味、斬新なのではないかと思った。最初から最後まで神楽の魅力拡散と舞い手の募集に徹している。純粋でストレートな広報活動。そこに暗い文学の影はない。そして不思議とこのリズムに惹かれていく。繰り返しの多い神楽の笛の音に惹かれていくように。「お餅を撒くと知っていて/みんな袋をもってきます」のあたりから完全に心が舞ってしまった。伝えたいこと(詩の目的)が見え隠れする詩はあざとさを感じるものだが、この詩は目的が丸裸すぎてかえって気持ちがいい。迷いがない。
■浜江順子選
【入選】
三刀月ユキ「マーメイドペイン」
熊倉ミハイ「げんにぬりぬり」
こやけまめ「うつくしいものがしつこい」
未来の味蕾「点滅するネオンサイン」
大庭颯隼「翳らない部屋」
【佳作】
宮本誠一「トライトーン」
柿沼オヘロ「藤棚」
古森もの「記憶は白い」
メンデルソン三保「たくあんの人」
阿呆木種「Romance」
選評 浜江順子
1年という期間、送られてくる詩は膨大であったが、ある意味、私に煌めくような大きな刺激を与えてくれた。それはまるで詩の銀河のごとし。私の初心は、はるか虹の彼方にあった。いつも少しモコモコで少し不格好な初心。一般的に初心はけっこうか細い土筆みたいなヤツで、なんていうことのない風にポキッと折れたりするものだ。己を信じて、未来へと書き続けて欲しい。今回は十代を二人、選んだ。意図的ではないが、偶然にそうなった。私といえばこれからも詩を書くのだが、初心に戻り、皆さんのエネルギーに負けることなく、もっと果敢に冒険をしようと思う。1年間、投稿していただいた皆さんに感謝したい。
■浜江順子選
【入選】
三刀月 ユキ「マーメイドペイン」
ここには詩の本質も語られているようにも思う。つまり、「無言の苦しみの中で/心臓に腹に真珠を育て続けるあなたよ」、さらっと書いたようにみえる詩もそこに書いた者の「声にならぬ痛み」があるからこそ、読む者の心を打つのだ。ここでは、もちろん、詩人に限定して書いてはいない。もっと広く人々の痛みという枠で捉えてよいだろう。そして、これらの痛みを感知する耳も「わたしたちは今日 そうして最も古い耳を持つ/街も山も重度の難聴で」と、あくまで客観的に捉えている。現実には自分を含めて他者の痛みにはきわめて鈍感な「難聴」で、したりげな顔をして生きているのだ。
熊倉ミハイ「げんにぬりぬり」
残忍な人間社会の構造を軽いタッチの「にんげんに/バターぬりぬり」と、軽やかに風刺している技は秀逸で、(ほほおッ)と感嘆させるのである。軽やかに書くほどに、かえってその残酷さはクッ、クッと浮き上がる構造を実によく利用している。例えば、「へいたいに/バターぬりぬり/ジャムも/どまんなかにぬりぬり/すぐさま軍服を着てもらい/工場の外にそのままプイ」、まるでいまある世界の戦争を描写しているようである。現に世界は残酷さと軽やかさが裏表で、こともなげに恐ろしいことが次々となされている。「ゴウゴウゴウゴウ/またいつもどおり」と、さりげえなく終えるところも憎いばかりだ。
こやけまめ「うつくしいものがしつこい」
美しいものを愛でるということにさえ、あえてアンチテーゼを唱えてみせるこの詩は、読む者たちの感情をスーッと収納する言葉たちを有している。「記憶の中で造花にしたはずの桜は腐っている/もう会いたくない人たちも次々に腐っていく」、人間の心に潜む本心を晒していく。だからこそ、説得力を心の二等辺三角形の底辺から有す。「人は、地球の物質は、繋がりすぎた」、これは世界への大いなる反論で、多くの人たちが思うところでもある。昔の人と人があまり繋がりえなかった時代は、人間の本質において正しい時代ともいえる。最後の「私はいつもそれらに監視されている」は、ダイレクトだが説得力を持つ。
未来の味蕾「点滅するネオンサイン」
人間がモノ化していく現代を痛烈に風刺しているこの作品は、『げぷっ』、「―――ピーッ、」など、軽い音響効果も動員して人間の怖ろしい未来をも小気味よく、リズミカルに描写していく。「性別に囚われない赤ん坊たちが/商品棚に陳列されている」は、空恐ろしい未来図で、人間とアンドロイドの見分けがつかなくなり、さもありなんと思えるからいっそう怖い。さらに「性別に囚われない成人たちが/商品棚に陳列されている」と、成人までも商品化されているかもしれない未来社会。人間が商品化された未来世界を、小気味よいタッチで鮮やかに呪い描いている。
大庭颯隼「翳らない部屋」
17歳の男子高校生の書いた短いこの詩は、日常の危うい世界をクールなタッチでぶっ飛ばしていく。過激な気配を少しアンニュイなタッチでこともなげに独自の感覚で言い放つ。「あたたかな土曜午後の訃報/惰性で口に突っ込んだたらこパスタ/喉にひっかかり水で流す/結構簡単にしんでしまうよ」、普段の生活に潜む危うい死の影さえ淡々と飛ばしてみせる。「窓にセロファン、赤に断たれる肌/寝取った日、夜の長いことよ/君がたてがみを揺らして文字をむさぼる」も「寝取った」前後を鋭角的な角度で描いてみせる。言葉と言葉を軽やかな感覚で発射、そこには意外な正確さと巧みさが若さの奥に隠れている。
【佳作】
宮本誠一「トライトーン」
「音楽の悪魔」とも呼ばれる三全音(英語ではトライトーン)をひとつのドラマとして再現したこの詩は、「そう、あのときだって/………………………………」の転調してからのドラマが巧みだ。「やつは自分から/存在を/無音へ/ずらしちまったのさ」は、どういう後戻りできないある状態なのか定かではないが、その描写は「一度アームから ガタンと肘を落としちまえば/押しちまった核ボタンみたいなもので/もう後戻りできない」と、うまく嵌め込まれたドラマツルギーのようにこの詩で確かな役割を果たしていて、見事である。
柿沼オヘロ「藤棚」
詩の中のキマイラは中性のキリスト教寓意譚では「淫欲」や「悪魔」という意で使われ妄想や空想を表すように、この詩でもほぼその意味で使われている。藤棚からの官能の世界、そしてキマイラという流れを無理なく詩にしているこの作品は、「キリンのキマイラのようで/その腹の下に 私がいるようで」と、その流れは無理なく、おどろおどろしく推移している。「そんな官能がなぜか懐かしく」と、かつての愛を懐かしみながらも、「百年の約束を果たしたように/キマイラになっていく」と、物語化させていく最後のくだりは想像の世界が日常へと飛んでゆく。
古森もの「記憶は白い」
独特の表現は独自の隠喩ともいうべきで、作者の匂いがいやおうなくついてくる。導入の「感情の/開け方を忘れて/朝、/乾いていく」のこの四行で、この作者の詩に対する嗅覚の個性的にして的確な感覚が分かる。ここの表現はなぜか一般にも鮮やかに通じるところが巧みである。「フォークであなたの/頬を刺したとき/風より先に/血が流れて驚いたこと/それが何より/雪が降る、/に似ていて/安心できたこと」は、その感覚が独特でしかも優れていることを証明してみせている。人間本来の孤独の下に隠された怖ろしいまでの描写は読者を納得させるのに十分である。
メンデルソン三保「たくあんの人」
「たくあんの人」という設定が巧い。「二時か三時 わたしのベッドに横座りして/………………………………/たくわんをすすめてくれる」は、性別、年齢は分からない。「誰なのか知りたい気もするが/知らなくていい気もする」は、ある意味、人生讃歌で自分自身へのいたわりのような気もする。自分でいたわらなければ、ともすると誰もいたわってくれない時代。最後に「たくあんの人がやたら/わたしの真夜中に馴染んでいて/ちょっと笑いたくなった」と、軽ろやかに着地する。ユーモアの感覚と人生への哀愁が「たくあんの人」を生み、読む者も知らず知らずに癒される。
阿呆木種「Romance」
17歳の女性のこの詩は、恐ろしいドラマを短い詩のなかに凝縮した。「おんなは蠅に 恋をした」というもので、これは何か別のものを比喩しているのか、それともストレートにそのままの世界なのかは定かではでないが、ドキッとする想定で、読む者の心を鷲づかみにする。ドラマとしては「蠅に恋した おんなは自死し/その肉以って 愛を産む」、衝撃的な内容を淡々と綴るゆえに、かえってその恐ろしさ、おぞましさ、純愛さ、訳の分からぬ何かがドドッと押し寄せ、読む者の心にも卵を産みつけていき、哀しい恋の結末に何ともいいがたい驚きとその狂気に酔いしれるのだ。
■雪柳あうこ選評
1年間、訪れ続ける詩たちと日々向き合って過ごしてきました。夏には暑さを歌う詩が、そして冬には寒さに凍える詩が多く集い、あらためて、わたしたちがことばと共に生きる「生物」なのだと感じさせてくれました。
生きることに必死であることが伝わる詩が多くあります。一方で、今期はユーモアの光る詩も多かったように思います。ことばはいつも、個人的あるいは社会的な偶然/必然によってあなたから生まれてくるものだと信じています。それらをぜひあなただけの方法で練り上げてみせてください。これからも、どこかであなたの詩と出会えることを願っています。
【入選】
・緒方水花里「ターミナル」
・佐々木春「ホイール」
・長澤沙也加「振り返らないアパートで」
・むきむきあかちゃん「マンダリン」
・安藤慶一「海月」
【佳作】
・熊倉ミハイ「げんにぬりぬり」
・三刀月ユキ「ぼっき」
・泉水雄矢「布団が吹っ飛んだ」
・関根健人「葬葬」
・早乙女ボブ「二十一歳」
・柴田爽矢「恋は茄子」
【選外佳作】
・遠野一彦「ひかり」
・雪水雪枝「からめる」
・メンデルソン三保「キティちゃんと核爆弾」
・佐藤百々子「nuit de verre」
・吉岡幸一「死んでいる米田さん」
【入選】
・緒方水花里「ターミナル」
労働にはそれなりの(あるいは期待より小さい)対価があるだけの「すきではない」世をどう生きているのか、どう生きるのか、どう生きたいかが、リフレインに乗って巧みに描かれています。バスや「諭吉を英世にする世の中」など、各所に用いられている比喩と現実性のバランス、そして社会と個人のあり方の視点の持ち方など、多彩な魅力に満ちた詩であると同時に、「言いたいことは言いたい」という筆者の想いを読み手に確と伝えてくれます。わたしはこの詩がすきです。きっとこの詩を読む人たちも、この詩が好きになるんじゃないかと思います。
・佐々木春「ホイール」
「わたし」が「きみ」に「ガラスの球根」を託すところから始まる散文詩は、きみの旅を見つめるわたしの視点によって美しく想像的に綴られていきます。「わたし」と「きみ」の両輪のくらしの中に生まれただろう、壊れやすい未来を携えた「きみ」の遥かな旅。それは幻想的なだけでなく、同時に「わたし」から「きみ」へのいとおしさと、託して旅立たせることを選んだのだろうさびしさを根底に感じさせてくれます。「きみ」が球根を丁寧に植えることによって、昇華されていくもの、残るもの、巡り続けるものを予感させます。詩として描かれることの必然を感じました。
・長澤沙也加「振り返らないアパートで」
この詩が描いている過去が現在にオーバーラップする様は、今にかかる振りほどきづらい力を「振り返らない」と言いたい様を絶妙に表現しているように思えます。祖父が一人で暮らしていたアパートに凝る深みと小さな罪の輪郭、それらを象るように己が生きる「アパート」の現在からあまり遠くない過去を想う切実さ、不意に生々しい千円札の感触。読み手一人ひとりが己の目線を照らして読んだ時に、このアパートに読み手それぞれの物語が立ち上がり、多様な読み方を可能にさせてくれるでしょう。技量のあることばで構成された見事な詩です。
・むきむきあかちゃん「マンダリン」
宗教、そして「信じる」という行為を冷静に追求することを、瑞々しい響きを持つ果実に込めて描いた詩です。わたしたちは(とくに子供時代は)親密な他者が信じているものに抗いがたいですが、時に現代が「権力」として描くものがどういう質を持つのか、そしてその側面を確と描いていると感じました。それらの重たさをどこかさらりとまとめつつ、果実の香だけでなく爽快ささえ感じられるような最終連が見事です。感性と技量の双方を感じます。
・安藤慶一「海月」
繊細で美しいだけではない、厳しくも情熱的な海の風景が描かれます。目のない海月同士のからみ合いは情交にも似て、どこか官能的です。海という広大さにどうしようもなく流されながらも、許された感覚器官で必死に何かを掴み、時に相手と共にあることに藻掻く様は、人の生き様そのものなのでしょう。「沖へ向けて走る/震えるつまさきで/生きていることに汚れながら」が印象的です。最終連、すべてに果てた後、もはや生きているのか死んでいるのか分からない「ひるまの海月」が静かに漂う様子に目を閉じて祈りたくなる、そんな詩でした。
【佳作】
・熊倉ミハイ「げんにぬりぬり」
子どもの頃に想像を巡らせたことのある、どこかマザーグース的な世界が、「ぬりぬり」の音韻とことばの軽快さを追求しながらリズミカルに進んでいきます。想像と創造の世界にぐんぐん羽を伸ばしているようでいて、後半は「同僚」が登場してくるなど、比喩だけでなく現実へのそれとない仕掛けも見事です。人を物のように扱うことや、やり場のない感情を何とかする様を、皮肉とユーモアをたっぷり含めて描く面白さを感じました。最後、せっかくこの詩なら「いつも通り」じゃなくても面白いかも、と思いました。
・三刀月ユキ「ぼっき」
三歳の息子の裸の姿に母の目が見た率直な感動が、湯気の熱と共に伝わってくる力強い詩です。むき出しの命に触れる喜びと驚きを手に取るようにわからせてくれることばの運びは、わたしたちが柔らかな生き物であることを強く感じさせてくれます。最終連、わたしたちが子に見出す普遍的で優しい祈りが伝わります。三歳児らしさを汲んだのだろうタイトルも素朴で素敵です。一方で、性器や命、あるいは愛ということばに比喩を用いると、詩としてもっと面白くなるかもしれない可能性を思います。
・泉水雄矢「布団が吹っ飛んだ」
布団が吹っ飛んで電車の架線に引っかかる……どこかで聞いたような、でも実際にはあまり起こらないような話を軸に、軽快なことばの運びがかろやかに詩の世界へ連れて行ってくれます。革靴、目線、動き、感情表現の細部まで、日常へのいとおしさのある眼差しと、表現への丁寧な工夫が感じられます。普段は隣の人を意識もしない電車にあって、同じ感情を共有していく様が素晴らしいです。最終連、あえて途切れたことによって生まれる読後感も素敵でした。「みどりのでんしゃ」を青空や布団(の白)と対比させながらもう少し印象付けてもいいかもしれません。
・関根健人「葬葬」
骨を拾うシーンから始まるこの詩は、箸で抓んだその小ささ軽さが導く「わたしはわたしのからだの/おもさをじかくしなければならない」という2連目冒頭がとくに見事です。連綿とつながる生と死に直面して己に流れ込むものを「おもさ」として自覚し、この先を生きる者としての己の自覚と責任を問い直すことばに、静かな共感を覚えました。死を前にして感じ取るものが「官能的」でもあり、また「星雲の瞬きにも似ていた」と表現されるのには、「骨」に対して肉体的にも精神的にも深く広がることばを選べる筆者の力を感じます。葬ることで引き受けたしなやかな覚悟を感じさせる最終連も印象的です。あえて「葬葬」としたことが、もう少し明示されてもよいかもしれません。
・早乙女ボブ「二十一歳」
込められた情感の多彩さは、夜明け前のモノクロームの世界に呼応するように淡々と語られていきます。一連一連が独立した短い詩のようにも読めました。ことばは多すぎても少なすぎても難しいですが、この詩はそのバランスが絶妙にかみ合っているように思います。一人きりで音楽を聴いて、水を飲み、心身を満たすことのさみしさとよろこび。最終連は他者の暴力性を示唆すると同時に、かすかに他者への期待も感じられるように思えました。タイトルと内容の関連が少し明示されると、多くの方に確と伝わるかもしれません。
・柴田爽矢「恋は茄子」
「恋は茄子/ゆびのゆらめくあそこらへんで/あなたのゆめをあやとりたい」という第一連から惹きつけられました。焼きナスを作っている途中のように、いい匂いがしたり、ぐにゃりと柔らかかったりする描写も官能的です。あいまいな恋の輪郭と、生きることに直結する食(茄子)を比喩的に融合させながら、幽玄と有限を漂うような表現が素晴らしいです。「恋は茄子」であることをたっぷりと楽しむことができる詩ですが、途中に読み手に驚きを覚えさせるような動きが1行あってもいいかもしれません。
【選外佳作】
・遠野一彦「ひかり」
・雪水雪技「からめる」
・メンデルソン三保「キティちゃんと核爆弾」
・佐藤百々子「nuit de verre」
・吉岡幸一「死んでいる米田さん」