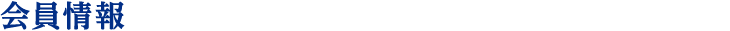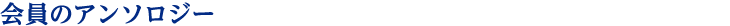会員のアンソロジー3・以倉 紘平氏~
以倉 紘平 イクラ コウヘイ
①1940(昭和15)4・8②大阪③神戸大学国文学科卒④「アリゼ」⑤『地球の水辺』『プシュパ・ブリシュティ』湯川書房、『朝霧に架かる橋』『心と言葉』編集工房ノア。
吉野山――嵯峨信之氏に
――子供のころ
一緒に遊んでいてね
夕方になるとみんな帰って行くんだよなあ
自分の家へ。それがふしぎだった
吉野 東南院の大広間
嵯峨さんは幾度もこんな話をしたものだ
一緒に遊んだのは束の間であった
夕星が出て
嵯峨さんは帰って行った
今頃、靴を脱ぎながら
靴底についている花びらを見て
なにかなつかしいと
どこか遠い世界のものだと思っているだろう
この世で
私たちがポエジーと呼んでいるもののように
吉野山の満開の桜はもう思い出さないだろう
池上 耶素子 イケガミ ヤスコ
①1938(昭和13)1・28②静岡③静岡大学教育学部卒④「地球」「嶺」⑤『遠い夏の声』地球社、『如月の昼下がり』書肆青樹社。
花が咲いて
やがて
雪の下から福寿草
畔にタンポポ 山にマンサク
庭に連翹
大地の半分を黄色に染める
花々の放つ光の
吹き渡る風の
連綿と続くいのちの
再生の春は
花と 風と 光り
ふり注ぐ透明な沈黙
あなたの眼差しは
地上にあふれ 満ちて
父よ
風が吹いて
あなたを思う
花が咲いて
あなたを思う
池澤 眞一 イケザワ シンイチ
①1938(昭和13)7・23②鳥取③鳥取大学学芸学部卒④「灘」⑤『袋灘』私家版、『道具』手帖社、『鳥取平野水尻』詩人会議出版、『青谷花暦』今井書店。
勾玉
古代出雲狩りに出かけた男たちが
山野を巡って野宿を重ね
獲物を見つけて慌てた拍子に蹴つまづいた
割れた石くれの 風化に抵抗しはじめたばか
りの角 カギ裂きが足元をにぶらせ
血の匂いが山蛭をうごめかし
肉食獣を刺激する
足の外傷が治るまで
男は洞穴で日をすごし 家族への語り草
ネタを手にして無聊をかこち
手なぐさみに石を磨いてみると
しまいこむべきポケットは
身体にはなく
穴をうがち紐を通し
首からぶら下げて移動する
婚約の印に娘に贈り
心を形にして示す
池田 瑛子 イケダ エイコ
①1938(昭和13)4・7②富山③青山学院大学文学部英米文学科卒④「禱」「地球」⑤『母の家』『池田瑛子詩集』土曜美術社出版販売、『縄文の櫛』文芸社。
青い炎
音を消し 目をつむると
みえてくる 母の深い悲しみの跡
言葉にもなれず
どこにも記されず
零れる涙にもなれず
日々の暮らしに隠されていった
ひりひりする心の傷みを
ながい歳月
月と星々が読みとってくれただろうか
亡くなって十七年も経つ今頃になって
母の悲しみの炎が
夜の橋を 渡ってくる
ほの ほの と もえる青い炎が
やわらかい闇のなかで
わたしは待っている
ほの ほの と もえる青い炎を
抱きしめようと ない翼をひろげて
池田 實 イケダ ミノル
①1930(昭和5)6・15②大阪③慶応義塾大学文学部卒④「詩と批評」「ポエームTAMA」⑤『うさぎ どうする』思潮社、『もう誰も問わない』ふらんす堂、評論『詩論の周辺』『続詩論の周辺』文藝社。
砂山の美学
平面上の一点に微粒子の砂粒を一つまみずつ
落とし続ける〈造形されていく円錐の砂山〉。
落とした一つまみの砂粒が円錐の砂山の頂点
に達した瞬間 一粒は頂点に留まり 他の砂
粒は円錐の側面を覆い尽くし 溢れた砂粒は
円錐の裾野にこぼれ落ちる。
一粒一粒が意思あるように
意思あるものの決断に似て
円錐に留まるか 滑り落ちるか
選択は恣意的であるように思われる。全体と
して砂山が自分で判断し自らの意思で円錐を
造形しているように見える。しかし砂山に自
己に言及し自己を指示する機能はない。
この砂山は意思のある生物ではない。自然の
予定調和を意思と見られる無機物である。
砂粒の円錐には自己組織化の力学があり 砂
の円錐の表面は直前の表面を次々にコピーし
て造形されていく 円錐の造形方法を指令す
る情報がコピーを繰り返していくように。
自己組織化と自己言及性がある生物の生殖の
ように。
池谷 敦子 イケタニ アツコ
①1929(昭和4)3・9②静岡④「鹿」⑤『象がくる空』『気がつけば風』『夜伽』花神社、『?降る』土曜美術社出版販売、『青く もっと青く』書肆青樹社、『眠れぬ夜のあなたに』文芸社。
「し……」
あけがた 運河の向こう岸から
「し……」と一声
待ちわびていた水のように泌みる
その声のかたちとしての きみが
わたしの網戸に止まっていた
「ミズ」をください「ミズ」を と
土の耳にささやきつづけて六十三年
きみは ことしも帰ってきた
あの酷い叫喚の夏を告げるかたちに
熱い金網に貼りついたまま
暮れなずむ長い時を 一個の
禱る彫り物となっていく
やがて蟬鳴の大波がくる前に きみは
闇の宙へと発つだろう
「し……」とも告げることなく
わたしのなかに その痕を彫りつけたまま
池山 吉彬 イケヤマ ヨシアキラ
①1937(昭和12)・9・30②長崎③早稲田大大学院文学研究科修士課程④「光芒」⑤『林棲期』朝日新聞社出版販売、『精霊たちの夜』草原社、『都市の記憶――長崎原爆詩集』新風舎。
証人
その木はまっすぐに立っていた
一望荒野の
瓦礫のなかに
すこしの歪みもみせず
校庭に並ぶ直立不動の小学生のように
その木はけなげに立っていた
巨大な火球が彼の真上で爆発し
爆圧は垂直に瞬間的に落ちてきたので
逃げ出すひまもなかったのだ
それが孤独な電柱であることは
歪んだ変圧器が残っていることでわかる
上から二番目の横木が左右とも
下方に傾いているものの
周囲の建造物がほとんど全壊し
焼失してしまったからっぽの世界の
それは 唯ひとりの証人である
彼の全身は黒く焦げ
顔の表情もさだかではないけれども
『都市の記憶』
井坂 洋子 イサカ ヨウコ
①1949(昭和24)12・16②東京③上智大学文学部国文科卒④「一個」⑤『朝礼』紫陽社、『GIGI』『地に堕ちれば済む』『箱入豹』思潮社。
溝
俯瞰図を書けない蟻の足が透き通ってくる
かげろうが立つ道の 端に寄れば反対側が
翳り どちらに寄っても炎暑に灼かれる
前頭葉の溝まで干涸びるようだ その溝に
沿って歩き続ける 生垣の向こうを横切る
のは級友 私に目もくれずに 自分の巣に
散っていった彼女らはそれぞれが私に似た
影を引き 長い耳をしている 頭上に傷痕
のようなどす黒い太陽を戴き 炎暑に灼か
れながら生真面目な姿勢を崩さない 死ん
でいったひとりの友が半身を無間に転写さ
れながら 振り子で水脈を探しあてている
それでこのうねり波うつ道に 新しい水道
管が縦横に走っている訳がわかった
井崎 外枝子 イザキ トシコ
①1938(昭和13)3・6②石川③金沢大学英米文学科卒④「詩と詩論」「笛」「鮫」「大マゼラン」「ネット21」⑤『北陸線意想』オリジン出版センター、『母音の織りもの』能登 印刷出版部。
風の船
風よ 奪うな
わたしのことばを
――ヨコどうしてここにいる
――なにをしにここにきたか
と 風よ聞くな
おまえは旅をしながら
いつでもここにこられる
百年前にもここにきて
百年後にもここにくる
波打ち砕かれる足元
じりじりと後ずさりさせられる
岩だけの土地
――地の底にゆけ、地の底に
といっているのか
もうここは風の国の入り口か
透明な破片が突き刺さる
風の結晶だ
吹雪にまぎれて
近づいてくるのは
風の船だ
石井 春香 イシイ ハルカ
①1946(昭和21)12・24②福岡③伝習館高校卒⑤『有明』火の鳥社、『砂の川』編集工房ノア、『贅沢な休日』待望社。
少女
雲間から
少女の髪が見え隠れて
ためらいがちに覗いている
桃の花は開いている
さくらのつぼみは ふくらんでいる
北風のあいだを
かいくぐってきたちいさなひかりは
もう育っている
少女は おずおずと手を伸ばし
冷たい花びらに触れた
丘の上で はにかむ口元
少女は言葉をひき寄せた
まだ村には 下りていけない
もっと大きくなって
あなたの庭を照らしに行くわ
少女の後に待っている眩しい時間
放ち始める季
石井 藤雄 イシイ フジオ
①1939(昭和14)3・31②千葉③市川学園中学卒④「日本農民文学会」「花」「日本未来派」⑤『野の声』思潮社、『鳥獣虫魚譜』八坂書房、『公害』土曜美術社出版販売。
闇夜の烏
闇夜に烏が飛んでいる
どの方向に飛んでも
壁にぶつかったり
藪の中に迷い込んだり
台風の渦に巻かれたり
露地に入り迷路になる
難渋ばかりしてそれが当り前になっている
己の精神の在り処や
存在すら懐疑的になっていて
なにやら希望や夢も湧いているのに
好むと好まざるに関わらず
どうしても闇夜に飛ぶ破目になっている
暗い林の中や霧の山
明けない夜はないのに
明かるい陽の光の中を飛ぶは何時
石内 秀典 イシウチ ヒデノリ
①1940(昭和15)7・13②滋賀③滋賀大学経済学部卒④「ラビーン」「ふ~が」⑤『転勤』『河へ』編集工房ノア、『背中』UNIO。
背中
ときに
静かに立てかけられた張板の様な
背中に出会うことがあった
吹雪く日
火鉢を前に
黙って座る父
しんとした背中の向こうに横たわる
父の膨大な時間の集積
その時間を解きほぐす糸口に向き合う前に
私はすでに
父の歳にせまろうとしている
従軍し大陸で戦った父は
ただ 南京に近い農家の庭先で
藁山を銃剣で突いて
隠されたいもを探し出したという ほか
人に向けて発砲したことを
一度も言わなかった
背中は 黙していた
石下 典子 イシオロシ ノリコ
④「墓地」⑤『花の裸身』『神の指紋』。
ちぶさ
かんかんに張る乳房の
痛みに眠れぬ夜は
死産の児が乳を求めて這いあがる
不要の胸乳をかき抱き
越えねばならない尾根づたい
土蔵の暗がりにはかみ殺す泣き声が湿る
乳の出ない母親は
もらい乳を聞き歩き
かんかんの乳房は乳呑み児を探す
女は不浄 産む道具とされた時代の女達に
産褥の休養はわずか
赤い信女は昔日の腐心を若い女に語り継ぎ
ほっとしたように目を落とした
呑ませきった幸運の乳房
だが真白い血は傲慢な理念だったかと
こぼれる肉塊をこの掌に掬いあげる
蕾の唇とちぶさは不幸ではならない
授乳の面輪には
幼い双眸が棺に入るまでくらいつく
石川 逸子 イシカワ イツコ
①1933(昭和8)2・18②東京③お茶の水女子大学史学科卒④「兆」「詩区かつしか」⑤『定本・千鳥ヶ淵へ行きましたか』影書房、『ゆれる木槿花』花神社、『〈日本の戦争〉と
詩人たち』影書房。
雲のささやき
のったり とろり ゆらり ゆうらり
ほわり ほわっか ふうわり ほほり
立春ながら 風はとりわけつめたいのに
雲さん てんでにお昼寝してるんですかあ
いかにものんきに見えますよう
〈ふふ 浮かんでた甲斐あったかも〉
〈せこせこ人間たち
心のトゲ少し消えるかな〉
〈おせっかいだよね あたしたちも〉
〈地上があんまりとんがってると
せつないからなあ〉
〈そう そう〉
のったり雲たちの ささやきを
かすかに聞いたのは
病気のキジバトと 枯れ木の先っぽの
赤いサクラのつぼみだけのようです
石川 敬大 イシカワ ケイダイ
①1952(昭和27)11・10②福岡④「侃侃」⑤『フィルターごしの恋』梓書院、『北一輝の帽子』『九月、沛然として驟雨』書肆侃侃房。
夏のキャンバス
ほそい茎はストローで
とても深いところから水を汲み
花弁の皿を
オレンジの果汁で満たす
それを飲み干すのはだれなのだろう
はるかに南の島を望む
城跡に立って
殉教者たちの石碑にうなだれて祈る
わたしは
信者ではないけれど
不慣れな指先で
そっと十字を切ってみる
ひまわり畑は
夏の風にも黙って立ち
わたしの問いに
なにも応えてくれないけれど
落ちてゆく夕陽に
いっせいに頭をまわし
首を折って鎮まっていた
石黒 忠 イシグロ タダシ
①1937(昭和12)3・28②北海道③日本大学文学部国文学科中退⑤『仕掛弓・悲歌』『水辺にて』潮流出版社、『金子光晴論』土曜美術社出版販売。
もう翡翠の蝉を副葬品にしても始まらない
大きな幕が用意されたものである
空がすっぽりつつみこまれ
星一つ みえない
救急車のサイレンと大声のアナウンス
高所平気症のスピッツ駆けるベランダの下は
マッチ一本で火の海になる
迷路も高低差も呑み込む河畔の扁平な街並み
視界の果ては
タワー・マンションの棒グラフ
海への衝立 極限までの土地利用
林立する高層建築は 鬼っ子
天井破りの積乱雲タワーの元凶
ゲリラ豪雨は ノアの方舟をも押し流す
壁面を太陽電池のパネルに姿を変えようと
屋上庭園を果樹園で飾ろうとも
マチュピチュのようには残りえないだろう
シベリヤでは永久凍土が溶け出し
牧草地を湖沼地帯に変え チベットでは
砂漠化した草原が 大きな湖を呑み込もうと
している
①1937(昭和12)9・17②神奈川③中央大学文学部卒④「時間と空間」⑤『そこだけが磨かれた』時間社、『聖牛』『石棺』『槐の花』思潮社。
朽木舟
蝶は 葎の上を這い飛び
蝌蜴は 壁にはりつき
寝ても 覚めても
目を瞑れば なおも
溺るるばかりの 虫のしぐれ
「松虫」の音に 魂魄吸われ
阿倍野の原の 闇に臥し
空しくなった 昔男のような
虫の音の 葬送のなか
朽木舟に 身を託し
このまま 行方知れずになろうかとも
石原 武 イシハラ タケシ
①1930(昭和5)8・3②山梨③明治学院大学文学部英文学科卒④「地球」「日本未来派」⑤『軍港』思潮社、『飛蝗記』花神社、『ケネス・パッチェン詩集』土曜美術社出版販売、『遠いうた 拾遺集』詩画工房。
マフラーに寄せるソネット
後ろ手に縛られ絞首台に立ったフセインは
顎を突き上げ
俺は殉教者だと
目隠しの頭巾を拒否した
唾を吐きアメリカと異教徒を呪った
縄が首にかかったとき
縄は固くて首を傷つけるから
マフラーを巻いてやると刑吏が言った
フセインは大きく頷き
マフラーの恩寵にすがって
穴の底に落ちて行った
わが処刑の日には
神よご慈悲で おお
雪の逢瀬に巻いた薔薇色のマフラーを
伊集院 昭子 イジュウイン アキコ
①1944(昭和19)9・7②千葉③東京YWCA学院秘書養成部卒④「地球」「日本未来派」⑤『フーガ』現代詩工房、『パラソル』地球社、『忘れかけていた男』土曜美術社出版販売。
メッセージ
はじまりはあなたから
一月の汀
新しい岸辺でゴールが輝く
いつもの場所で開花する
春を知らせる白梅
気高く生きるあなたのよう
見つけましたか
四つ葉のクローバー
あふれる希望と幸福を
さあ扉を開いて
芽吹いている 今
羽ばたくあなたに
「エイプリル ラブ」
風に揺れるすずらんの花
緑の葉かげでやさしく奏でる
あなたは五月の音楽家
泉沢 浩志 イズミサワ ヒロシ
①1924(大正13)9・16②福島④「光線」「竜」「モノローグ」⑤『三月の中で』クレーンブックス刊行会。
闇の隙間
不図 訝るまなこに映るのは
では と手をあげて曲った
文明の青白い背中だ
やがて、デジタルの向こうに溶けるだろう
そして所在なく 何処か
べつの世界の棧を探る手つきが
つゆ知らず己の首を締めてしまう
おお たどたどしいこの充血!
ぜんたい 何を絞りだすのだ
ぼくの
いがらっぽい一日から
ぼくには もう何んにも無かった
大の字
に消えてゆく痺れのイメージすら
いつかな見失ってしまう
夜光塗料の染みた小さい「時」を 腕に點し
て
泉谷 明 イズミヤ アキラ
①1938(昭和13)1・1②青森③弘前大学教育学部卒④「亜土」⑤『ぼくら生存のひらひら』『濡れて路上いつまでもしぶき』津軽書房、『ぼくの持てるすべての抒情を吹きとばし』『ひとひとり』路上社。
なにか
流れる川を見るように
風の道をみつめています
そこにはなにか
揺れる道ばかり
すりぬける風でわかります
そこにはなにも
ないこと知っています
なのにきっと
それですわりつづけます
風ばかり
こころくたくたに
強く抱きしめられるなにか
みつけられるものとしてなにか
あるいは
ぼうとまねいているなにか
そんな道が見えてくるんじゃないかと
あるいは
なにか
①1929(昭和4)3・19②兵庫③興亜専門学校(旧制)中退④「階段」⑤『龍鐘譚ほか』詩画工房、『神戸の詩人たち』編集工房ノア、『伊勢田史郎詩集』土曜美術社出版販売。
存在
銀行のファサード
たれもいなくなる午後三時
落日は やがて 光の箭となって
きらきら 大理石の階段に撥ねかえる
噴水の飛沫
メタボリック状の鳩の群れ の 羽根
ぎらぎら
広場の敷石 ジャガーの
とつぜん 夕闇が来て
野犬が 鳩を銜え 跳躍した
ゆっくり と 立ち上がってくる
石段に蹲っていた たれか
いつか見たことのある 忘却曲線上 の 影
灼きつけられ 剥ぎとられかけている
ヒロシマの 人
*原爆の強烈な熱線に灼かれた人の影が、かつて銀行の
石段の上に存在していた。
伊勢山 峻 イセヤマ シュン
①1931(昭和6)3・30②東京③東京学芸大学中等教育学科卒④「青衣」「青い花」⑤『横切る人』青衣社、『火?』土曜美術社出版販売。
花いちもんめ
真夏の昼下がり
一ちゃんは 一人ブランコに乗っている
欅の木陰で 横に手をつないだ園児の列
――ふるさとまとめて 花いちもんめ
列は前に進んだり 後ろに下がったり
――和ちゃんが欲しい
向き合った列からも
――利ちゃんが欲しい
わらべ歌の起源には 残酷な物語もあるが
園児たちの声は明るく
途切れると蟬の声が一段と激しい
二人がじゃんけんをしている
一ちゃんは勝ち負けがわからないから
仲間には入れない
じじっと足元に?が落ちた
一ちゃんは蟬を踏みつぶして
立ち上がり
――一ちゃんが欲しい と叫んだ
積乱雲が激しく盛り上がってきた
磯貝 景美江 イソガイ ケミエ
①1932(昭和7)6・17②千葉③慶応義塾大学通信教育中退④「日本未来派」⑤『躍動』掌詩人社、『もうひとつの窓』東京文芸館、『小さな城』書肆青樹社。
雲上に生きる
銀色に純白に、やや黄金色も添えて
光り輝く雲が大きく高く
勇壮に湧きあがって来る
遠く近く幾重にも連らなる
鮮やかな山裾を覆い尽くし
目の前の風景に、吸い寄せられる
かつて幼児が這い、立ち
滴る緑の涼風を子守歌にのせて
添い寝もして来たぬくもりが漂う
小さな手垢の泌みは
何ものにも替えられないが
襖をいっせいに張り替えると
真新しい生まれたばかりの、雲海となった
それは襖の、明るいアイボリの和紙の地に
描き出された名画から
さわやかな空気が立ちのぼり
何処までも展ける
大自然が生み出した、パノラマだ
日々雲の上で目覚め、雲の上で眠る
いだ・むつつぎ イダ ムツツギ
①1933(昭和8)1・7②静岡③神奈川大学法科二部卒④「詩人会議」「京浜詩派」⑤『ぼくら人間だから』水曜社、『よこはま小動物詩集』横浜詩人会議。
竜はいた
前へ動いていく明かり
長く長くつながった明かり
ザーザーザーザーザー
明かりは足音をたてて進む
明かりはたくさんのちょうちん
町は明かりでいつもとちがう
明かりは冷えこむ北風に向かう
それでも
明かりは一段と大きな声
九条まもれのこえは
町のウラ通りまでひびく
そのとき異様な光景
明かりのうねりが竜に見えた
しばらく やはりその姿
圧政から庶民をまもる竜はいた
竜は赤々と燃えながら
一気に坂を上っていく
伊丹 公子 イタミ キミコ
①1925(大正14)4・22②高知③伊丹高女卒⑤『通過儀礼』求龍堂、『空間彩色』『赤道都市』『天球 水球』冬樹社、『カンボジアの壁』春陽堂書店、エッセイ集『詩人の家』
沖積舎。
晩夏
晩夏のひかりが好きだ
人間が発光体なのか
周りの葉っぱがそうなのか
かがやいていた真夏の時間
プールで海豚のように
水を散らしていた子供たち
とおい日マレーシアからやってきた
虎の足跡が残されていた南洋のホテル
ばっさと明るい昨日までのひかりが去り
晩夏の光線は
とめどなく人を優しくする
親しかったひとびとのおおかたは
死んでしまった
そのひとびとを思うにふさわしい空気
庭でアロエの夏?せした葉がゆれる
夏の音楽の何もかも消えてしまった
ちょっと気弱な
晩夏のクリスタルふうなひかりが好きだ
市川 愛 イチカワ アイ
①1939(昭和14)2・10②埼玉③慶応義塾大学文学部国文学科卒④「WHO’S 」⑤『舞踏、ほか』『小さな村の四季』花神社。
誰だっけ
エレベーターからロビーに飛び出した出会
い頭 要介護四の夫に「誰だっけ?」と言わ
れてしまった えっ! そこまで進んでし
まったの認痴症「私よ、私」青くなって叫ん
だ
申しわけなさそうな顔が緩み ニコニコ
笑っている あゝ良かった解ったらしい
でも私って誰なんだろう 「アイ子」とい
う固有名詞が通じないとすれば どう説明で
きるのだろう まだ言葉がかなり通じていた
頃 「今日って何」と怒った口調で詰問され
た時も お手上げだったけれど
それ以来だろうか
「今日」が宙に浮いてしまったような
私の日々 そして今度は
「私」も形を無くしてしまいそう
重心が定まらない私が
後ろばかり振り返っているから
宙に浮いてしまう「今日」
漂ってばかりいる「今日」だから
はっきりしない「私」の形
市川 つた イチカワ ツタ
①1933(昭和8)3・25②静岡④「回游」「新現代詩」「光芒」⑤『白い心象画』新詩人社、『刻をつなげて』土曜美術社出版販売、『回游』回游詩人社。
幸せを包む
年が変わると
幸せを新しい包装紙で包みなおす
一年間手垢にまみれたそれは
時々通行手形のように見せたもの
今年は少し派手な包装紙にした
派手すぎると思ったがこれくらいしないと
幸せなんて包み切れるものではない
幸せですかって誰かに聞かれたら
甘やかな包装紙のまま
ふんわり 柔らかいでしょ温かいでしょ
なんて手に乘せながら決して開けては見せな
いの
いい慣らわした幸せは辛くても苦くても
掛け替えの無いものだから
見えなくてそれでいいの
気持ちの置き場所にも拠るから
私はこれくらいで飛びっきり幸せだから
それを包むにふさわしい
明るくって綺麗な包装紙を選んだ
市原 千佳子 イチハラ チカコ
①1951(昭和26)4・21②沖縄③千葉敬愛短期大学初等教育科卒④「歴程」「宮古島文学」⑤『海のトンネル』修美社、『太陽の卵』思潮社、『新選沖縄現代詩文庫①市原千佳子
詩集』脈発行所、『詩と酒に交われば』あすら舎。
浮族
道は地球にからんで伸びる その上を
タイヤはころがり進む
人もまた からまり ころがり
ときにふみはずしたりして通る
前に進むためのカラクリはまがりくねり
その先でも きりもみ
もみじの意を決したようなきりもみ
露天の温泉に夜がきて
からだのアウトラインが消えると
まるい月が水面にやってきた
ああ浮いている。月。もみじ。
そう浮いている。この球。この球の 人。
億年の昔からそうだった
みんな浮族だった
それぞれの間にならくの闇をおいて
悠久の呼吸で闇を密にして
だからあんなにも星々は美しく遠い
宇宙の 地球の 温泉の 闇の底で 泣いた
ふみはずして泣いた
男と女の愛はさみしさがちいさすぎる
浮族としては胸をはれない
市村 幸子 イチムラ サチコ
①1947(昭和22)1・25②北海道③藤女子短期大学卒④「光芒」⑤『人の芽』草原舎。
たんじょう
羊水の流れに漂い
見ることも 聞くことも 触れることも
内なる秘めごと
そんなあなたが くるみもっていたものを
語っておくれ
こうのとりの爪あとを
刻みこんで生まれてきた あなた
あなたが どこからやってきたのか
その魂のふるさとで 見てきたものを
語っておくれ
あなたを見つめるわたしの視線を素通りして
はるか彼方の世界と交信している あなた
急がねば 急がねばならない
あなたのまなざしが
わたしの視線と結び合うまえに
あなたの瞳に
この世のもろもろのことが 写し出されるま
えに
語っておくれ
一色 真理 イッシキ マコト
①1946(昭和21)10・19②愛知③早稲田大学第一文学部露文専修卒⑤『純粋病』詩学社、『DOUBLES』沖積舎、『元型』『偽夢日記』土曜美術社出版販売。
ネガ
白い夜空を割って
真っ黒な月が沈みかけている
自分が本当にここにいるのかどうか
不安でたまらない
鏡という鏡を自分の周りに置いて
自分を映してみる
たくさんの自分を見ていると
ますます自分がそこにいない気がしてくる
自分の外側に自分がどんどん流れ出てしまい
中心がからっぽになっていく
ぼくはいつのまにか自分を裏返しにしてしま
い
袋の中身を全部こぼしてしまったのだ
月がとうとう固い地面に激突して
血と肉と骨が西の空いっぱいに砕け飛んだ
いで あつし イデ アツシ
①1932(昭和7)11・15②東京③東北大学医学部卒④「山形文学」⑤『マリーのお尻』『樟脳の舟』深夜叢書社。
iの歌(連作の一つ)
iは晒し首
朝靄の中から
浮かび上がって来るのである
きのうの夕日は
いやに赤茶けて
浄土平の方へ落ちていった
ぼくはその時
冗談めかして云ったのだ
「世界の中心が
十円銅貨になって
裏返しに墜ちて行くとは
実にいい気味だ」
しかし
一つの用意された首がうたれ
うたれて墜ちるまでが
ぼくの今日の一日
と知っていたのだ
怖くてならなかったのだ
伊藤 勳 イトウ イサオ
①1949(昭和24)9・19②岐阜③明治学院大学大学院卒④「未開」⑤『風紋』書肆山田、『一元の音』花神社、『流光』檸檬社。
ミノスのゆりの王子
牛の角を摑んでその背を跳び越えたり
猿どもが岩山のサフランを摘んだり
宮殿の壁面を海豚が泳ぎ回つてゐた頃
神々の依り代の人に物象にすべては一碧の水
原子は結んでは解けても生成も消滅もせず
宇宙は万華鏡のからくりを楽しませてくれる
ただ触れ合ふことだけがすべて
時は持続せず記憶の中でただ推移してゆく
三千六百年の時の狭間は谷となつて抜落ちて
向岸が切り立つて迫り「今ここ」にある
岩肌に源流のしづくが光を集めて丸い
澄んで色づく軽やかな影となつて生きてゐる
アタラクシアの朝
ゆりは花びらが渦巻いて目となり人となり
をとこともをんなともつかぬ神官は
ゆりとなり風となり共にをどる
多島海の水晶質の潮が晴れた横顔を掠めれば
海は渦巻となり連なつて連渦の紋
あや
となり
宮殿をめぐり棺へと流れてゆく
遠くこだまを交はして
伊藤 勳 イトウ イサオ
①1934(昭和9)②福島③日本大学芸術学部演劇学科卒④「VOU」⑤『トークトール フルーク』『イマアジュ ジャック』昭森社、『最後の審判』プレス ビブリオマーヌ。
詩詩繍繍
これは詩繍である
で始まり
これは詩繍ではない
で終わる
どこかに一冊の詩繍がある
しかし一行目は失敗である
よって一百三十七ペェジは削除する
それゆえにこの詩繍は完璧である
どこかに一冊の詩繍が存在する
決して書かれない詩繍
絶対に読まれない詩繍